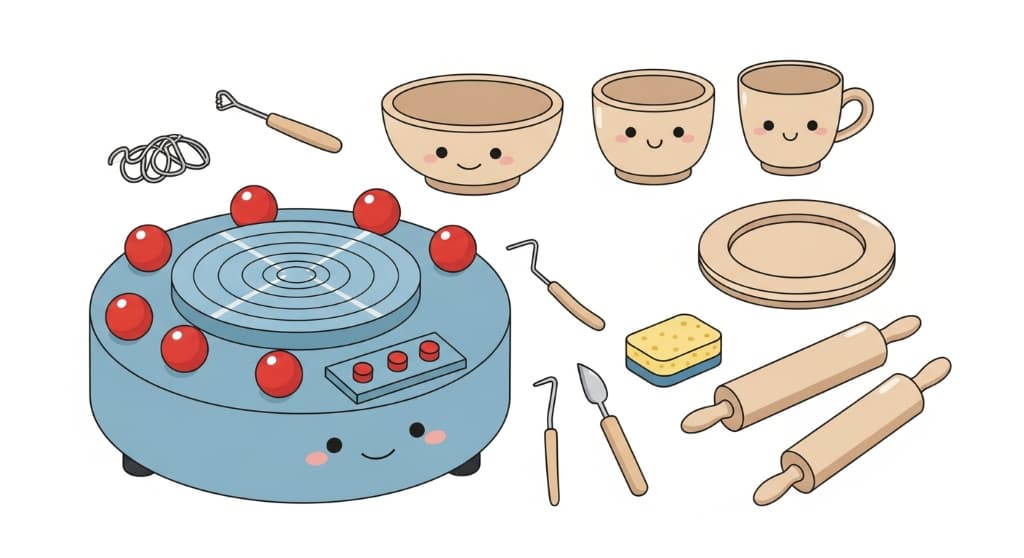陶芸初心者が本当に買うべき本はこの3冊!私が遠回りして見つけた最適ルート、教えます

「よし、陶芸やってみよう!」
その気持ち、めちゃくちゃ素敵です。でも次の瞬間、「…で、何から始めれば?」って固まっていませんか?とりあえず本でも、と思って本屋に行ったら、専門書がずらりで圧倒されて、そっと棚に戻す…なんて経験、ありませんか?(ええ、何を隠そう、かつての私です)
もう遠回りはさせません。結論から言いますね。陶芸初心者が最初に手に取るべき一冊は、あなたの心を「これ作りたい!」と鷲掴みにする、美しい作品集です。難しい技術書は、その次でいい。いや、その次じゃないとダメなんです。なぜなら、その「作りたい!」という初期衝動こそが、面倒な土練りや難しい専門用語を乗り越える、最強のガソリンになるから。
この記事では、数々の本を読み比べ、時には「うーん、これは違った…」という失敗も重ねてきた私が、心から「最初に出会いたかった!」と思う実在の書籍を、その魅力と根拠をしっかりとお伝えしながら厳選してご紹介します。さらに、あなたが本屋で迷子にならないための「自分だけの最高の一冊を見つけるコツ」まで、私の体験談を交えながら、余すところなくお話しさせてください。
もう本選びで迷いません。そして、ただの粘土の塊が、あなたの手の中で愛おしい「うつわ」へと変わっていく、その素晴らしい世界の扉の前に立っているはず。一緒に、最高の一冊を探す旅に出ましょう!
初心者の本選びは「技術」より「作りたい!」の発見がすべて

いきなり核心を突きますが、陶芸を始めたいあなたが本を選ぶとき、一番やってはいけないのが「完璧な技術書」から入ること。もちろん技術は大事ですよ。でも、それは二の次、三の次。最優先事項は、あなたの心に「うわ、これ作りたい!」という火を灯してくれる一冊を見つけること。これ、テストに出ます(笑)。
なぜ「作り方」の本から入ると挫折しやすいのか
昔の私に言ってやりたい。「おい、その分厚い本じゃ無理だぞ!」と。
やる気に満ちていた私は、陶芸を始めようと決意したその足で本屋に向かい、『陶芸技法大全』みたいな、いかにもプロが読んでそうな本を買ったんです。これで完璧なスタートが切れる、と。でも、ページをめくって数分後には、もう心がポッキリ折れていました。「菊練り」「還元焼成」「いっちん」…知らない言葉のオンパレード。写真を見ても、達人の滑らかな手さばきは、もはや異次元の魔法にしか見えません。
結局、その本は美しい”積読”となり、私の陶芸への第一歩を重く、遠いものにしてしまいました。そう、技術書は、ある程度の知識や経験があって初めて「なるほど!」と理解できる”答え合わせ”の本なんです。地図も持たずにいきなりラスボスの城に乗り込むようなもの。そりゃ、心が折れますよね。
「このお皿、素敵!」その感動があなたを動かす最強のエンジン
じゃあ、どうすればよかったのか。答えは本当にシンプルでした。先に「ゴール」を見つけること。つまり、「この作家さんのような、温かみのあるマグカップを作りたい」「こんな渋いお皿を自分で作って、お刺身を盛り付けたい」という、具体的で、胸がときめくような憧れを持つことです。
「これを作りたい!」という強烈な目標が定まると、あれだけ意味不明だった専門用語が、ゴールへたどり着くための「キーワード」に変わります。難しい土練りだって、「このいびつだけど味のあるお茶碗を作るために必要な工程なんだ」と思えば、俄然やる気が出てくるから不思議。
モチベーションが、技術的な問題を「乗り越えるべき課題」から「知りたい!」という探求心へと変えてくれるんです。だから、まずはあなたの心を揺さぶり、インスピレーションを与えてくれる、美しい作品がたくさん載っている本を探すこと。絶対に、その方が陶芸ライフのスタートは楽しく、そして長続きします。私が、身をもって保証します!
私が本気で推す陶芸初心者向けバイブル3選

ここからは、私がこれまで出会った本の中から、特に「初心者の頃の自分に、これをプレゼントしたい!」と心から思う、実在する書籍を3冊、厳選してご紹介します。なぜこの本が素晴らしいのか、その理由と根拠(公式サイトなどのURL)も併せて、熱量たっぷりで語らせてください!
1. まずは陶芸の全体像をつかむ!『はじめての陶芸』(成美堂出版)
「そもそも陶芸って、何から何まで、どうなってるの?」という、まさに”?”だらけのあなたに、まず手に取ってほしいのがこの一冊。私がこの本を推す理由は、とにかく「写真が大きくて、時系列で、めちゃくちゃ親切」だからです。
土の準備から、ひも作り、タタラ作りといった基本的な成形方法、そして削り、乾燥、素焼き、釉がけ、本焼きまで…陶芸の一連の流れが、まるで隣で先輩が「次はこうやるんだよ」と教えてくれているかのように、丁寧に解説されています。特にいいなと思ったのが、失敗例とそのリカバリー方法まで載っていること。「あ、ヒビが入っちゃった!もうダメだ…」なんて落ち込む前に、この本を開けば「なるほど、こうすれば修正できるのか」と、次に進む勇気をもらえます。
難しい理屈は後回しで、「ふーん、こういう流れで器ってできていくんだ」と、まずは全体像をぼんやりとでも掴むこと。この一冊をパラパラと眺めておくだけで、いざ陶芸教室に行ったときの先生の話の理解度が、驚くほど変わりますよ。まさに”はじめて”の相棒にふさわしい、お守りのような本です。
2. あなたの「好き」が絶対見つかる!『うつわを愛する』
さあ、ここからが本番です!私が熱弁する「作りたいものを見つける」ための最高の一冊が、この『うつわを愛する』。これは技法書ではありません。陶芸家、料理家、編集者など、様々な分野で活躍する何人もの「うつわ好き」たちが、自身の愛するうつわについて、その魅力や出会いを熱く語るエッセイ&写真集です。
この本の何がすごいかって、登場するうつわの多様性。骨董の渋いお皿から、現代作家のモダンなカップ、海外の素朴な民藝品まで…ページをめくるたびに、全く違う表情のうつわたちが現れ、あなたの感性を揺さぶってきます。そして、ただ美しいだけでなく、それが実際に食卓で使われている様子や、語り手のうつわへの愛情が伝わってくる文章を読むうちに、「ああ、いいなあ」「私もこんな風に、自分の作ったうつわを暮らしの中で使ってみたい」と、自然と創作意欲が湧いてくるんです。
私がこの本を読んだとき、「そうだ、私が作りたいのは、完璧な作品じゃなくて、日々の暮らしに寄り添ってくれる、愛おしい”相棒”みたいなうつわなんだ」と、自分の目指す方向がハッキリと見えました。あなたの「好き」の引き出しを無限に広げてくれる、インスピレーションの源泉。ぜひ、じっくり味わってみてください。
3. 一歩進んで「なぜ?」がわかる『陶芸の釉薬』(誠文堂新光社)
最後は、少しだけステップアップした一冊。でも、これを知っておくと、陶芸の面白さが10倍、いや100倍になります。それが、この『増補改訂 陶芸の釉薬』です。
「え、いきなり釉薬(ゆうやく)専門!?」って思いましたよね。わかります。でも、陶芸の魅力って、形を作る面白さと同じくらい、「色」を決める面白さがあるんです。この本は、その「色」の正体である釉薬について、写真と具体的な調合データ付きで、めちゃくちゃ分かりやすく解説してくれています。
初心者のうちは、教室にある釉薬を「じゃあ、この青いやつで」みたいに感覚で選びがち。でも、この本を読めば、「この美しい織部(おりべ)の緑は、こういう成分でできているのか」「このマットな質感は、藁灰(わらばい)を入れると出るんだ!」という、「なぜ?」がわかるようになります。この「なぜ?」がわかると、作品を見る目が変わり、作るときの深みが全く違ってくる。
もちろん、最初から全部を理解する必要はありません。パラパラとめくって、「うわ、このトルコ青、綺麗だな…」なんて、美しい釉薬のテストピース(色見本)を眺めるだけでも眼福です。そして、自分の作品に釉薬をかける段階になったとき、この本が手元にあれば、あなたはもう「言われたからこれを塗る」初心者から、「この色を出したいから、この釉薬を選ぶ」という、一歩進んだ作り手になっているはず。あなたの陶芸ライフを、長く、深く支えてくれる専門書として、これ以上ない一冊です。
もう迷わない!自分にぴったりの陶芸本を選ぶ3つのコツ

ここまで私のおすすめを紹介してきましたが、最終的には、あなた自身が「これだ!」と思える本を見つけるのが一番です。ここでは、本屋さんで迷子にならないために、自分にぴったりの陶芸本を選ぶための、具体的な3つのコツをお伝えします。
コツ1「写真と図解の多さ」は正義!視覚情報で選ぶ
これはもう、絶対的なルールです。特に初心者のうちは、文章だけで陶芸の技術を理解しようとするのは、正直言って無理ゲーです。陶芸は、手の微妙な角度、土を押さえる力加減、道具の当て方など、言葉では伝えにくい「感覚」の連続だからです。それを補ってくれるのが、大きくてわかりやすい写真や、親切な図解の存在。
本を手に取ったら、まずは中身をパラパラとめくってみてください。文字がぎっしり詰まっている専門書は、今のあなたには必要ありません。そっと棚に戻しましょう(笑)。そうではなくて、一つの工程ごとに写真が何枚も使われていて、手の動きや道具の使い方がアップで写っているものがベストです。
「百聞は一見に如かず」とはよく言ったもので、陶芸の本選びにおいては、まさに「写真や図解の多さは正義」です。視覚的に「なるほど、こうやるのか」と理解できることが、挫折しないための、そして上達への一番の近道なんです。
コツ2「今の自分」のレベルと目的を正直に見つめる
次に大切なのが、「今の自分に本当に必要な情報は何か?」を冷静に考えることです。やる気に満ち溢れていると、ついつい背伸びして難しい本に手を出しがちですが、それが一番の落とし穴。
まずは、自分のレベルと目的を正直に見つめ直してみましょう。
「まだ土も触ったことがない、全くの初心者?」
「手びねりで、温かみのあるマグカップを作ってみたい?」
「いや、もうロクロに挑戦して、シュッとしたお皿が作りたい?」
「形よりも、きれいな色の釉薬や、かわいい絵付けに興味がある?」
例えば、全くの初心者で、まずは手びねりから始めたいと思っているのに、電動ロクロの上級者向けの技法が満載の本を買っても、宝の持ち腐れになってしまいますよね。当たり前のようですが、人は興奮すると、意外と自分の現在地を見失いがちなんです。
「あれもこれもできるようになりたい!」という気持ちは素晴らしいですが、まずは一歩ずつ。今のあなたが一番知りたいこと、一番やってみたいことに焦点を当てて本を選べば、無駄な出費も防げるし、何より得た知識をすぐに実践に移せて、楽しさをダイレクトに実感できますよ。
コツ3「この人の作る器、好き!」その直感を何より信じる
最後のコツは、少し意外に思われるかもしれませんが、「著者の作風」や「掲載されている作品のテイスト」で選ぶ、ということです。これ、実はめちゃくちゃ大事なポイント。技法書って、どれも同じように見えて、実は著者の作家性や美意識が色濃く反映されているんです。
本に掲載されている作例を見て、「わ、このお茶碗、すごく好み!」「この色合い、真似してみたいなあ」と、あなたの心がときめく本を選んでみてください。なぜなら、その本に書かれている技術やコツは、すべて「その素敵な作風の器を作るため」に最適化されたものだからです。自分が「好き」だと思えるゴールに向かって学ぶ方が、モチベーションが段違いに上がります。
例えば、私が好きな作家さんの技法書は、たとえ説明が少し難しくても、載っている作品がとにかく魅力的だから、食い入るように読んでしまいます。「この絶妙な歪みはどうやって出すんだろう?」「このマットな質感にするための釉薬の調合は…」と、自然と探求心が湧いてくる。あなたの「好き」という直感は、あなたにとって最高の先生です。その心の声を信じてみてください。きっと、あなたと相性ぴったりの、長く付き合える一冊に出会えるはずです。
まとめ 最高の1冊はあなたの陶芸ライフを何倍も豊かにしてくれる

さて、陶芸初心者のための本選びについて、私の体験と想いを込めて語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。
一番伝えたかったのは、最初の本選びは、単なる情報収集ではないということ。それは、あなたの「作りたい!」という情熱の種火を見つける、宝探しのような旅だということです。分厚い技術書で頭でっかちになるよりも、まずは美しい作品集を眺めて「こんなの作りたいなあ」と胸をときめかせる方が、ずっとずっと大切なんです。その「好き」という最強のエンジンさえあれば、難しい技術の壁だって、きっと楽しみながら乗り越えていけます。
今回ご紹介した『はじめての陶芸』で全体像をつかみ、『うつわを愛する』でインスピレーションのシャワーを浴び、『陶芸の釉薬』で一歩先の面白さに触れる。このルートは、私が自信を持っておすすめできる、遠回りしないための最適ルートです。
もちろん、最終的にあなたの心を動かす一冊は、あなた自身が見つけるもの。ぜひ、この記事を読んだら、本屋さんや図書館に立ち寄ってみてください。そして、表紙に、写真に、著者の想いに心惹かれた本を、気軽に手に取ってみてください。その一冊との出会いが、あなたの日常に、土の匂いと手作りの温もりをもたらしてくれる、素晴らしい陶芸ライフの始まりになるはず。最高の相棒を見つけて、あなただけの作品を生み出す喜びを、ぜひ味わってくださいね。