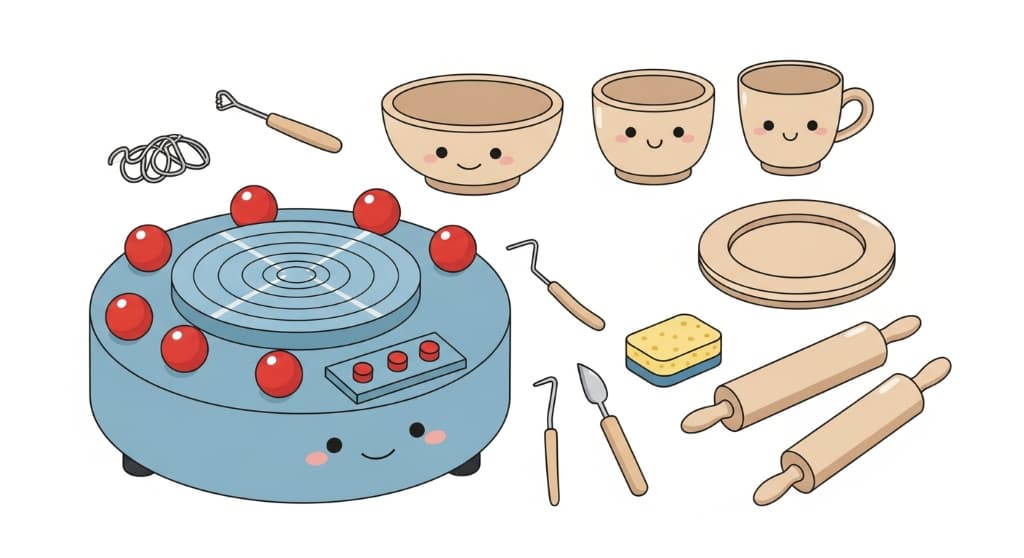陶芸を初めてやるときは何を作るのが良いですか?

土をこね、形を作り、世界にたった一つのうつわを生み出す「陶芸」。なんだか憧れるけど、自分にできるかな…?不器用だし、難しそう…。そんな風に思っていませんか?わかります。私も最初はそうでした。
でも、初めての陶芸、絶対に楽しいです。そして、何を作るか迷っているなら、答えはもう決まっています。それは「お茶碗」か「湯呑み」です!
なぜなら、この二つには陶芸の基本的な楽しさと難しさ、そして完成した後の「使う喜び」という最高のご褒美がギュギュッと詰まっているから。この記事を読み終わる頃には、あなたはきっと土を触りたくてウズウズしているはず。陶芸体験教室の予約ボタンを、ポチッと押してしまうかもしれませんよ。あなたの手から生まれる、愛おしい「最初の一個」を作るための、最高のエスコートをさせてください!
初めての陶芸は「お茶碗」か「湯呑み」で決まりです

「え、もっとオシャレなものとか、オブジェとかじゃなくていいの?」って思いました?もちろん、作りたいものを作るのが一番です。でも、もしあなたが「何を作ればいいかわからない」「せっかくなら陶芸の醍醐味を味わいたい」と思っているなら、騙されたと思ってお茶碗か湯呑みを選んでみてください。
これこそが、初心者が陶芸の沼にハマるための、王道にして最強の入り口なんです。なぜなら、この二つは陶芸の基本工程をしっかり学べて、かつ、日々の生活でこれでもかというくらい使えるから。これ、本当に大事なことなんですよ。
理由その1 陶芸の基本「作る・削る・彩る」が全部詰まっているから
陶芸って、ただ粘土をこねて終わりじゃないんです。ざっくり言うと、「成形(形作ること)」「削り」「施釉(釉薬をかけること)」という大きな3つのステップがあります。そして、お茶碗や湯呑みは、この3つの工程をバランスよく体験できる、まさに「陶芸の教科書」みたいな存在なんです。
まず「成形」。手びねりなら、粘土の塊から自分の手のひらを使って、少しずつ形を立ち上げていく。この、土が自分の思い通りになったり、ならなかったりする感覚がたまらない!電動ろくろなら、回転する土にそっと指を添えて、にゅーっと器が立ち上がってくるあの瞬間…!感動モノですよ。もちろん、最初はぐにゃぐにゃの物体Xを生み出してしまうかもしれませんが、それすら愛おしい失敗です。
次に「削り」。成形して少し乾かした器の底の部分、「高台(こうだい)」を削り出す作業です。これがまた、地味に見えて奥が深い。カンナっていう専用の道具でシュッシュッと削っていくんですが、この作業で作品が一気に「ただの粘土」から「うつわ」へと進化するんです。ここでビシッと綺麗な高台が決まると、「私、もしかして才能ある…?」なんて勘違いしちゃうくらい、テンションが上がります。
そして最後の魔法、「施釉」。素焼きされた自分の作品に、釉薬(ゆうやく)というガラス質の液体をかけます。この時点では、泥水みたいで全然綺麗じゃないんです。でも、これが窯の中で高温で焼かれることで、美しい色やツヤに大変身する!どんな色になるかは窯から出てくるまでのお楽しみ。このドキドキ感、まるで宝箱を開ける前みたいで、本当にワクワクしますよ。この一連の流れを体験することで、「あ、陶芸ってこうやって作るんだ!」という全体像が、すとんと腑に落ちるはずです。
理由その2 毎日使えるから達成感が半端ないんです
正直に言いましょう。初めて作った作品は、たぶん、歪んでいます。ちょっと厚かったり、薄かったり、綺麗な円じゃなかったりするでしょう。でも、それでいいんです!それがいいんです!
想像してみてください。自分で作った、ちょっと不格好だけど世界に一つだけのお茶碗で、炊き立ての白米を食べる毎日を。自分で作った、指の跡が残る湯呑みで、温かいお茶をすするひとときを…。最高じゃないですか?
お店で売っているような完璧な器も素敵です。でも、自分の手から生まれた器には、お金では買えない「愛着」という最強のスパイスが加わります。ご飯をよそうたびに、「ふふふ、これ私が作ったんだぜ」ってニヤニヤできる。お茶を飲むたびに、土をこねた日のことや、ろくろと格闘した時間を思い出して、じんわり幸せな気持ちになれる。この「使う喜び」こそが、陶芸の最大の魅力だと私は断言します。
作ったはいいけど、棚の奥にしまいっぱなし…なんてことになったら、あまりにもったいない。その点、お茶碗や湯呑みは、ほぼ毎日使いますよね?だからこそ、作った達成感や満足感が、日々の暮らしの中で何度も何度もよみがえってくるんです。これって、すごく素敵なことだと思いませんか?
お茶碗と湯呑みどっちを選ぶ?それぞれの魅力と作るコツ

「よし、お茶碗か湯呑みにするぞ!」と決めたあなた。素晴らしい!でも、ここでまた新たな選択肢が生まれます。「どっちにしよう…?」と。わかります、その気持ち。どちらも魅力的だからこそ、迷いますよね。ここでは、あなたの好みや性格に合わせて、どちらを選ぶべきか、そして作る時のちょっとしたコツを伝授します。
ごはん大好き派なら断然「お茶碗」
三度の飯より飯が好き!そんなあなたには、迷わず「お茶碗」をおすすめします。毎日使うものだからこそ、自分の手にしっくりくる「マイお茶碗」を作る喜びは格別です。
お茶碗作りの基本は「玉づくり」という技法。粘土でボール(玉)を作り、そこから親指でぐりぐりと穴をあけ、少しずつ広げて形にしていく、最も原始的で、土の感触をダイレクトに感じられる作り方です。まるで、自分の手のひらで卵を優しく包み込むように。この時、大事なのが「自分の手にご飯茶碗を持った時の感覚」を思い出すこと。高すぎないか、低すぎないか。指のかかりはどうか。そんなことを考えながら作ると、自然と手に馴染む形になっていきます。
ここで初心者がやりがちな失敗が、欲張って大きく作ってしまうこと。実は、粘土は乾燥して焼くと1〜2割くらい縮むんです!「よし、丼ものもいける大きなお茶碗にしよう!」なんて意気込むと、焼き上がったら「あれ…?思ったより小さい…ていうか、これじゃ猫のエサ皿じゃん…」なんて悲劇が起こることも。そう、何を隠そう私の初作品がそれでした(笑)。なので、完成形より一回り大きいくらいをイメージするのがコツですよ。炊き立てのご飯の湯気が、自分の作ったお茶碗から立ち上る瞬間を想像してみてください。もう、それだけでご飯3杯いけそうじゃないですか?
ほっと一息つきたい派なら「湯呑み」
コーヒーや紅茶、緑茶など、温かい飲み物で一息つく時間が好き。そんなあなたには「湯呑み」がぴったりです。お茶碗よりも少しシャープな形、飲み物が美味しく感じられる口当たり。そんなことを考えながら作る時間は、まさに癒しそのものです。
湯呑みは、お茶碗と同じ「玉づくり」でも作れますが、もし電動ろくろに挑戦するなら、ぜひ湯呑みを作ってみてほしいです。湿らせた手で土に触れると、にゅいーーーんと粘土が立ち上がってくるあの感覚!あれは一度味わうと病みつきになります。もちろん、最初は中心を取る「土殺し」という工程でつまずいたり、ちょっと力を入れすぎてぐにゃっと器が崩壊する「全集中・水の呼吸どころじゃないパニック」を味わったりもしますが、それもまた一興。先生が優しく(時には力強く)サポートしてくれますから、安心してください。
作る時のポイントは、飲み口の厚さ。ここが分厚すぎると野暮ったいし、薄すぎると口当たりは良いけど割れやすくなる。この絶妙な塩梅を探るのが、腕の見せ所であり、楽しいところ。完成したマイ湯呑みで、お気に入りの緑茶を淹れる。両手でそっと包み込むと、じんわりと温かさが伝わってくる…。ああ、なんて贅沢な時間なんでしょう。取っ手をつけてマグカップにアレンジするのも素敵ですね。あなたの「ほっとする時間」に、これ以上ない彩りを添えてくれるはずです。
いやいや、もっと違うものを作りたい!そんなあなたへのおすすめ
「お茶碗と湯呑みが王道なのはわかった。でもさ、私はもっとこう…違うものが作りたいんだ!」という天邪鬼でクリエイティブなあなた。いいですねぇ、その心意気、大好きです!もちろん、陶芸で作れるものは無限大。ここでは、王道以外の選択肢と、それぞれの楽しさ、そしてちょっぴりの注意点をご紹介します。ただし、少しだけ難易度が上がるかもしれないことは、覚悟しておいてくださいね…?
平らな形は意外と難しい「お皿」
「お皿なんて、粘土を平たく伸ばせばいいだけでしょ?簡単じゃん」と思ったそこのあなた。ふふふ、実はそれが大きな落とし穴なんです。「平らで均一な厚さにする」というのが、想像の10倍は難しい。手で伸ばそうとすると、どうしても厚いところと薄いところができてしまって、まるで世界地図みたいな歪な形になりがち。
さらに、お皿は乾燥させる工程で「反り」との戦いが待っています。せっかく綺麗に平らにしたのに、乾燥中にふちがビヨーンと反り返って、焼き上がったらUFOキャッチャーのアームみたいになってた…なんてことも。
じゃあどうすればいいかというと、「たたら作り」という技法がおすすめです。これは、スライスした粘土の板(タタラ板)を使って作る方法。これなら初心者でも比較的均一な厚さの板が作れます。ケーキの取り皿や、アクセサリーを置くトレイ、醤油皿くらいの小さなサイズから挑戦するのが吉。縁を少しだけ立ち上げたり、スタンプで模様をつけたりと、デザインで遊べる楽しさもありますよ。
食卓のアクセントに「箸置き」や「豆皿」
大きなものを作る自信はないけど、何か形にしてみたい。そんなあなたには、「箸置き」や「豆皿」が最高です。なんといっても、小さいから失敗のダメージが少ない!これが精神衛生上、非常に良い(笑)。使う粘土も少量なので、お茶碗などを作った後の余った土で、おまけに作れちゃうこともあります。
そして、小さいからこそ、形やデザインで思いっきり遊べるのが魅力です。葉っぱの形にしたり、ネコや犬の形にしたり、リボン型にしたり…。絵付けで顔を描いたり、模様を入れたり。あなたの創造性をフルに発揮できます。箸置きなんて、5個くらい作って、全部違う形にしても可愛いですよね。
私の友人は、家族全員分の箸置きを作ったんですが、焼き上がったら全部大きさがバラバラで(縮み率を計算してなかったらしい)、一番大きいのがお父さん用、一番小さいのが子ども用、と自然に役割が決まっていました。そんな偶然の産物も、手作りならではの楽しさ。食卓にちょこんと置くだけで、会話が生まれるような、そんな小さなアート作品を作ってみませんか?
難易度MAX?でも夢がある「花瓶」や「徳利」
せっかくやるなら、大物に挑戦したい!そんなチャレンジャーなあなたには、「花瓶」や「徳利」という選択肢もあります。ただし、はっきり言って、これはかなり難易度が高いです!
なぜなら、高さと細さを出す技術が必要だから。特に電動ろくろで、細く、高く、粘土を立ち上げていくのは、かなりの熟練度が求められます。さらに、口をきゅっとすぼめたり、徳利のようなくびれを作ったりするのは、まさに上級者向けのテクニック。初心者がいきなり挑戦すると、ろくろの上で粘土が遠心力に負けて、「さよなら…」と崩壊していく様を、ただ呆然と見つめることになるかもしれません。
でも、夢がありますよね。自分で作った花瓶に、庭で摘んだ一輪の花を飾る生活。自分で作った徳利とお猪口で、きゅっと一杯やる夜。想像しただけで、最高です。もし挑戦するなら、まずは背の低い、小さめの一輪挿しから始めるのがおすすめです。そして何より、「先生、助けてください!!」と素直に助けを求める勇気が大事。先生のゴッドハンドを借りながら、夢の作品を形にする。そんな共同作業も、また良い思い出になりますよ。これはもう、完成度より「挑戦した」という事実そのものが、価値になる体験です。
いざ陶芸へ!その前に知っておきたい心構えと準備
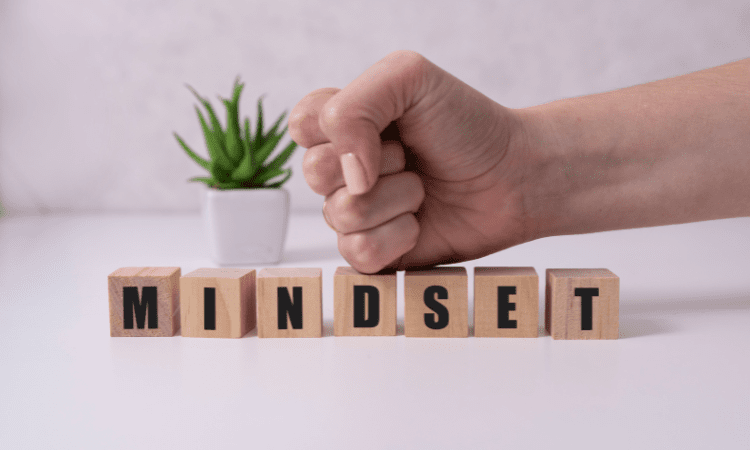
さあ、作るものも決まって、気分はもうすっかり陶芸家!教室に乗り込む準備は万端ですか?…いや、ちょっと待ってください。その燃え上がる情熱はそのままに、当日を120%楽しむための、ほんのちょっとした心構えと準備についてお話しさせてください。これを知っているのといないのとでは、楽しさが全然違ってきます。転ばぬ先の杖、ならぬ、汚れる前のエプロン。そんなお話です。
「完璧」を目指さないのが一番のコツ
これが、もう、一番大事なことかもしれません。断言します。初めての陶芸で、「完璧」を目指してはいけません。
陶芸教室に行くと、先生が作った見本が置いてあります。それはもう、シンメトリーで、すべすべで、寸分の狂いもない美しい形をしています。それを見て、「よし、私もこんなのを作るぞ!」と意気込む気持ち、よーくわかります。でも、その気持ちは一旦、心のポケットにしまっておきましょう。
初めて土に触れるあなたが、いきなりプロのような完璧なものを作れるわけがありません。当たり前です!むしろ、歪んでいいんです。ちょっとくらい傾いてたっていい。厚さが均一じゃなくても、それがどうしたって言うんですか。その不完全さこそが、あなたの「手」が作った証であり、世界に一つしかない「味」であり、「個性」なんです。
綺麗な円にならなくても、「なんか有機的で良い形だね」と思えばいい。表面がボコボコしてたら、「手びねり感があって温かみがあるね」と思えばいい。「味」という言葉は、手作り作品における最強の魔法です。完璧を目指すあまり、うまくいかなくてイライラしたり、落ち込んだりしては、せっかくの楽しい時間が台無しです。不器用で、不格好で、でもなんだか愛おしい。そんな「うちの子が一番かわいい!」みたいな親バカ気分で、自分の作品を愛でてあげてください。その方が、絶対に楽しいから。
当日の服装と持ち物 これだけは押さえて!
さあ、具体的な準備の話です。当日に「あちゃー!」とならないために、これだけは押さえておきましょう。
まず服装。これはもう「汚れてもいい服」、一択です。泥はね、絶対にします。陶芸教室にはエプロンが用意されていることが多いですが、それでも服の裾や袖口は危険地帯。お気に入りの真っ白なブラウスとか、買ったばかりのワンピースとかで来るのは、無謀というものです。昔、私が白いTシャツで行ってしまい、ろくろの泥はねで見事な水墨画アート(?)が完成したことがありますが、全然嬉しくなかったです。ジーンズにTシャツ、みたいなラフな格好が一番。
そして、これも超重要。「爪は短く切っていく」こと!長い爪は、粘土をこねている時に邪魔になるだけでなく、作品に「ズサァッ!」と悲しい傷跡を残してしまいます。せっかく綺麗に形を整えたのに、自分の爪でひっかいてしまった時の絶望感たるや…。ネイルアートをしている方は、特にご注意を。
持ち物は、基本的には手ぶらでOKです。道具も粘土も、全て教室が用意してくれます。でも、もし余裕があれば、「どんなものを作りたいか、簡単なスケッチを描いていく」と、当日スムーズに進みます。頭の中のイメージを、簡単な絵にしておくだけで、先生にも伝えやすいし、自分も迷いません。あとは、汗を拭くタオルくらいでしょうか。そして何より大事な持ち物は、「今日は土と遊ぶぞー!」という、童心に返ったワクワクの気持ちです!
まとめ 最初の一個があなたと陶芸の一生の思い出になる

さて、ここまで「初めての陶芸で何を作るか」というテーマで、熱く語ってまいりました。結論として、やはり私の一押しは「お茶碗」か「湯呑み」です。陶芸の基本が学べて、毎日の暮らしの中で「使う喜び」を実感できる。これ以上に、最初の一個としてふさわしいものはないと、今でも信じています。
でも、もっと大切なのは、あなたの「これ、作りたい!」という心の声に耳を澄ませること。それがお皿でも、箸置きでも、無謀とも思える花瓶でも、構いません。心がワクワクする方へ進むのが、結局は一番の正解なんです。
そして、どうか「完璧」を目指さないでください。あなたの手から生まれる、少し歪で不格好なその形こそが、かけがえのない個性であり、愛おしさの源になります。陶芸は、ただの物作りではありません。土のひんやりとした感触に癒され、日常の喧騒から離れて無心になる時間。自分の手で、自分の暮らしをほんの少し豊かにする、魔法のような体験です。
もし、この記事を読んで、あなたの心の中に小さな灯火がともったなら、ぜひお近くの陶芸教室の「一日体験」を検索してみてください。その一歩が、あなたと陶芸の、そしてあなた自身が作った「最初の一個」との、一生忘れられない出会いになるはずです。あなたの手から、どんな素敵な器が生まれるのか。想像するだけで、私もワクワクしてきます。あなたの陶芸ライフが、素晴らしいものになることを、心から応援しています!