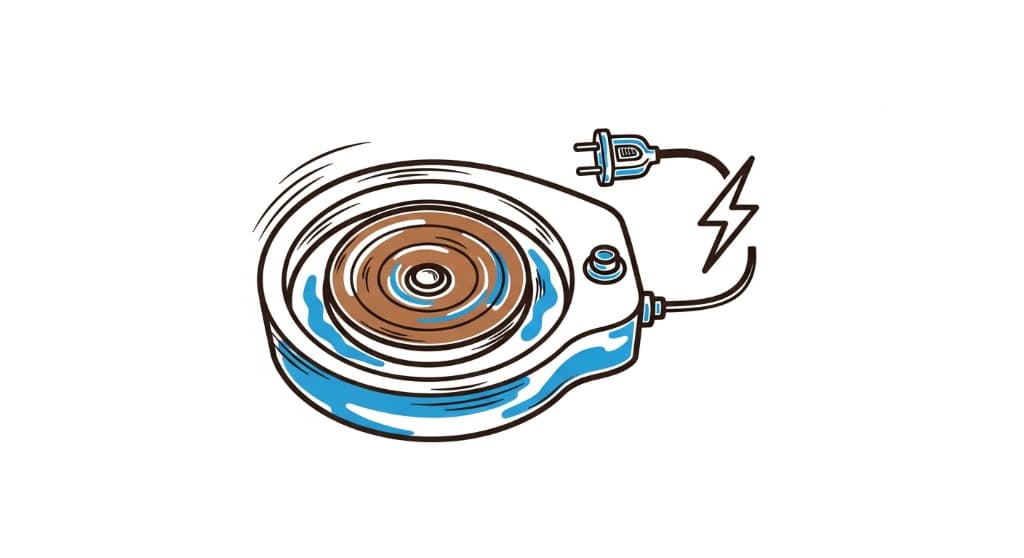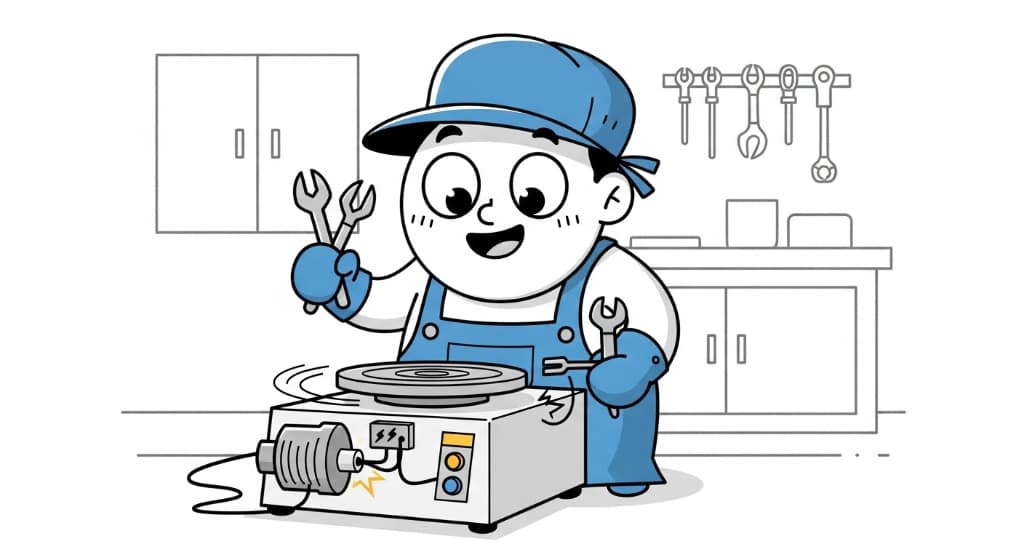【電動ろくろの価格】相場はいくら?初心者が自宅で陶芸を始める夢、叶えちゃいます!

「いつか自分の家で、電動ろくろを回してみたい…」
陶芸に少しでも興味がある方なら、一度はそんな夢を抱いたことがあるのではないでしょうか。静かな部屋で、ひんやりとした土の感触を楽しみながら、くるくると回る粘土の塊が少しずつ形を変えていく…あの時間、最高にクリエイティブで、心が無になる、まさに至福のひとときですよね。私もその魅力にどっぷりハマった一人です。
でも、いざ「自宅に電動ろくろを!」と決意した瞬間、大きな壁が立ちはだかります。そう、「で、電動ろくろって、一体いくらするの?」という、とっても現実的な問題です。検索してみると、なんだかピンからキリまであって、正直よくわからない…。安いのを買って後悔したくないし、かといってプロが使うような何十万円もする機械は手が出ない。
この記事では、そんなあなたの悩みを一気に解決します!結論から言ってしまうと、初心者が趣味で始めるなら、5万円~15万円の価格帯の電動ろくろが最も現実的で、後悔しない選択肢です。この価格帯なら、パワーも静音性も十分で、あなたの「作りたい!」という気持ちにしっかりと応えてくれる頼もしい相棒になってくれます。
この記事を最後まで読めば、なぜその価格帯がベストなのか、価格帯ごとにどんな違いがあるのか、そして購入前に知っておくべき全てのことが分かります。もう価格のことで悩むのはおしまい。さあ、一緒にあなただけの最高の相棒を見つけて、夢の「おうち陶芸ライフ」への第一歩を踏み出しましょう!
電動ろくろの価格相場は5万円から15万円が現実的な狙い目
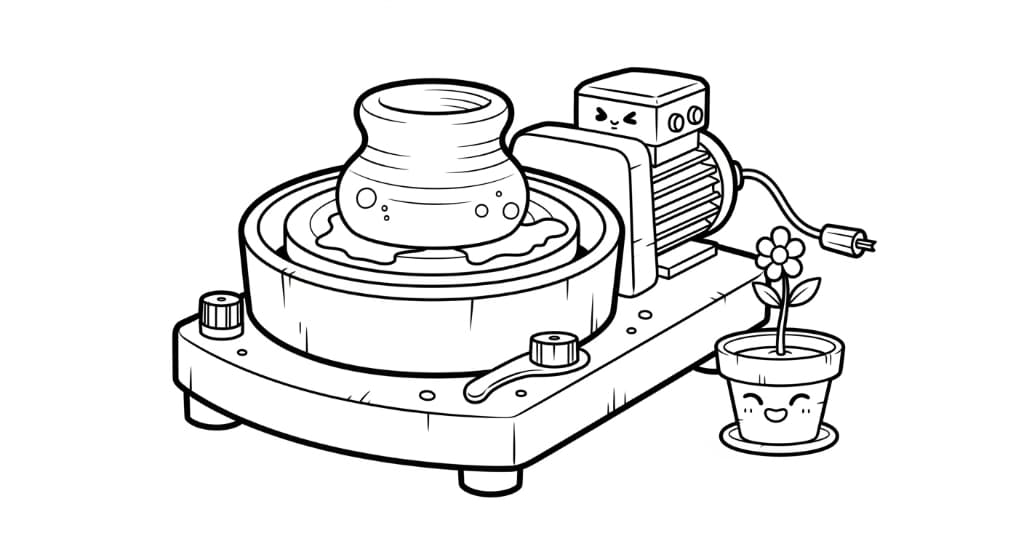
さて、いきなり核心からお話ししますが、もしあなたが本気で趣味として陶芸を始めたいと考えているなら、電動ろくろの予算は5万円から15万円の範囲で見ておくのが大正解です。え、もっと安いのじゃダメなの?逆に高い方がいいんじゃない?色々な声が聞こえてきそうですね。わかります、わかります。私も最初はそうでしたから。でも、これにはちゃーんと理由があるんです。
なぜ5万円から15万円がおすすめなのか
この価格帯がなぜ「黄金のゾーン」なのか。それは、陶芸を長く楽しむための「性能」と「価格」のバランスが最高に良いからです。
まず、陶芸って、実は粘土とのパワー勝負な一面があるんですよ。特に、中心を出す「土殺し」という工程では、粘土がブレないようにグッと力を込める必要があります。このとき、ろくろのモーターパワーが弱いと、粘土の抵抗に負けて回転が不安定になったり、最悪の場合止まってしまったり…。これ、めちゃくちゃストレスなんです!せっかく集中しているのに、道具のせいでうまくいかないなんて、悲しすぎますよね。
5万円以上のモデルになってくると、このモーターパワーが格段に上がります。ご飯茶碗やお皿はもちろん、ちょっと大きめの花瓶や鉢物など、あなたが「これ作ってみたい!」と思うほとんどの作品に対応できるパワーを備えています。安すぎるモデルで「パワーが足りない…」と買い替えることになる「安物買いの銭失い」のリスクを避けられる、というわけです。
それに、静音性も全然違います。家族が寝静まった夜にこっそり作業したい、なんて方も多いはず。この価格帯のモデルは、驚くほど静かなものが多いんです。まさに、趣味に没頭するための環境を整えてくれる、頼れる存在なんですよ。高すぎず、安すぎず。あなたの創作意欲を邪魔せず、しっかりと支えてくれる。だからこそ、この5万円~15万円という価格帯が、最高のスタートラインになるんです。
3万円以下の格安ろくろってどうなの?
「でも、ネットで探すと1万円とか3万円とかで売ってるのもあるけど…」うん、ありますよね。正直に言いましょう。もし、あなたが「一生に一度でいいから、ろくろっていうものを触ってみたい」というくらいの気持ちなら…アリかもしれません。でも、「趣味として続けていきたい」と思っているなら、私はあまりおすすめしません。ごめんなさい、ハッキリ言っちゃいます。
なぜなら、先ほどお話しした「パワー不足」が一番の懸念点だからです。小さな湯呑みくらいなら作れるかもしれませんが、粘土の量を少し増やしただけで、とたんに回転が不安定になります。粘土に振り回されて、全然形にならない…なんてことになりかねません。そうなると、だんだんろくろに向かうのが億劫になって、せっかくの「やりたい!」という気持ちが萎えてしまう可能性が高いんです。
それに、耐久性や音の問題もあります。モーター音がかなり大きかったり、使っているうちにガタが来やすかったり。作りがシンプルな分、泥が機械の内部に入り込んで故障の原因になる、なんて話も聞きます。もちろん、すべての格安品がそうだとは言いません。でも、せっかく夢のマイろくろを手に入れるなら、ストレスなく創作に集中できる相棒を選んでほしい。それが私の偽らざる気持ちなんです。本当にちょっとした小物を作るため、と割り切れるなら…という感じですね。
20万円以上の高級機はプロの世界
じゃあ逆に、高ければ高いほど良いんじゃない?と思いますよね。確かに、20万円、30万円と価格が上がっていくと、ろくろの性能は飛躍的に向上します。モーターのパワーは言うまでもなく、特筆すべきはその「静音性」と「安定感」。まるで高級車のように、滑らかで全くブレない回転を実現してくれます。大きな壺や大皿など、プロの作家さんが作るような巨大な作品にもびくともしないパワーと耐久性を備えています。
これはもう、完全にプロフェッショナルや、陶芸教室を運営する方向けの領域です。毎日何時間も、何十年も使い続けることを想定して作られているので、作りがとにかく頑丈。機能も豊富で、まさに至れり尽くせり。憧れますよね…私もいつかは、なんて夢を見たりします(笑)。
でも、趣味で始める私たちが、最初からこのクラスのろくろを持つ必要があるかというと、正直「オーバースペック」と言えるでしょう。例えるなら、免許取り立てでいきなりF1マシンを買うようなものかもしれません。もちろん、予算に上限がないのであれば最高の選択ですが、まずは5万円~15万円の「黄金ゾーン」で腕を磨き、「もっと大きな作品に挑戦したい!」「このろくろと共に生きていく!」と決意が固まったときに、ステップアップとして検討するのが、最も賢い選択だと思いますよ。
価格帯別に見る電動ろくろの特徴とできること

さて、「5万円~15万円が狙い目」というお話はしましたが、じゃあ具体的にそれぞれの価格帯でどんな違いがあるの?という点が気になりますよね。ここでは、もう少し細かく価格帯を分けて、それぞれのモデルで「できること」と「できないこと」を、私の独断と偏見も交えながら、生々しく解説していきたいと思います!自分の作りたいものと予算を天秤にかけながら、読んでみてくださいね。
~5万円「お試し・小物作り向け」エントリーモデル
この価格帯は、いわゆる「卓上ろくろ」と呼ばれるコンパクトなモデルが中心になります。有名どころだと、シンポの「RK-5T」や、ちょっと変わり種の「どべえ」なんかがこのあたりに入ってきますね。
最大の特徴は、その手軽さ!テーブルの上にポンと置けて、重さも10kg前後のものが多く、女性でもなんとか持ち運べます。「常設するスペースはないけど、やりたい時にサッと出して使いたい」という方には、このコンパクトさは大きな魅力です。価格も手頃なので、「続くかどうかわからないけど、とにかく一度自宅でやってみたい」という方の「最初の一台」としては、有力な候補になるでしょう。
作れるものとしては、湯呑み、ぐい呑み、小さめのご飯茶碗、豆皿といった、いわゆる「小物」がメインになります。粘土量で言うと、だいたい1kgくらいまでが快適に作れる範囲かな、という印象です。
ただ、やっぱりパワーと静音性は上位モデルに一歩譲ります。粘土に少し力を加えると回転が遅くなったり、モーター音が「ウィーン」と響いたりするのは、この価格帯ではある程度覚悟が必要です。大きな皿や丼、花瓶などを作りたい!という野望がある方には、正直、物足りなさを感じるでしょう。あくまで「お試し」や「小物専門」と割り切って選ぶのが吉です。
5万円~15万円「本格的な趣味始めに」一番人気の価格帯
来ました!私が最もおすすめする、まさに「ど真ん中」の価格帯です。このクラスになると、もう「おもちゃ」や「お試し」ではありません。立派な「陶芸の道具」です。代表的なモデルとしては、陶芸をやっている人なら誰もが知っている、シンポの「RK-3D」や「RK-55」あたりがこのゾーンの王者ですね。
この価格帯の魅力は、なんといってもそのバランスの良さ。まず、モーターパワーが十分にあるので、粘土量3~5kgくらいまでなら余裕で扱えます。これだけあれば、ラーメンどんぶりやカレー皿、中くらいの花瓶など、日常で使うほとんどの器を作ることが可能です。「あ、これ作りたいな」と思ったものが、だいたい作れる。この「できることの幅広さ」が、趣味を長く続ける上でめちゃくちゃ重要なんです。
そして、静音性もぐっと向上します。特にダイレクトドライブモーター(ベルトを使わない方式)を搭載したモデルは、本当に静か。「え、回ってるの?」と思うくらいスムーズで、夜中の作業も気兼ねなくできます。私もこのクラスのろくろを使っていますが、集合住宅でも全く問題なく、創作活動に没頭できています。
重さは20kg~40kgくらいと、ちょっと重くなりますが、その分ドッシリとした安定感があり、大きな粘土をこねても本体がブレることがありません。まさに、あなたの創作活動をがっちりと支えてくれる、頼れる相棒。初期投資としては少し勇気がいるかもしれませんが、その価値は十二分にあります。本気で陶芸を楽しむなら、絶対にこの価格帯から選ぶことを強く、つよーく、おすすめします!
15万円~「もう、あなたは作家です」準プロ・プロ仕様モデル
15万円の壁を超えてくると、そこはもう準プロ、そしてプロの世界へと足を踏み入れることになります。シンポで言えば「RK-2X」や「RK-2P」といった、陶芸教室やプロの工房でよく見かける、あの風格あるモデルたちがこのカテゴリーです。
このクラスのろくろは、とにかく全てがケタ違い。モーターパワーは言うまでもなく、粘土を10kg以上乗せても微動だにしない圧倒的なトルクを誇ります。大壺や巨大なオブジェなど、アマチュアではなかなか挑戦しないような大物作りに対応できる設計です。
そして、特筆すべきはその静粛性と振動のなさ。まるで無重力空間で粘土が回っているかのような、究極の滑らかさを実現しています。一度このクラスのろくろを体験すると、もう元には戻れない…なんて言われるほど。また、毎日長時間の使用に耐えうる頑丈な設計になっており、耐久性も抜群です。まさに一生モノ、いや、次の世代にも受け継げるほどのクオリティです。
正直なところ、趣味で始める方が最初からこのクラスを選ぶ必要は全くありません。完全にオーバースペックです。ただ、もしあなたが陶芸にのめり込み、「いつかは個展を開きたい」「作家として活動していきたい」という大きな夢を抱いたなら…その時には、このクラスのろくろが、あなたの夢を叶えるための最強の翼となってくれるはずです。今はまだ、憧れの存在として心に留めておくくらいがちょうど良いかもしれませんね。
後悔しない電動ろくろの選び方5つのポイント

さあ、価格帯ごとの特徴がなんとなく掴めてきたところで、次はもっと具体的に「じゃあ、どの機種を選べばいいの?」という疑問にお答えします。カタログを見ても、専門用語ばっかりでよくわからないですよね。ここでは、私が実際にろくろを選んだ経験や、陶芸仲間の話をもとに、「ここだけは絶対チェックして!」という5つのポイントに絞って、熱く語らせていただきます!
ポイント1 モーターのパワーと静音性で選ぶ
もう何度も言っていますが、これが一番大事!本当に、本当に大事です!モーターのパワーは、作れる作品の大きさに直結します。「大は小を兼ねる」ということわざがありますが、ろくろのパワーに関してはまさにその通り。パワーがあれば、小さなものから大きなものまで、ストレスなく作ることができます。カタログには「積載粘土量〇kg」といった記載があるので、自分がどれくらいの大きさの物を作りたいかを想像しながら、余裕のあるスペックを選びましょう。
そして、もう一つが静音性。これは、あなたの「陶芸ライフの質」を左右します。特に、アパートやマンションなどの集合住宅にお住まいの方、家族と暮らしている方は、絶対に無視できないポイントです。モーターの駆動方式には、主に「ベルト式」と「ダイレクトドライブ式」があります。簡単に言うと、ベルト式は少し音が大きめな傾向があり、ダイレクトドライブ式は非常に静かです。予算が許すなら、断然ダイレクトドライブ式がおすすめ。深夜、一人静かに土と向き合う…そんな最高の時間を手に入れるためにも、静音性にはぜひこだわってください。「うるさくて家族に白い目で見られる…」なんて悲劇は、絶対に避けたいじゃないですか!
ポイント2 ドベ受け(泥じぶきを受ける皿)の形状と手入れのしやすさ
地味!地味だけど、これ、めちゃくちゃ重要です!断言します!ドベ受けとは、ろくろを回している時に飛び散る泥水(ドベ)を受けるお皿のこと。陶芸って、想像以上に泥だらけになるんです。そして、作業が終わるたびに、このドベ受けを掃除する必要があります。
このドベ受けには、大きく分けて「一体型」と「分割型」があります。一体型はろくろ本体とくっついているタイプで、分割型は2つ以上にパカっと外れるタイプ。私のおすすめは、断然「分割型」です!なぜなら、掃除が圧倒的に楽だから。分割できれば、シンクに持っていってザブザブ丸洗いできます。でも一体型だと、本体ごと運ぶわけにもいかないので、雑巾やスポンジでちまちまと拭き掃除するしかありません。これが、結構な手間なんです…。
「掃除が面倒くさい」という気持ちは、確実に創作意欲を削いでいきます。「あー、またあの掃除が待ってるのか…」と思うと、ろくろに向かうのが億劫になってしまう。そんな本末転倒なこと、避けたいですよね?ろくろ選びの際は、ぜひこのドベ受けが簡単に取り外せるかどうかを、血眼になってチェックしてください。あなたの陶芸ライフが快適になるかどうかの、大きな分かれ道ですよ!
ポイント3 回転方向の切り替えは必要?
電動ろくろには、回転方向を切り替える機能がついているモデルがあります。一般的に、右利きの人はろくろを「反時計回り」で使い、左利きの人は「時計回り」で使います。なので、もしあなたが左利きなら、時計回りに回転する機能は必須です。
「じゃあ、右利きなら反時計回りだけでいいんじゃない?」と思いますよね。はい、基本的にはその通りです。ほとんどの右利きの人は、反時計回りでしか使いません。私も右利きですが、時計回りで使ったことは一度もありません(笑)。
ただ、中には「削り(高台などを削り出す作業)の時だけ逆回転にしたい」という方や、「両利きだから両方使いたい」という方もいらっしゃいます。また、将来的に誰かに教える機会があるかもしれない、なんて可能性もゼロではありません。ほとんどのモデルには切り替え機能がついているので、あまり神経質になる必要はありませんが、念のため「ちゃんと切り替えられるかな?」と確認しておくと安心です。まあ、ちょっとした脱線話ですが、たまに逆回転で挑戦してみようかな、という衝動に駆られることは…あります。やったことないですけどね!
ポイント4 大きさと重さ 設置場所と収納を考える
これも、意外と見落としがちなポイントです。夢のマイろくろに舞い上がって、ポチっと購入!届いてみたら、「デカっ!重っ!どこに置くの!?」なんてことになったら目も当てられません。
まずは、ろくろをどこに置くのか、具体的にシミュレーションしてみましょう。常設できる専用のスペースがあるのか、それとも使うたびに押し入れやクローゼットから出し入れするのか。それによって、選ぶべきモデルが全く変わってきます。
常設できるなら、多少重くてもドッシリと安定感のある据え置き型がおすすめです。重さがある方が、作陶中にブレなくて快適ですからね。逆に出し入れするなら、20kg以下、できれば10kg台の卓上モデルが現実的でしょう。40kgもあるろくろを毎回運ぶなんて、考えただけで腰が砕けそうです…。
カタログに記載されている「本体寸法(幅×奥行×高さ)」と「重量」をしっかりと確認し、メジャー片手に設置場所の採寸を忘れずに行いましょう。この一手間が、購入後の「こんなはずじゃなかった…」を防いでくれます。あなたの生活スタイルに合った、無理のない一台を選びましょうね。
ポイント5 中古という選択肢 あり?なし?
「少しでも安く手に入れたい…」そう考えたとき、「中古」という選択肢が頭をよぎりますよね。うん、わかります。ヤフオクやメルカリ、ジモティーなんかを覗くと、確かに新品よりずっと安い価格で出品されていることがあります。
結論から言うと、中古は「ハイリスク・ハイリターンな選択肢」です。メリットは、もちろん価格。運が良ければ、上位モデルを格安で手に入れられるかもしれません。しかし、デメリットも大きい。一番怖いのは「故障のリスク」です。モーターやベルト、ベアリングといった心臓部は、使えば使うほど消耗します。前の所有者がどれくらい使っていたのか、どんな使い方をしていたのかは、見ただけでは分かりません。保証も当然ありませんから、買ってすぐに壊れても自己責任。修理代の方が高くついてしまった…なんてこともあり得ます。
もし中古を選ぶなら、陶芸用品を専門に扱っているお店の「整備済み中古品」を選ぶのが賢明です。プロの目でチェックされ、必要な部品交換やメンテナンスが施されているので、フリマアプリで個人から買うよりずっと安心です。それでも、中古は中古。ある程度のギャンブル要素は覚悟の上で、慎重に検討することをおすすめします。私個人としては、長く使う相棒だからこそ、安心して使える新品を選ぶのが一番かな、と思っています。
電動ろくろ購入前に知っておきたい!ろくろ以外の必要経費

「よーし、ろくろの予算は決まった!これで陶芸ライフの始まりだ!」と、気持ちが高ぶっているあなたに、少しだけ現実的なお話をさせてください。ごめんなさいね、水を差すようで。でも、これを知っておかないと、後で「え、こんなにお金がかかるの!?」とビックリしてしまうかもしれません。そう、電動ろくろは、買ったら終わりじゃないんです。むしろ、そこからがスタート。ろくろ以外にも、色々と必要なものがあるんですよ。
土、釉薬、道具…意外とかかる初期費用
まず、当たり前ですが「粘土(土)」がなければ何も始まりません。粘土は種類も豊富で、10kgで1,000円~3,000円くらいが相場です。最初は扱いやすい「信楽の並土」あたりから始めるのがおすすめですよ。
次に、形を整えたり、削ったりするための「道具」たち。最低限そろえたいのは、以下のスタメンたちです。
・カンナ:高台などを削るための道具。数種類あると便利。
・シッピ:ろくろから作品を切り離すための糸。
・コテ:表面を滑らかにしたり、形を整えたりするヘラ。
・なめし皮:口当たりなどを滑らかにするための皮。
・針:粘土の厚みを測ったり、線を引いたりする。
・スポンジ:水をつけたり、表面を整えたり。
これらを一つずつ揃えていくと、なんだかんだで5,000円~10,000円くらいはかかります。最初は、必要な道具が一通り入った「初心者セット」みたいなものを買うのが手っ取り早くて楽ちんですね。
そして、作品に色をつける「釉薬(ゆうやく)」。これもまた、沼なんですよ…!色が無限にあって、見てるだけでワクワクします。1kgで2,000円~5,000円くらいするものもあり、あれもこれもと欲しくなってしまいます。最初は基本的な「透明釉」や「白萩釉」あたりから始めると良いでしょう。こうやって計算していくと、ろくろ本体とは別に、初期費用として2万円~3万円くらいは見ておくと安心です。
最大の壁「焼成」はどうする?窯問題
そして、これが一番の、最大の、ラスボス級の壁です。そう、「焼成(しょうせい)」、つまり作品を焼くための「窯」をどうするか問題。
「え、窯も買うの?」と思ったあなた。ご安心ください。自宅に窯を持つのは、土地や予算、消防法の問題など、ハードルがめちゃくちゃ高いので、ほとんどの人は持っていません。私も持っていません。
じゃあ、どうするのか。主な解決策は2つです。
1つ目は「貸し窯(レンタル窯)」サービスを利用すること。陶芸用品店や専門の工房が、時間や窯のスペースを貸し出してくれます。料金は窯の大きさや焼成温度によりますが、1回(素焼きと本焼きで2回)で1万円~3万円くらいが相場です。作品がたくさん溜まってから、まとめて焼くのが効率的ですね。
2つ目は、近所の「陶芸教室」に相談してみること。教室によっては、生徒さん以外でも作品の焼成だけを受け付けてくれる場合があります。「焼成代行」なんて呼ばれたりしますね。料金は作品のサイズ(縦×横×高さ)で決まることが多く、湯呑み1個で500円~1,000円くらい。作った分だけ払う形なので、少量からお願いできるのがメリットです。
どちらにせよ、ろくろを買う前に「焼いてくれる場所」の目星をつけておくことが、めちゃくちゃ重要です。せっかく作った作品が、焼けないまま棚の肥やしになる…なんて、悲しすぎますからね!まずは「〇〇市 貸し窯」とか「〇〇駅 陶芸 焼成」とかで検索して、あなたの「焼き場」を確保しておきましょう!
まとめ 最高の相棒を見つけて、あなただけの陶芸ライフを始めよう!

いやはや、なんだかんだと熱く語ってしまいました。ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。電動ろくろの価格相場から、選び方のポイント、そして購入後の「現実」まで、かなり具体的にお話ししてきました。
もう一度、大切なことをおさらいしましょう。初心者が趣味で電動ろくろを買うなら、狙うべき価格帯は「5万円~15万円」。この「黄金ゾーン」のろくろを選べば、パワー、静音性、耐久性のバランスが良く、あなたの「作りたい!」という気持ちに長く応えてくれる、最高の相棒になってくれるはずです。安すぎるモデルでストレスを溜めたり、高すぎるモデルを持て余したりすることなく、快適な陶芸ライフをスタートできます。
そして、ろくろを選ぶときは、「モーター性能」「ドベ受けの掃除のしやすさ」「大きさと重さ」といったポイントをしっかりチェックすること。さらに、購入前に「粘土や道具の初期費用」と、最大の難関である「焼成してくれる場所」を確保しておくことを、絶対に忘れないでくださいね。
電動ろくろは、決して安い買い物ではありません。だからこそ、じっくり悩んで、納得のいく一台を選んでほしい。それは単なる「機械」ではなく、あなたの創造性を形にし、日々の生活に彩りと癒やしを与えてくれる、かけがえのない「パートナー」になるのですから。
もし、まだ購入に踏み切れない、不安だ…という方は、まずは近所の陶芸教室で一度、電動ろくろに触れてみるのも素晴らしい一歩です。そこで土の感触や、ろくろの楽しさを肌で感じてみてください。きっと、その魅力の虜になるはずです。
さあ、準備は整いましたか?
ひんやりとした土に触れ、無心でろくろを回す、あの至福の時間をあなたの日常に。最高の相棒を見つけて、今日からあなただけの物語を紡いでいきましょう。