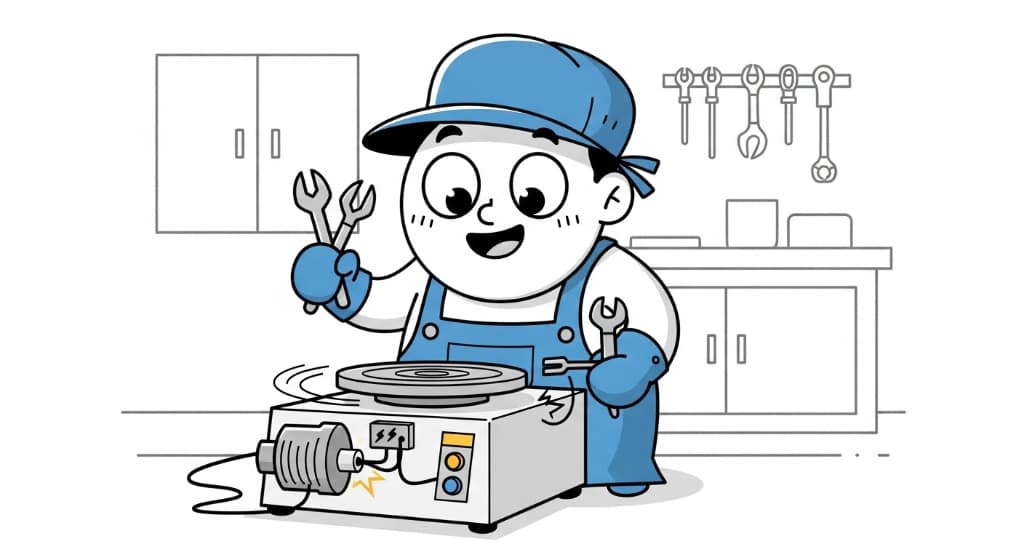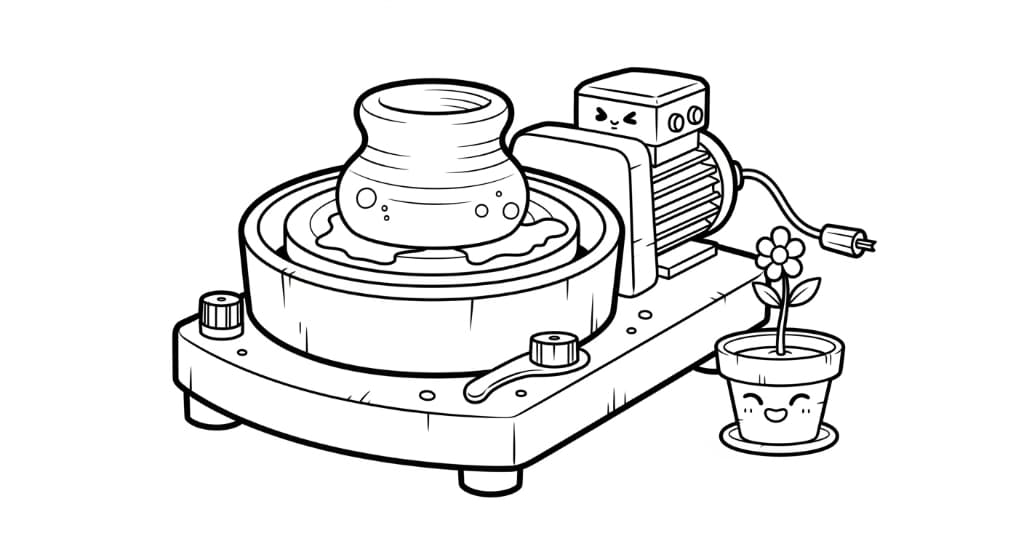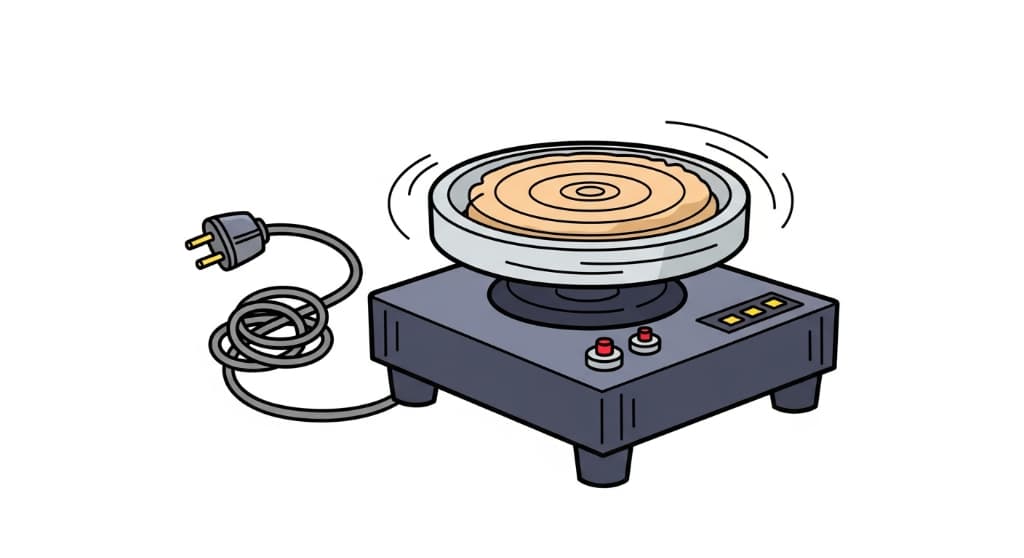【絶望】電動ろくろが動かない!初心者がパニックになる前に読むべき原因と対処法

さあ、今日は待ちに待った陶芸の日!エプロンをきゅっと締めて、粘土も準備万端。あとはこの電動ろくろのスイッチを入れれば、夢のうつわ作りが始まる…はずだったのに。
「……え?なんで?」
スイッチ、オン。フットペダル、踏む。…シーン。
もう一度、スイッチを確認。ペダルをぐっと踏み込む。…うんともすんとも言わない。
血の気が引くって、まさにこのことですよね。頭の中は「故障?」「壊した?」「買ったばっかりなのに!?」と大パニック。楽しいはずの趣味の時間が、一瞬で冷や汗だらだらの時間に早変わり。わかります、私もまったく同じ経験をしたことがあるんですから。
でも、ちょっと待ってください!その電動ろくろ、本当に故障していると決まったわけではありません。実は、電動ろくろが動かない原因って、びっくりするほど単純な「うっかりミス」だったりすることが本当に多いんです。
この記事では、かつて私が絶望の淵で試した「電動ろくろが動かない時に確認すべきこと」を、私の赤裸々な失敗談とともにお届けします。これを読めば、無駄なパニックから解放され、落ち着いて原因を探れるようになります。そして、うまくいけば数分後には、元気に回りだすろくろを前に、笑顔を取り戻しているはずですよ。さあ、一緒に確認していきましょう!
電動ろくろが動かない!焦る前にまず確認したいこと

電動ろくろがウンともスンとも言わない時、私たちの頭に真っ先に浮かぶのは「故障」の二文字。もう最悪。修理に出さなきゃ…いくらかかるんだろう…なんて、ネガティブな想像がぐるぐる駆け巡りますよね。でも、その思考、一旦ストップ!です。
実は、ろくろが動かない原因のほとんどは、機械の専門知識がなくても解決できる、ごくごく基本的な見落としだったりします。プロに連絡する前に、自分でできることはたくさんあるんです。ここで慌てて「壊れた!」と決めつけてしまうのは、あまりにもったいない。まずは落ち着いて、身の回りのことからチェックしていくのが、解決への一番の近道なんですよ。
まずは深呼吸!故障と決めつけないで
「動かない!」と認識した瞬間、心臓がドクン!と跳ね上がりますよね。わかります。めちゃくちゃわかります。特に、やっと手に入れた自分だけの電動ろくろだったりしたら、そのショックは計り知れません。「私の扱いが悪かったのかな…」なんて、自分を責めてしまったり。
でも、そんな時こそ、一度ろくろから離れて、ふかーく深呼吸してみてください。一杯お茶でも飲んで、気持ちをリセットするんです。パニック状態では、正常な判断なんてできませんから。見えるはずのものも見えなくなってしまいます。
「故障だ」という思い込みは、視野をぐっと狭くしてしまいます。そうすると、本当に単純な原因を見過ごしてしまうんです。だから、まずは「これは故障じゃないかもしれない。何か簡単な見落としがあるだけかも」と、自分に言い聞かせてみてください。その心の余裕が、解決への第一歩になります。大丈夫、きっと何とかなりますから。
本当に基本的な5つのチェックポイント
心が少し落ち着いたら、さっそく基本的なチェックを始めましょう。これから挙げる5つのポイントは、「そんなこと?」と思うような当たり前のことばかりです。でも、人間って焦っていると、本当にこういう当たり前のことを見落とす生き物なんですよ。ええ、私がそうでしたから…。
電源プラグ、ちゃんと刺さってますか?
壁のコンセントに、ろくろのプラグはしっかり奥まで刺さっていますか?「刺さってるよ!」と思うかもしれませんが、もう一度、ぐっと押し込んでみてください。掃除の時にちょっとズレて、接触不良になっていること、意外とあります。延長コードを使っている場合は、そっちのスイッチがオフになっているなんてオチも。
本体の電源スイッチは「オン」になってますか?
これも基本中の基本。でも、昨日の片付けの時にオフにして、そのまま忘れていたりしませんか?機種によっては、主電源と回転スイッチが別になっていることもあります。全部のスイッチをもう一度確認です。
家のブレーカーは落ちていませんか?
ろくろは意外と電気を使います。電子レンジやドライヤーなど、他の家電と一緒に使ったタイミングで、ブレーカーが落ちてしまうことも。部屋の電気がついているか、他のコンセントは使えるか、確認してみましょう。
フットペダルはしっかり接続されていますか?
フットペダルは、ろくろ本体にケーブルで接続されていますよね。そのコネクタ部分、カチッと音がするまで差し込まれていますか?足元にあるものだから、うっかり蹴飛ばしてしまって、接続が甘くなっていることも考えられます。
緊急停止ボタン、押されていませんか?
多くの電動ろくろには、安全のための大きな赤い「緊急停止ボタン」がついています。これを一度押すと、他のどんなスイッチを操作しても動かなくなります。何かの拍子に、服や体が当たって押し込まれていませんか?もし押されていたら、ボタンを回したり引いたりして解除してみてください。(解除方法は機種によります)
どうでしょう?この5つのうち、どれか当てはまるものはありましたか?もし、これだけで解決したら、ラッキー!さあ、気を取り直して作陶を再開しましょう!…え?まだ動かない?大丈夫、次のステップに進みましょう。
意外と見落としがち?電源コードとフットペダルの罠

基本的なチェックをしてもダメだった…となると、少しだけ不安がぶり返してきますよね。でも、まだ諦めるのは早いです。もう少しだけ、詳しく見ていきましょう。特に、電気を供給する「電源コード」と、回転を指示する「フットペダル」周りは、トラブルが隠れていることが多いんです。
足元にあったり、壁際を這っていたりして、普段あまり意識しない部分だからこそ、見落としがちなポイントが潜んでいます。「ちゃんと刺さってるし、問題ないはず…」と思っていても、もう一度、愛情を込めて(?)じっくり観察してみてください。
そのプラグ、本当に奥まで刺さってますか?
さっきの基本チェックでも触れましたが、電源プラグの問題は本当に根深いです。ええ、これは私の大失敗談なんですけど…。ある日、いつものようにろくろの前に座って、スイッチを入れたのに動かなかったんです。コンセントは刺さってる。スイッチもオン。ブレーカーも落ちてない。なんで!?って。
30分くらい、ああでもないこうでもないって唸りながら、ろくろ本体を眺めたり、叩いてみたり(ダメ、絶対)。もう半泣き状態で、ダメ元でコンセントを一度抜いて、もう一度「えいっ!」って力強く差し込んでみたんです。そしたら…ウィーンって。…え?
そう、犯人は「半差し」状態のプラグでした。見た目には刺さっているように見えても、中の金具がちゃんと接触していなかったんですね。たったそれだけのことに、私は30分も無駄にしたんです。もう、恥ずかしいやら情けないやら…。でも、それ以来、プラグは「これでもか!」ってくらい押し込むようになりました。あなたも、騙されたと思って、プラグを一度抜き差ししてみてください。違うコンセントに差してみるのも、有効な手段ですよ。
フットペダルが「家出」している問題
電動ろくろの心臓部がモーターなら、司令塔はフットペダルです。この司令塔からの指示が届かなければ、ろくろは当然動きません。ペダルが「家出」しちゃってる、なんて冗談みたいな状況ですが、接続不良は意外とよくある話なんです。
まずは、本体との接続部分。コネクタをもう一度、ぐりぐりと押し込んでみてください。ちゃんと刺さっているつもりでも、ほんの少し浮いているだけで接触不良になります。
次にチェックしたいのが、ケーブルそのものです。ペダルって足元にあるから、ついつい無頓着に扱ってしまいがち。知らず知らずのうちに椅子のキャスターで踏んづけていたり、ケーブルを無理に引っ張ってしまったり…。そうすると、ケーブルの根元や途中で「断線」しかかっていることがあります。見た目にはわからなくても、中で細い銅線が切れかかっているんですね。ケーブルを優しく揺すってみたり、角度を変えてみたりしながらペダルを踏んでみて、一瞬でも動く気配があれば、断線の可能性が高いです。そうなるとケーブル交換が必要ですが、原因が特定できただけでも大きな一歩ですよね。
モーターは唸るのに回らない…機械的なトラブルかも

今までのチェックは、主に「電気系統」の話でした。では、「スイッチを入れるとモーターの『ウィーン』という音はする。でも、肝心の円盤(ターンテーブル)が回らない」という場合はどうでしょう?これは、電気がモーターまでは来ている証拠。問題は、そのモーターの力をターンテーブルに伝える「動力伝達部分」にある可能性が高いです。
ちょっとだけ機械的な話になりますが、構造は意外とシンプル。カバーを外して中を覗いてみる勇気があれば、原因が見つかるかもしれません。ただし、必ず電源プラグを抜いてから作業してくださいね!感電したら大変ですから。
ベルトの緩みや外れを疑ってみよう
多くの家庭用電動ろくろは、モーターの回転を「ベルト」を使ってターンテーブルに伝えています。自転車のチェーンみたいな役割ですね。このベルトが、長年使っているうちに伸びて緩んでしまったり、何かの拍子にプーリー(滑車)から外れてしまったりすることがあるんです。
モーターは空回りしているから音はするけど、力が伝わらないからターンテーブルは回らない。まさにこの症状にぴったりです。
ろくろの底や側面にあるカバーを、ドライバーで開けてみてください。(※機種によって構造は違うので、必ず取扱説明書を確認してくださいね!)中を覗いてみて、ゴム製のベルトがだるんだるんに緩んでいたり、完全に外れていたりしたら、それが原因です。
外れているだけなら、正しい位置にかけ直せばOK。もし緩んでいるようなら、ベルトの張りを調整するネジがある機種もあります。ただ、ベルト自体が劣化して伸び切っている場合は、新しいベルトに交換が必要です。メーカーのサイトや購入したお店で、交換用パーツとして手に入る場合が多いですよ。私も一度、ベルトが外れてて「うわ、本格的に壊れた!」って焦ったことがありますが、かけ直しただけで復活して、すごく嬉しかったのを覚えています。ついでに中のホコリを掃除してあげると、なんだかろくろへの愛着も深まります。
粘土のカスが邪魔してる?悲しき詰まり事件
作陶していると、どうしても粘土のドベ(泥水)や削りカスが飛び散りますよね。特に、ターンテーブルの軸の周りや、受け皿との隙間に、そうした粘土が溜まりやすいんです。普段は少しずつだから気にならなくても、積もり積もってカチカチに固まってしまうと、これがとんでもない抵抗になります。
結果、モーターは回ろうとしているのに、物理的に邪魔されてターンテーブルが動けない、という「詰まり事件」が発生するわけです。これも「モーター音はするけど回らない」原因の一つ。
ターンテーブルを手で回そうとしてみてください。もし、ものすごく重かったり、ゴリゴリとした感触があったり、全く動かなかったりしたら、粘土が詰まっている可能性大です。
解決策は、もう、ひたすら掃除です!竹串や古い歯ブラシ、濡らした布などを使って、隙間に詰まった粘土を根気よく掻き出しましょう。これがまた、けっこう大変な作業で…。でも、きれいに掃除し終わって、スムーズに回るようになったターンテーブルを見ると、達成感がすごいですよ。「ごめんよ、汚してて…」なんて、ろくろに話しかけちゃったりして。日頃からこまめに掃除してあげることの大切さを、身をもって知ることになります。本当に。
「あれ、こんなボタンあった?」安全装置と設定ミス
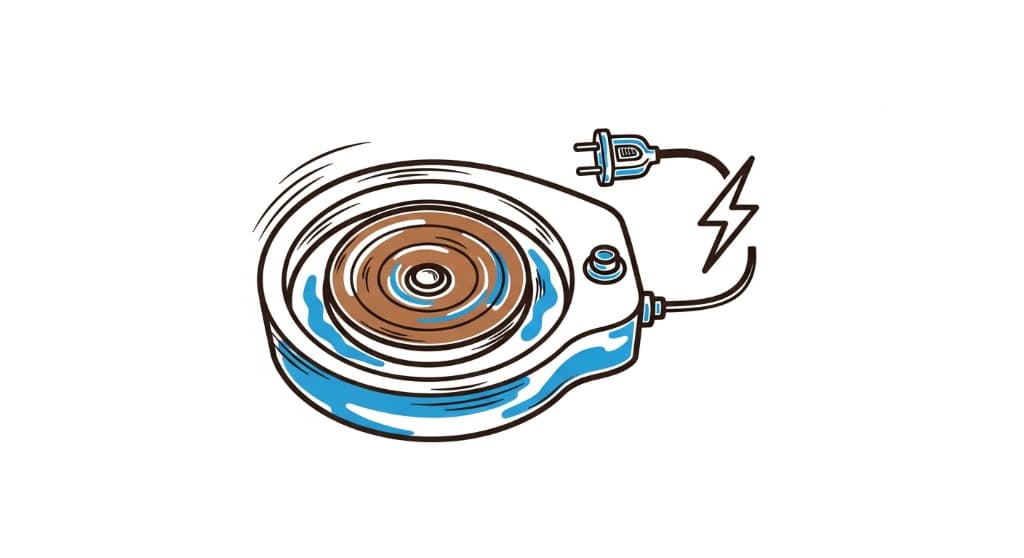
電源OK、接続OK、機械的な詰まりもなさそう。うーん、いよいよ万策尽きたか…?いやいや、まだです!まだ見落としているポイントがあるかもしれません。それは、普段あまり触ることのない「安全装置」や「設定スイッチ」の存在です。
特に、電動ろくろを使い始めたばかりの頃は、全ての機能を把握しているわけではありませんよね。「こんなところに、こんなスイッチがあったなんて!」という発見が、案外、解決の糸口になったりするものです。灯台下暗し、とはよく言ったものです。
緊急停止ボタン、押してませんか?
基本チェックの項目でも触れましたが、この「緊急停止ボタン」は本当に厄介な存在です(もちろん安全のためには不可欠なんですが!)。大きくて目立つ赤いボタン。キノコみたいな形をしていることが多いですね。
これを押すと、回路が強制的に遮断されて、ろくろは完全に沈黙します。で、ですよ。問題は、このボタンを押したことを忘れがちなこと。あるいは、押した自覚すらないことなんです。
作業に夢中になって、前のめりになった拍子にお腹で「ポチッ」。袖が引っかかって「ポチッ」。片付けの時にうっかり「ポチッ」。焦っている時ほど、この目立つはずの赤いボタンが視界から消えるんですよね。不思議なことに。
もう一度、本体をよーく見てください。赤い、押せるボタン、ありませんか?もし押し込まれていたら、それが原因です。解除方法は、ボタン自体を右か左にカチッと回すタイプや、そのまま手前に引っ張るタイプなど、機種によって様々です。説明書を確認するか、色々試してみてください。カチッと音がしてボタンが元の位置に戻れば、解除成功。これで動いたら、思わず「お前かーい!」ってツッコミを入れたくなりますよ。
回転方向の切り替えスイッチは正しい位置?
電動ろくろには、ターンテーブルの回転方向を切り替えるスイッチがついているものがほとんどです。右利きの人は反時計回り、左利きの人は時計回りに回すのが一般的だからですね。
このスイッチ、通常は「右回転」「左回転」のどちらかに入れるわけですが、機種によっては、その中間に「中立(オフ)」の位置があるんです。スイッチが、どっちつかずの真ん中の位置で止まっていませんか?
この「中立」は、文字通り電源をオフにするポジション。ここにスイッチがあると、いくら主電源を入れてフットペダルを踏んでも、モーターには「回るな」という指令が行っている状態なので、当然動きません。
これもね、片付けの時とかに無意識に触ってしまって、中途半端な位置で止まっていることがあるんですよ。「右!」「左!」とカチッカチッと切り替えて、正しい位置に入っているか確認してみてください。こんな単純なことで悩んでいたのか…と、拍子抜けするかもしれません。でも、それで動けば万々歳ですよね!
色々試したけどダメ…いよいよ故障を覚悟する時

ここまで、考えられる限りのセルフチェックを試してきました。それでも、あなたの愛機は沈黙を続けている…。うーん、こうなると、いよいよ自力での解決は難しいかもしれません。私たちの手に負えない、内部の電子回路やモーター本体の故障である可能性が高まってきます。
すごく残念だし、がっかりしますよね。でも、ここまで頑張ってチェックした自分を褒めてあげてください。やれるだけのことはやったんですから。ここからは、潔くプロの力を借りるフェーズです。落ち込むのはここまでにして、次のアクションに移りましょう。
メーカーや販売店に相談する勇気
さあ、専門家に助けを求めましょう。連絡先は主に2つ。ろくろの「メーカー」か、それを購入した「販売店(陶芸用品店など)」です。
まずは、保証書や取扱説明書を引っ張り出してきてください。そこに、お客様相談窓口などの連絡先が書かれているはずです。保証期間内であれば、無償で修理してもらえる可能性もありますから、保証書は絶対に確認しましょう。
電話するのって、ちょっと緊張しますよね。「うまく症状を説明できるかな…」とか、「怒られたりしないかな…」とか。でも、大丈夫。向こうはプロです。毎日、色々な相談を受けていますから、こちらのつたない説明でも、きっと的確に状況を理解してくれます。
電話する前に、この記事でチェックしたことをメモしておくとスムーズです。「電源は入りますか?」「モーター音はしますか?」といった質問をされる可能性が高いので、「〇〇は試したけどダメでした」と具体的に伝えられると、話が早く進みますよ。勇気を出して、電話をかけてみましょう。それが一番の近道です。
修理ってどのくらいかかるの?気になる費用と期間
プロに相談して、いよいよ「修理」となった時に気になるのが、お金と時間ですよね。こればっかりは、故障の症状や機種によって全く違うので、「いくらです!」とは言えないのが正直なところです。ごめんなさい。
ただ、一般的な流れとしては、まずろくろをメーカーなどに送って、見積もりを出してもらうことになります。その見積金額を見て、修理を進めるか、それとも…新しいものを買うか、を判断することになります。基盤の交換などになると、数万円かかることもあり、「え、新品が買えちゃうじゃん…」なんて悲しい現実に直面することもあるかもしれません。
修理期間も、部品の在庫状況などによりますが、数週間から1ヶ月以上かかることも覚悟しておいた方がいいでしょう。その間、作陶ができないのは本当につらい。つらいですよね…。
でも、まずは見積もりを取らないことには始まりません。もしかしたら、簡単な部品交換だけで、数千円で済むかもしれない。希望は捨てずに、まずはプロの診断を仰ぎましょう。そして、このろくろを待っている時間も、次の作品の構想を練る良い機会だと、ポジティブに捉えてみませんか?
まとめ 電動ろくろが動かなくても、あなたの陶芸ライフは終わらない!

電動ろくろが動かない。このトラブルは、陶芸を楽しむ多くの人が一度は経験する「あるある」です。だから、決してあなた一人が不幸なわけでも、機械に嫌われているわけでもありません。どうか、自分を責めないでくださいね。
今回ご紹介したように、原因はコンセントの半差しや、うっかり押してしまった緊急停止ボタンなど、本当に些細な見落としであることがほとんどです。「故障だ!」とパニックになる前に、まずはこの記事を片手に、一つひとつチェックしてみてください。きっと、その多くは自力で解決できるはずです。
もし、それでもダメだったとしても、落ち込む必要はありません。メーカーや販売店という頼れるプロがいます。トラブルを乗り越えることも、また一つの経験。自分でカバーを開けてみたり、掃除をしてみたりすることで、自分の道具への理解が深まり、より一層の愛着が湧いてくるものですよ。私も、あの動かなかった日のことを、今では笑い話として語れるようになりました。
トラブルは、あなたの陶芸ライフを終わらせるものではなく、もっと深く楽しむためのスパイスみたいなもの。さあ、無事に動き出したろくろで、あるいは、修理から帰ってくる愛機を待ちながら、最高のうつわ作りを続けましょう!あなたの創作活動が、これからも素晴らしいものであり続けることを、心から願っています。