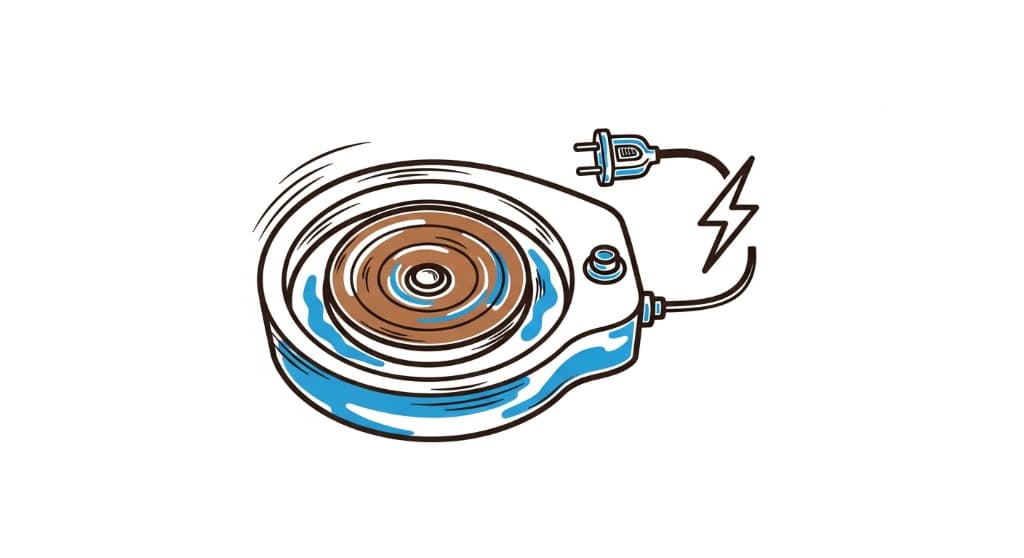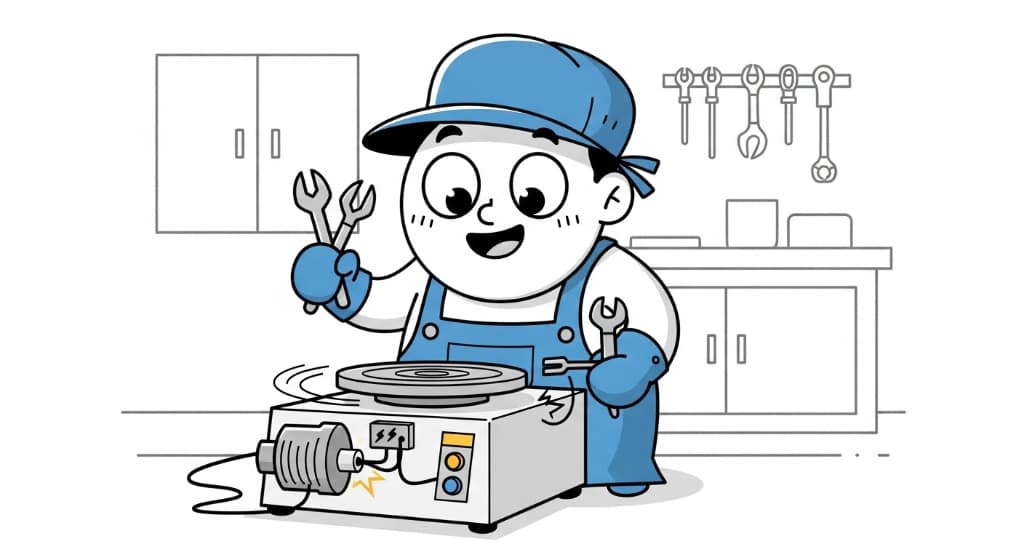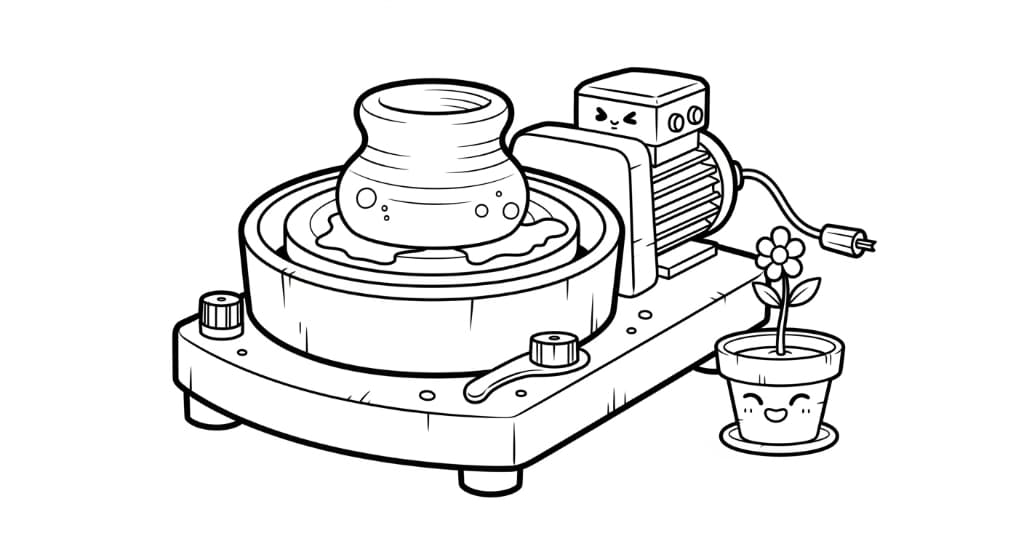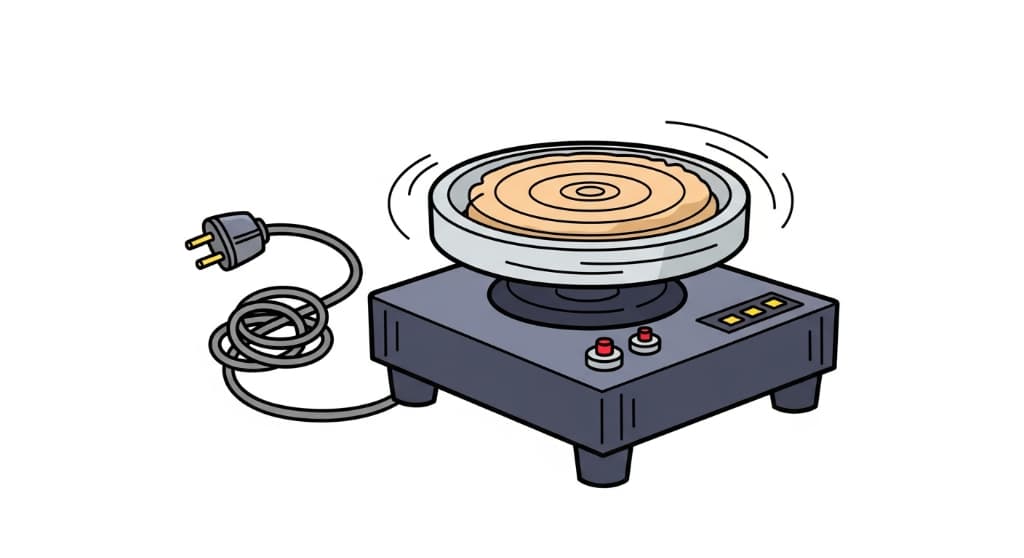電動ろくろで心が折れたあなたへ。実はコツは「力」じゃなくて「角度」だった話

「さあ、やるぞ!」と意気込んで電動ろくろの前に座ったものの、スイッチを入れた途端に土がぐにゃり。あらぬ方向へ暴れ出し、気づけば遠心力で粘土が壁まで飛んでいく…。え、嘘でしょ、なんで?映画みたいに、シュッと綺麗なうつわができるんじゃないの?
わかります、わかります。その気持ち、痛いほど。私も最初はそうでした。隣のベテランさんが涼しい顔で湯呑みを10個も20個も作っている横で、私はただただ泥だらけの物体を量産する日々。正直、才能ないのかなって、何度も心が折れかけました。
でもね、もしあなたが今、同じように悩んでいるなら、ぜひこの記事を読んでみてください。電動ろくろは、決して腕力や才能だけでどうにかなるものじゃありません。実は、ほんの少しの「コツ」を知っているかどうかが、すべてなんです。
結論から言ってしまうと、そのコツとは「土の中心を正確に捉えること」と「正しい姿勢と角度を保つこと」。これだけです。力任せに土を押さえつけるのではなく、土が「どうして欲しいか」を聞いてあげるような感覚。この記事を読み終える頃には、きっとあなたも「ぐにゃり」の呪いから解放され、土と対話しながら思い通りの形を生み出す楽しさに目覚めているはず。泥だらけになるのも、なんだか愛おしく思えてきますよ。さあ、一緒にろくろの沼へ、もっと深くハマってみませんか?
電動ろくろは「力」じゃなく「土殺し」と「中心出し」が9割

多くの初心者が勘違いしてしまう最初のポイント、それは「暴れる土を力でねじ伏せよう」としてしまうことです。気持ちはわかる!だって、言うこと聞いてくれないんだもん。でも、これが最大の落とし穴。電動ろくろの成功は、力ではなく、最初の準備段階である「土殺し(つちごろし)」と「中心出し」が、誇張抜きで9割を占めているんです。ここさえクリアできれば、あとの成形は嘘みたいにスムーズに進みます。
なぜ「力」で押さえつけようとすると失敗するのか
まず、この話からさせてください。ろくろって、高速で回転してますよね。その回転する物体に、均等じゃない力が加わったらどうなるでしょう?そう、ブレるんです。めちゃくちゃブレる。洗濯機の中身が偏ってガッタンガッタン揺れるのと同じ原理です。
初心者の頃の私は、このブレを腕力で「えいやっ!」と押さえつけようとしていました。右手で押したら左が膨らむ、左で押したら今度は右が…みたいないたちごっこ。しまいには粘土が根元からちぎれて、情けない姿でろくろ板の上に取り残される始末。ああ、悲しい。
力で押さえつけるということは、土に対して不均一な圧力をかけている証拠。土は「そっちから押されるなら、こっちに逃げまーす」と素直に反応しているだけなんです。だから、力で戦うのは絶対にNG。私たちがやるべきなのは、土が回転の中心と一体化し、気持ちよく回ってくれる「お膳立て」をしてあげることなんですね。
すべての基本「土殺し」って一体なんだ?
「土殺し」…なんだか物騒な名前ですよね。私も最初は「え?土を殺すの?」ってビビりました。でもこれは、粘土の粒子を整え、硬さを均一にするための、とっても大事な準備運動なんです。
買ってきたばかりの粘土や、一度練った粘土でも、中にはまだ空気の粒(気泡)が残っていたり、水分量が均一でなかったりします。このままろくろに乗せると、気泡が原因で後からひび割れたり、硬い部分と柔らかい部分があるせいで綺麗に伸びなかったりするんですね。
土殺しは、ろくろの上で粘土を円錐状に上げたり、平らに下げたりを繰り返す作業です。上に「ぐぐぐーっ」と伸ばしていく時に、粘土の中の粒子が螺旋状に整列していくイメージ。そして、下に「むぎゅーっ」と押しつぶす時に、その粒子がさらに密になっていく。これを3〜5回ほど繰り返すことで、粘土は驚くほど素直で、扱いやすい「良い土」に変身してくれるんです。この作業を面倒くさがらずに、丁寧に行うこと。これが、美しい作品への第一歩。まさに、急がば回れ、ですね。
運命の分かれ道「中心出し」を制する者はろくろを制す
土殺しが終わったら、いよいよ運命の「中心出し」です。これは、回転するろくろの「ど真ん中」に、粘土の塊の中心をぴったり合わせる作業。これができていないと、何をどうやっても形は歪みます。断言します。絶対に歪みます。
やり方は、まず両手で粘土を包み込むように持ちます。そして、脇をきゅっと締めて、肘を太ももや作業台に固定する!これがめちゃくちゃ大事。自分の体を一本のブレない軸にするんです。手先だけでどうにかしようとすると、ろくろの回転に負けて手がブレてしまいます。体全体で、ろくろの回転を受け止めるイメージです。
そして、ゆっくりと、本当にゆっくりと、手のひらで土に圧をかけていきます。右手の親指の付け根あたりで横から、左手で上から、優しく、しかし確実に押さえていく。すると、手に「ブルブルブル…」という振動が伝わってくるはず。これが「土が中心からズレている」というサイン。この振動が「スーッ…」と消えて、まるでそこに土がないかのように、手が全く振動しなくなる瞬間が訪れます。
これが、中心が出た合図!この瞬間、本当に感動しますよ。「あ、今、私と土とろくろが一体になった…!」って。最初は10分かかっても、20分かかってもいい。この「スーッ」の感覚を、身体が覚えるまで、何度も何度も練習してみてください。この感覚さえ掴めば、電動ろくろはもうあなたのものです。
身体で覚えろ!ブレない土台を作るための正しい姿勢と手の形
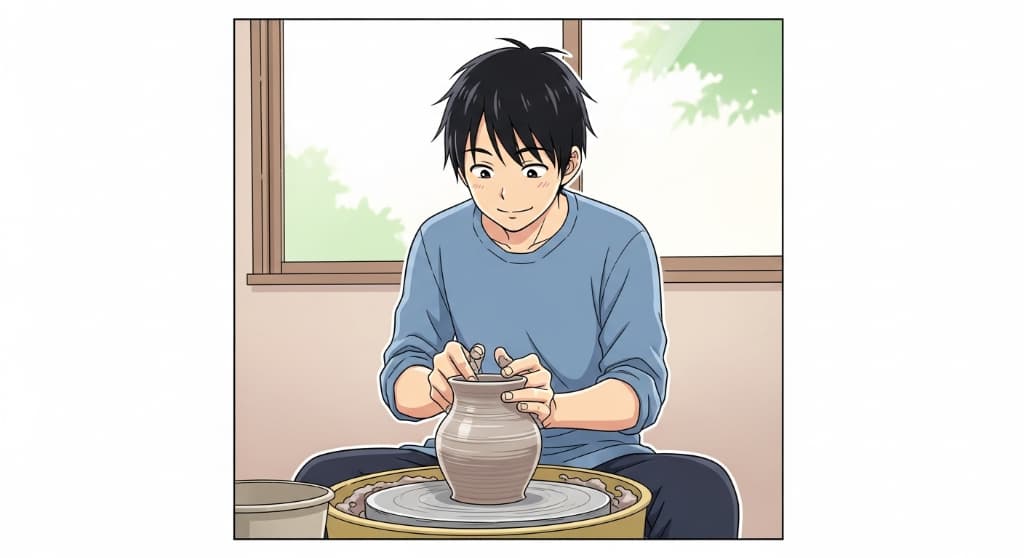
中心出しが9割とは言いましたが、その中心出しを成功させるためには、それを支える「身体の使い方」が不可欠です。スポーツと一緒で、正しいフォームを知らないと、いくら練習してもうまくいかないんですよね。ここでは、私が先生に口酸っぱく言われ続けた、ブレない土台を作るための姿勢と手の形について、熱く語らせてください。
椅子とろくろの距離感、実はめちゃくちゃ大事だった
「え、そんなことから?」と思うかもしれません。でも、本当に大事なんです。最初の頃、私はなんとなく楽な位置に座っていました。ろくろからちょっと離れて、腕を伸ばして作業するような感じ。でも、これだと腕がプルプル震えて、全然力が伝わらない。
正解は、「ろくろに抱きつくくらい、ぐっと近づく」こと。椅子の高さを調整して、膝がろくろの台より少し高くなるくらいの位置に座ります。そして、ろくろの縁に、自分の太ももが軽く触れるくらいまで、ぐいっと前に出る。ちょっと窮屈に感じるかもしれませんが、この姿勢が安定感を生むんです。
なぜなら、この後に出てくる「肘の固定」に繋がるから。ろくろと体が近いことで、肘を自分の太ももや腰骨にしっかりと固定できるようになります。これが遠いと、肘が宙に浮いてしまって、力の支点がなくなるんですね。まずは、ろくろと親友になるみたいに、思いっきり近づいてみてください。
脇を締めて肘を固定!体幹で支えるという感覚
「脇を締めなさい!」「肘を固定しなさい!」これは陶芸教室で100万回は聞いた言葉です。本当に、呪文のように言われ続けます。でも、それだけ重要だということ。
先ほどお伝えしたように、ろくろにぐっと近づいたら、両脇をきゅっと締めます。そして、肘を自分の太もも、もしくは腰骨あたりに「ぐっ」と押し当てて固定する。こうすることで、腕が自分の体の一部として完全にロックされます。腕というより、体幹。身体の軸そのもので土にアプローチする感覚です。
手先だけでこねくり回そうとすると、ろくろの回転の力に負けて、手があっちこっちに持っていかれます。でも、体幹で支えていれば、ろくろがどれだけ力強く回っても、自分の軸はブレません。最初はロボットみたいで窮屈に感じるかもしれません。でも、この「不自由さ」こそが、安定した作品を生み出すための「自由」に繋がるんです。騙されたと思って、一度、ガチガチに体を固めてみてください。土の反応が全然違うことに驚くはずですよ。
指先じゃない、手のひら全体で土と対話するイメージ
さて、姿勢が固まったら、いよいよ土に触れます。この時の手の形もポイント。初心者はつい、指先に力を入れてしまいがち。でも、指先という「点」で力を加えると、土に余計な凹凸を作ってしまう原因になります。
意識するのは、「手のひら全体」、特に親指の付け根のふっくらした部分(母指球)や、手のひらの側面といった「面」で土を包み込むことです。まるで、土と握手するかのように、あるいは、赤ちゃんの頭をそっと撫でるかのように、優しく、しかし広い面積で接触する。
土殺しや中心出しの時は、左手は土の側面を支え、右手は上からかぶせるようにして、両手でボールを包むような形を作ります。この時、指先は力を抜いて、あくまで添えるだけ。力を加えるのは、固定した肘から伝わってくる体幹の力。それを、手のひらという広い「面」を通して、じんわりと土に伝えていく。
「土と対話する」って、ちょっとポエティックな表現に聞こえるかもしれません。でも、本当にそういう感覚なんです。指先で一方的に命令するんじゃなくて、手のひら全体で「君はどうなりたいの?」と土の声を聞く。そんなイメージを持つだけで、力のかけ方が自然と優しく、的確になっていきますよ。
いよいよ成形!ぐにゃりを卒業するための指先の魔法

さあ、土殺しと中心出しという最大の難関を乗り越え、あなたの目の前には、静かに、そして完璧に中心で回る粘土の塊があるはずです。ここからが、いよいよ形を作っていく、陶芸の醍醐味!でも、油断は禁物。ここで焦ると、せっかく整えた土がまた「ぐにゃり」の世界に逆戻りです。ここからは、繊細な指先のコントロールが鍵を握ります。
穴を開ける「指入れ」は焦らずゆっくり垂直に
まず、うつわの「中」を作るために、中心に穴を開けていきます。これを「指入れ」と言います。中心出しが完璧にできていれば、土のてっぺんは完全に静止しているはず。そのど真ん中に、利き手の親指、もしくは人差し指と中指を揃えて、ゆっくりと、まっすぐ下に差し込んでいきます。
ここでのコツは、とにかく「焦らないこと」と「垂直を意識すること」。斜めに入ってしまうと、底の厚みが均一にならず、後で歪みの原因になります。ろくろの回転の勢いを借りて、指が自然に吸い込まれていくような感覚で、本当に少しずつ。
そして、もう一つの大事なこと。それは「底の厚みを残す」こと。作りたい器の底の厚さ(だいたい1cmくらい)をイメージして、そこまで指が到達したらストップ!底まで貫通させちゃったら、もう大変。初めての時は、横に針を置いて、深さを確認しながらやるのも良い方法です。左手は、必ず土の側面を優しく支えて、土が外側に逃げないようにサポートしてあげてくださいね。
土を上に伸ばす「筒描き」は内と外の手の連携プレー
穴が開いたら、いよいよ壁を上に伸ばしていく「筒描き(つつびき)」という工程です。これができれば、湯呑みやお茶碗の形が見えてきます。一番テンションが上がるところ!
筒描きは、内側の指と外側の指で土の壁を挟み、少しずつ上に引き上げていく作業。まさに連携プレーです。内側に入れるのは、利き手じゃない方の人差し指か中指。外側は、利き手の指、もしくはスポンジを当てます。
ここでの最大のコツは、「内側の指と外側の指が、常に同じ高さにあること」。そして、「内側の指が少しだけ強い力で押すこと」です。内側の指がリードして、外側の指はそれに寄り添ってついていくだけ、というイメージ。外側の力が強いと、器がどんどんすぼんでしまいます。逆に内側が強すぎると、お皿みたいに開いてしまう。この力加減が、本当に絶妙なんです。
最初は欲張らず、下から上まで、3回くらいに分けてゆっくり引き上げていきましょう。一気に高くしようとすると、壁が薄くなりすぎて腰が砕け、あの悪夢の「ぐにゃり」が再発します。土の声を聴きながら、少しずつ、少しずつ。指先に伝わる土の厚みを感じながら、均一な厚さを目指して引き上げていく。この集中する時間、たまらなく好きです。
唇(縁)が波打つのを防ぐ「なめし革」の使い方
筒描きでだいたい形ができてきたら、最後に口の当たる部分、「唇(くちびる)」や「縁(ふち)」を整えます。指で引き上げたままの状態だと、縁が少し波打っていたり、指の跡が残っていたりします。これを滑らかに仕上げるのが「なめし革」です。
なめし革は、鹿の皮などでできた、薄くて柔らかい革のこと。これを二つ折りにして、水で軽く湿らせます。そして、回転している器の縁を、このなめし革で優しく、本当に優しく挟み込む。
力を入れすぎは禁物。本当に「触れるか触れないか」くらいの力で、すーっと当てるだけです。すると、あら不思議。さっきまで少しガタガタしていた縁が、つるんと滑らかな、綺麗な円に仕上がります。この一手間を加えるだけで、作品の完成度がぐっと上がるんです。口当たりの良いうつわは、この丁寧な仕上げから生まれるんですね。この「つるん」の瞬間、思わず「おお…」と声が漏れますよ。
よくある失敗と、その場でできるリカバリー術(絶望するにはまだ早い!)

陶芸、特に電動ろくろは、失敗がつきものです。というか、失敗しない日はない、と言っても過言ではないかもしれません。でも、大丈夫。ほとんどの失敗は、取り返しがつきます。絶望して粘土を叩きつける前に、ちょっとだけ試してみてほしいリカバリー術があるんです。それに、失敗から学ぶことって、めちゃくちゃ多いんですよ。
ケース1「中心がズレてどうしようもない時」の応急処置
成形の途中で、「あ、やばい。なんかブレてきた…」と感じる瞬間。ありますよね。原因は、無理な力をかけたとか、ちょっと集中が途切れたとか、色々です。完全にぐにゃぐにゃになる前なら、まだ間に合います。
まずは、ろくろの回転を少し落としましょう。そして、もう一度、基本に立ち返ります。脇を締めて、肘を固定。両手で器全体をそっと、本当にそっと包み込みます。そして、ほんの少しだけ圧をかけて、器全体を「真ん中に寄せてあげる」イメージ。これを「締め直す」なんて言ったりします。
この時、決して力で無理やり中心に戻そうとしないでください。あくまで、器が「あ、こっちが中心だったわ」と自分で戻ってくるのを手伝ってあげる感覚です。これを数秒やるだけで、ブレがかなり収まることがあります。それでもダメなら?…うん、潔くやり直しましょう!その粘土はまた練り直せば使えるから、大丈夫。
ケース2「薄くしすぎて穴が開いちゃった!」時の悪あがき
筒描きに夢中になっていると、やってしまいがちなのが、壁を薄くしすぎて「ぴゅっ」と指が貫通してしまう事故。あー!って声が出ますよね。もうダメだ…と諦めたくなる気持ち、わかります。でも、小さな穴なら、まだ悪あがきできます。
まず、その穴の周りの土を、指でそーっと中央に寄せてきます。まるで、傷口を寄せるように。そして、器の内側から、少しだけ粘土を持ってきて(共土、といいます)、その穴にペタッと貼り付け、指で優しく馴染ませるんです。絆創膏を貼るみたいに。
もちろん、完璧には塞がらないことも多いです。焼いたらそこからヒビが入るかもしれない。でも、「これも挑戦の証だ」と思えば、なんだか愛おしく見えてきませんか?それに、このリカバリーを経験しておくと、「これ以上薄くしたらヤバい」という感覚が、指先に叩き込まれるんですよ。失敗は最高の先生です。
ケース3「形が歪んでしまった…」これも味だと言い張る勇気
一生懸命作ったけど、なんだか左右非対称。ちょっと口が歪んでる。綺麗な円になっていない…。うん、あります。というか、初心者のうちは、それが当たり前です。でも、それを「失敗」と断じるのは、まだ早い。
ちょっと見方を変えてみてください。その歪み、なんだか手作り感があって、温かくないですか?完璧なシンメトリーの工業製品にはない、唯一無二の「表情」に見えてきませんか?そうです、これは「失敗」ではなく「味」なんです。そう言い張る勇気を持ちましょう!
私が最初に作ったお茶碗なんて、もうひどいもんでした。高台(底の部分)がガタガタで、テーブルに置くとカタカタ揺れる。でも、自分で作ったその不格好な茶碗で飲むお茶は、どんな高級な器で飲むより美味しく感じました。完璧を目指すことも大切だけど、その時々の自分の未熟さや、一生懸命さの跡が残った器を愛でるのも、陶芸の素晴らしい楽しみ方の一つだと、私は思いますよ。
道具を味方につけよう!初心者が揃えたい便利な相棒たち

電動ろくろは、自分の手と土だけで完結するものではありません。様々な道具を「相棒」として使いこなすことで、作業効率がぐんと上がり、表現の幅も広がります。ここでは、私が「これだけは絶対にあった方がいい!」と心から思う、基本的な道具たちをご紹介しますね。最初はたくさんあって戸惑うかもしれませんが、それぞれの役割を知ると、どんどん愛着が湧いてきますよ。
シッピ、針、弓…これだけは持っておきたい基本の道具
まず、絶対に欠かせないのが「シッピ」。これは、完成した作品をろくろ板から切り離すための道具です。木の取っ手に、細い針金や糸がついています。これが無いと、せっかく作った作品をろくろから下ろせません。使い方は、作品の根元にシッピの糸をぴんと張って当て、ろくろをゆっくり手で回しながら、すーっと引き抜くだけ。この瞬間は、達成感がありますよ。
次に「針」。その名の通り、粘土用の長い針です。これは、器の縁の高さを揃えたり、不要な部分を切り取ったり、深さを測ったりと、とにかく万能。特に、縁を水平にスパッと切りたい時に、針を固定してろくろを回すと、カッターのように綺麗に切ることができます。一本持っていると、作業の精度が格段に上がります。
そして「弓」。これは、粘土の塊から、使う分だけを切り出すための道具。ピアノ線のようなものが張ってあり、これで大きな粘土の塊をスパッと切ります。手でちぎるよりも断面が綺麗で、気泡のチェックもしやすい。この3つは、陶芸道具セットにも大体入っている、まさに「三種の神器」ですね。
意外と見落としがち?スポンジとタオルの重要性
シッピや針のような専門道具も大事ですが、私が声を大にして言いたいのは「スポンジとタオルの重要性」です。え、そんな地味なもの?と思うなかれ。この二つが、作業の快適さと作品の仕上がりを大きく左右するんです。
まず「スポンジ」。これは、ろくろを挽く時に、手に水を含ませるために使います。バケツの水を直接手ですくうより、スポンジで含ませた方が、水量のコントロールがしやすい。また、筒描きの時に外側の手にスポンジを当てて滑りを良くしたり、最後の仕上げで器の表面を滑らかにしたりと、大活躍します。目の粗さが違うものをいくつか持っておくと、さらに便利ですよ。
そして「タオル」。これは言わずもがな、手を拭くためですが、それだけじゃありません。作業台に一枚敷いておくと、飛び散る泥を受け止めてくれて後片付けが楽になります。そして何より、頻繁に手を拭いて、手の水分量を一定に保つことが大事。手がびしょびしょのままだと、粘土がゆるくなりすぎてしまいます。汚れてもいいタオルを、必ず手の届くところに数枚用意しておく。このちょっとした準備が、集中力を切らさずに作業を続けるための、縁の下の力持ちなんです。
まとめ 電動ろくろは、あなたと土との対話そのもの

さて、ここまで電動ろくろのコツについて、私の体験や失敗談を交えながら、かなり熱く語ってきました。土殺しと中心出しの大切さ、ブレないための姿勢、そして成形の際の指先の感覚。たくさんのテクニックをお伝えしてきましたが、最後に一番伝えたいのは、電動ろくろは「技術」であると同時に、あなたと「土」とのコミュニケーション、つまり「対話」そのものだということです。
最初は、土がまるで言うことを聞かない、わがままな生き物のように感じるかもしれません。でも、それは私たちが土の声を聴けていないだけ。力でねじ伏せようとすれば反発し、優しく中心を探ってあげれば素直に回り、指先で「こうなりたい」と導いてあげれば、美しい形へと姿を変えてくれる。土は、いつだって正直なんです。
だから、どうか失敗を恐れないでください。粘土がぐにゃりと歪んでも、穴が開いてしまっても、それは失敗ではなく、あなたが土と対話しようと試みた、かけがえのない経験の証です。その歪みこそが、世界に一つだけの、あなたの「味」になります。完璧な円を作ることだけが、陶芸のゴールではありません。土に触れ、集中し、時には悩み、そして形が生まれた瞬間に喜びを感じる。そのプロセスすべてが、何にも代えがたい魅力なんです。
この記事が、あなたの電動ろくろライフの、ほんの少しでも助けになれば、こんなに嬉しいことはありません。さあ、エプロンを締めて、またあのひんやりとした土に触れてみませんか?きっと前回よりも、土が少しだけ、あなたに心を開いてくれるはずですよ。