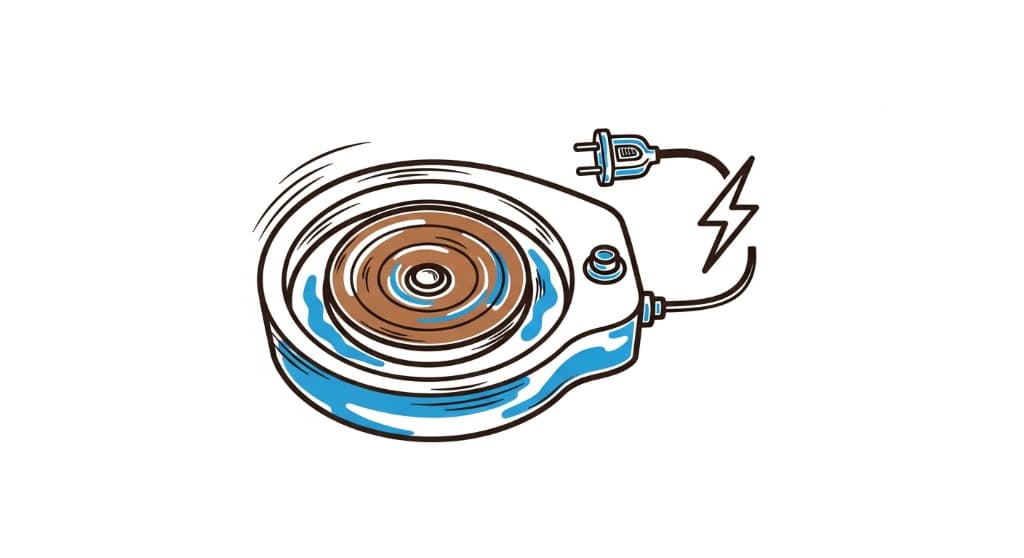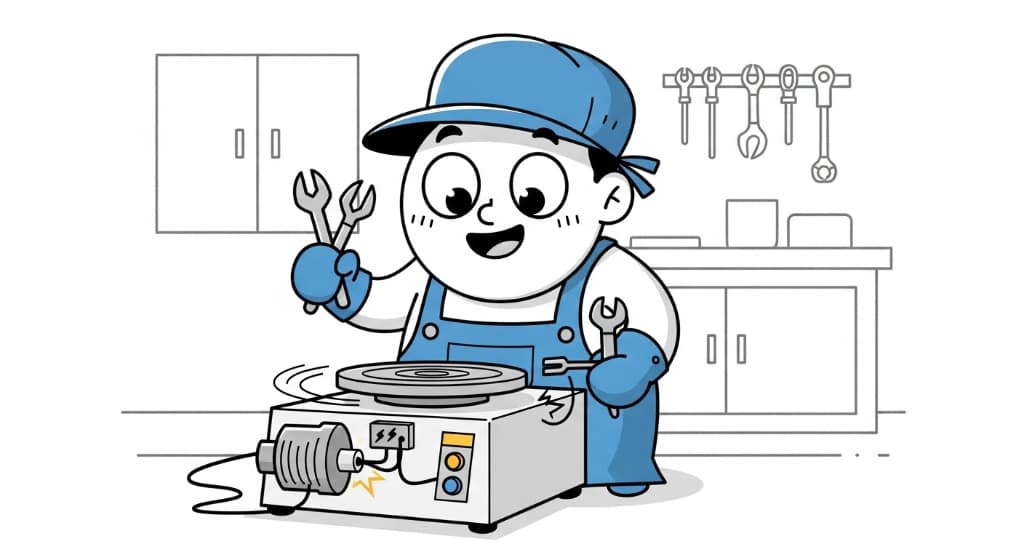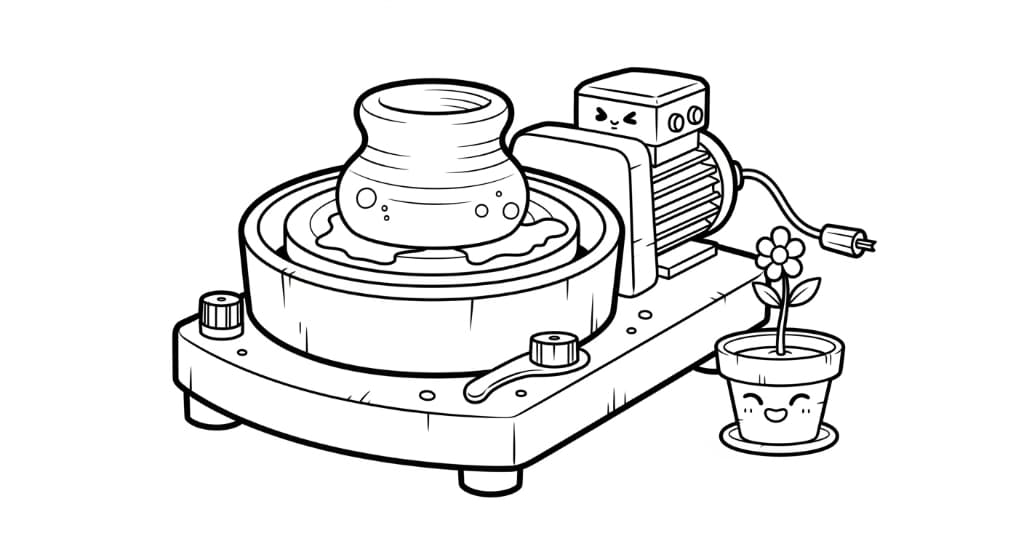「才能ないかも…」電動ろくろの失敗で心が折れそうなあなたへ。実はそれ、みんな通る道なんです。

ぐにゃり、と粘土が遠心力に負けて歪む。べちゃっと無残な塊になる。ああ、まただ…。電動ろくろに向かうたびに、理想の形からはほど遠い「何か」を生み出してしまい、「私、もしかして陶芸の才能、まったくないんじゃないか…」なんて、落ち込んでいませんか?
その気持ち、痛いほどわかります。本当に。でも、今すぐその考えはゴミ箱にポイしちゃってください!
なぜなら、電動ろくろの失敗は、才能の有無とはまったく、これっぽっちも関係ないからです。断言します。それは、陶芸を志す誰もが必ず通る、いわば「お約束」のイベントみたいなもの。私自身、粘土を前に何度絶望し、教室の隅で膝を抱えたい気持ちになったことか…。
この記事では、そんな「失敗」という名の最高の友人との付き合い方を、私の血と汗と涙の(ちょっと大げさかな?)経験談を交えながら、余すところなくお伝えします。
読み終える頃には、あなたの失敗に対する見方が180度変わるはず。「もうろくろなんて見たくない」と思っていたのが、「よし、次はこうしてみよう!」と、ワクワクしながら土に向かえるようになります。失敗の原因がわかれば、対策も立てられる。そして何より、失敗そのものが愛おしく思えてくるかもしれません。あなたの陶芸ライフを、もっと自由で楽しいものに変える旅へ一緒に出かけましょう!
電動ろくろの失敗は「才能」ではなく「お約束」です

まず、声を大にして言わせてください。電動ろくろで最初からうまくいく人なんて、ほぼいません!もしいたら、その人は前世でろくろ職人だったのかもしれない、うん、たぶん。あなたが今感じている絶望感や無力感は、陶芸家への道を歩み始めた証拠みたいなものです。だから、どうか自分を責めないでくださいね。
そもそも電動ろくろは難易度が高いという事実
考えてもみてください。回転する台の上で、柔らかくて気まぐれな土の塊を、指先の微妙な力加減だけで形にしていくんですよ?これ、冷静に考えたらものすごく高度な技術だと思いませんか。
陶芸教室の先生や、動画サイトのプロたちは、まるで鼻歌でも歌いながらやっているかのように、スイスイっと美しい器を作り上げますよね。あれを見て、「なんだ、簡単そうじゃん!」って思ってしまうのが、最初の大きな落とし穴なんです。
あれは、何百、何千、いや何万回という失敗と練習の積み重ねの末にたどり着いた「境地」です。自転車に補助輪なしで初めて乗る日を思い出してください。何度も転んで、膝をすりむいて、やっと乗れるようになったはず。電動ろくろは、自転車どころか、いきなり一輪車に挑戦するようなものかもしれません。だから、失敗して当たり前。ぐにゃぐにゃになって当たり前。まずは「電動ろくろは、めちゃくちゃ難しい!」という事実を、どーんと受け入れてしまいましょう。それだけで、心がずいぶん軽くなるはずですよ。
私が体験した「地獄の初ろくろ」と絶望感
かくいう私も、初めて電動ろくろに触った日のことは、今でも鮮明に思い出せます。あれは確か、梅雨入り前のジメっとした土曜の午後でした。陶芸体験教室に、ウキウキしながら参加したんです。「おしゃれなカフェオレボウルを作るんだ!」なんて、心の中は夢でいっぱい。
先生がお手本を見せてくれて、いざ自分の番。「はい、じゃあまず土殺しからねー」と言われても、もう何が何だか。力を入れればいいのか、抜けばいいのか。土は私の言うことなんてまったく聞かず、ただただ遠心力で外へ外へと逃げていく。やっとの思いで中心に据えた(つもりになった)土に指を入れた瞬間、ぐにゃり。ああ、無情。
隣に座っていたおばあちゃんは、楽しそうにお孫さんとおしゃべりしながら、きれいな湯呑を2つも3つも作っているのに…。なんで?どうして私だけ?焦れば焦るほど、手は汗で滑り、水は多すぎ、土はドロドロの悲惨な状態に。最終的に、先生が気の毒そうな顔で「…うん、これはもう一回やり直そうか」と、私の目の前の「何か」をワイヤーで切り取った時のあの絶望感。正直、「私、今日何しに来たんだっけ…」って、本気で思いました。たぶん、あの時の私の顔、相当ひどかったと思います。でも、今となっては笑い話。あなたも、今のその失敗は、数年後にはきっと笑い話になりますから。
なぜ?あなたの土が言うことを聞かない5つの根本原因

「失敗するのが当たり前なのはわかった。でも、やっぱり悔しい!」うんうん、その気持ち、よーくわかります。じゃあ具体的に、なぜ私たちの土は、あんなにも反抗的な態度をとるのでしょうか。実は、失敗にはちゃんと理由があるんです。ここでは、初心者が陥りがちな「5つの根本原因」を、私の失敗談と共に解説していきますね。これを読めば、「ああ、私の失敗はこれだったのか!」と、きっと腑に落ちるはずです。
原因1 土殺しが不十分で土が暴れていませんか?
まず最初の関門、「土殺し(つちごろし)」。すごい名前ですよね、ちょっと物騒で。でも、これは土をいじめているわけじゃなくて、土の中の空気の粒や硬さのムラを均一にする、とっても大事な作業なんです。いわば、本格的な作業に入る前の「土との対話」であり、「準備運動」。
初心者の頃の私は、この作業の意味がよくわかっていませんでした。「早く形を作りたい!」という気持ちが先走って、なんだか適当に上げ下げして「はい、終わり!」ってやっちゃってたんです。でも、この土殺しが不十分だと、土の中にまだ気まぐれな部分が残っている状態。そんな土をろくろで回したらどうなるか?…もう、お分かりですよね。
土が、中で「俺はまだ準備できてねえぞ!」って暴れだすんです。中心にいるように見えても、微妙なブレが残っていて、指で力を加えた瞬間にそのブレが増幅されて、ぐにゃり。ああ、悲劇。土殺しは、一見地味で退屈な作業に思えるかもしれません。でも、ここでどれだけ丁寧に土と向き合えるかが、その後の成否を大きく左右するんです。愛のムチだと思って、じっくり時間をかけてみてください。ここでサボると、後で土が盛大にグレます。
原因2 中心が出せない…全ての悲劇はここから始まる
土殺しをクリアしたら、次なる大ボスが「中心出し(ちゅうしんだし)」です。ろくろの中心に、土の塊の中心をぴったり合わせる作業。これがね、本当に、本当に難しい!全ての悲劇はここから始まると言っても過言ではありません。
中心がほんの少しでもズレていると、ろくろを回した時に土が波打つようにブレます。そのブレた土を、無理やり指で押さえつけようとしても、絶対にうまくいきません。むしろ、ブレはどんどん大きくなって、最終的には遠心力に負けてびろーんと無残な姿に…。
私も最初の頃は、この「中心」が全然わからなかった。「これで合ってる…のか?」「なんか、ちょっと揺れてる…気がする…?」そんな曖昧な感覚のまま次の工程に進んで、案の定、撃沈。これを何度繰り返したことか。
コツは、ろくろの回転に自分の体を預けるような感覚、とでも言いましょうか。肘をしっかり太ももや腰に固定して、体全体で土を受け止める。そして、両手で優しく、でも力強く包み込んで、土が「コトン」と静かに収まる一点を探すんです。地球の自転を感じるレベルで集中しないと…というのは言い過ぎですが、それくらい繊細で重要な作業。中心が出せれば、作品の8割は完成したも同然!それくらい、大事なポイントなんです。
原因3 指の力加減がわからない!強すぎても弱すぎてもダメなジレンマ
さて、無事に中心が出せたとしましょう。次はいよいよ、土に穴をあけ、壁を薄く伸ばしていく工程です。ここで待ち受けているのが「力加減」という、とんでもなく厄介な問題。
強すぎれば、壁がえぐれてしまったり、薄くなりすぎてへたってしまったり。かと思えば、弱すぎると土はまったく動いてくれず、ただ指が滑るだけ。この「豆腐を扱うように、でも芯はしっかり」みたいな、矛盾したような力加減が、本当にわからない!「え?何その矛盾?どうしろと?」って思いますよね。わかります、ええ、わかりますとも。
特に難しいのが、内側と外側から指で土を挟んで、上に引き上げていく「筒描き(つつびき)」という作業。左右の指の力を均等にしないといけないんですが、これがまあ、うまくいかない。片方の指に力が入りすぎた瞬間に、そこだけ薄くなって、全体がぐにゃり。ああ、何度この「ぐにゃり」に心を折られたことか。
こればっかりは、もう、経験としか言いようがない部分も大きいんです。でも、意識すべきは「焦らないこと」。ゆっくり、本当にゆっくり、土の反応を感じながら指を動かす。土が「今、ちょっと苦しいよ」って言ってるのか、「もっと伸ばしていいよ」って言ってるのか。その声なき声を聞くような感覚です。最初は聞こえなくても、失敗を繰り返すうちに、だんだんと指先が土の言葉を理解できるようになってきますから。
原因4 水の量が多すぎる?少なすぎる?土との対話不足
電動ろくろにおいて、水は潤滑油の役割を果たす、なくてはならない存在です。手が乾いていると、摩擦で土を傷つけてしまいますからね。でも、この水の量もまた、初心者を悩ませる大きな要因なんです。
焦っている時ほど、やたらと水をつけすぎてしまう。これが私の悪い癖でした。手が滑らないように、滑らかに動くようにと、スポンジで水をジャバジャバ…。するとどうなるか。土が必要以上に水分を吸って、どんどん柔らかく、腰のない状態になってしまうんです。そうなるともう、自重を支えきれなくなって、べちゃーっと潰れてしまう。まるで、土が「もう水いらないって!お腹タプタプだよ!」って悲鳴を上げているかのよう。
逆に、水が少なすぎてもダメ。指の滑りが悪くなって、土の表面を引っ掻いてしまい、そこから亀裂が入ったり、形が歪んだりする原因になります。
じゃあ、適量ってどれくらいなの?って話ですよね。目安としては、「手のひらが常にしっとり濡れている状態」をキープすること。でも、土がビチャビチャになるほどではない、という絶妙なラインです。これもまた、土との対話。土の表面をよく見て、「あ、ちょっと乾いてきたな」と感じたら水を足す。「なんだか土が疲れてきたな」と感じたら、少し水を控えて様子を見る。そんな風に、土のコンディションに合わせて水の量を調整できるようになると、失敗はぐっと減りますよ。
原因5 姿勢と意識がブレている!あなたの心が土に伝わる
最後は、少し精神論っぽく聞こえるかもしれませんが、これが意外とバカにできないんです。「姿勢」と「意識」の問題です。
電動ろくろは、手先だけでやるものじゃありません。全身を使ってやるものです。猫背になっていたり、肩に力が入ってガチガチだったり、肘が体に固定されていなかったりすると、そのブレが指先に伝わって、作品を歪ませる原因になります。まずは、どっしりと椅子に座り、足でしっかり地面を踏みしめ、脇を締めて肘を体に固定する。この基本姿勢を確立するだけで、驚くほど土が安定します。
そしてもう一つ、あなたの「意識」です。嘘みたいだけど本当の話なんですが、あなたの心の迷いや焦りは、そのまま土に伝わるんですよ。「あ、失敗するかも…」と思いながら触った土は、本当に失敗する確率が高いんです。逆に、「大丈夫、できる!」と、リラックスして集中している時は、土も素直に言うことを聞いてくれることが多い。
これはオカルトでも何でもなくて、たぶん、心の迷いが指先の微妙な震えや力加減の乱れとなって現れるからなんでしょうね。だから、もし「今日はなんだか集中できないな」と感じたら、無理に形を作ろうとせず、土殺しや中心出しの練習だけして帰る、というのも一つの手です。土と向き合うことは、自分自身の心と向き合うことでもある。そう考えると、陶芸って、なんだかすごく奥深いと思いませんか?
失敗から学ぶ!「次こそは」に繋げる具体的な練習法

失敗の原因がわかったら、次は対策です!ただやみくもに失敗を繰り返すだけでは、心がすり減ってしまいますからね。「失敗は成功のもと」という言葉を、本気で実践するための具体的な練習法をご紹介します。地味なものもありますが、効果は絶大。これを続ければ、あなたのろくろスキルは確実にレベルアップしますよ!
とにかく「土殺し」と「中心出し」だけを繰り返す地味な練習
「えー、またその話?」って思うかもしれません。でも、ごめんなさい、またこの話です。それくらい大事なんです。正直に言います。この練習、めちゃくちゃ地味です。そして、つまらないです。ええ、つまらない!作品が形にならないんですから、達成感もありません。
でも、考えてみてください。どんなスポーツでも、基礎練習が一番大事ですよね。毎日毎日、素振りやパス練習を繰り返す。それと同じです。土殺しと中心出しは、電動ろくろにおける「素振り」なんです。
具体的には、土の塊をろくろに据えて、土殺しをする。そして、完璧に中心を出す。ブレが完全になくなったら、それで終わり。またその土を一度ろくろから外して、最初からやり直す。これを、ひたすら繰り返します。
最初は全然うまくいかないでしょう。でも、10回、20回と繰り返すうちに、だんだんと「あ、この感覚か」という瞬間が訪れます。手に吸い付くように土が中心に収まる、あの快感。これを一度でも味わうと、世界が変わります。この地味な反復練習こそが、遠回りに見えて、実は上達への最短ルートなんです。騙されたと思って、次の陶芸教室では、最初の30分、これだけをやってみてください。その後の作業の安定感が、まるで違うことに驚くはずです。
小さな器から始める勇気。いきなり大物を作ろうとしない
陶芸を始めると、ついつい夢が膨らみがちですよね。「おしゃれなパスタ皿が欲しいな」「大きな花瓶を作ってみたいな」「ラーメンどんぶり、自作できたら最高じゃない?」その気持ち、痛いほどわかります。私もそうでした。でも、ちょっと待って!その大きな夢は、一度ポケットにしまっておきましょう。
初心者がいきなり大きな器を作ろうとすると、ほぼ100%失敗します。なぜなら、土の量が増えるほど、土殺しも中心出しも格段に難しくなるから。それに、壁を高く、薄く引き上げていく技術もより高度なものが求められます。難易度ハードモードでいきなりラスボスに挑むようなものです。
だから、まずは小さな器から始める勇気を持ちましょう。おすすめは、ぐい吞みやお猪口(おちょこ)サイズ。使う土の量も少なくて済むし、高さも出さなくていいので、失敗のリスクがぐっと下がります。
小さな器でも、土殺し、中心出し、穴あけ、筒描き、成形という、器作りの基本工程はすべて詰まっています。まずはこの小さな世界で、一連の流れを完璧にマスターすることを目指すんです。小さな成功体験を積み重ねることが、自信に繋がります。「なんだ、ぐい吞みか…」なんて侮ってはいけません。この小さな器に、電動ろくろの全てが凝縮されているんですから。ここで完璧な形が作れるようになれば、少しずつサイズアップしていくのも怖くなくなりますよ。
先生や先輩の「手」をガン見する!動画とは違う生の情報量
今は本当に便利な時代で、YouTubeなどで検索すれば、プロの陶芸家が電動ろくろのテクニックを解説してくれる動画がたくさんあります。私もよく見ますし、ものすごく勉強になります。でも、動画だけでは絶対に得られない情報があるんです。それが、「生」の情報量。
もしあなたが陶芸教室に通っているなら、それは最大のチャンスです。先生や、自分より長くやっている先輩の手つき、指の動きを、もうストーカーか!ってくらいガン見してください。
動画では伝わりきらない、微妙な力の入れ方、抜き方。指のどの関節を使っているのか。土に触れる時のスピード。呼吸のタイミング。体全体の使い方。そういった「生」の情報は、同じ空間にいて初めて感じ取れるものです。「あ、今、ちょっと力を抜いたな」「内側の指より、外側の指の方が少し上にあるな」といった発見が、山ほどあるはずです。
わからないことがあったら、恥ずかしがらずにすぐに聞きましょう。「すみません、今の指の角度、もう一回見せてもらえませんか?」とか、「どうしてもここが厚くなっちゃうんですけど、どうしたらいいですか?」とか。上手な人は、たくさんの失敗を乗り越えてきた人です。だから、初心者の「わからない」という気持ちを、きっと理解してくれます。見て、聞いて、真似てみる。この繰り返しが、あなたを上達へと導いてくれる最高の近道ですよ。
失敗作を「失敗」で終わらせない思考の転換
ぐにゃっとなってしまった、あの無残な土の塊。見ているだけで悲しくなりますよね。でも、それをただの「失敗作」として粘土箱に戻してしまうのは、もったいない!あまりにも、もったいない!
その歪んだ塊は、ただの土くれではありません。それは、「なぜ失敗したのか」という原因が詰まった、貴重な「データ」なんです。
一度、ろくろを止めて、その失敗作をじっくり観察してみてください。どの部分から歪み始めましたか?壁の厚さは均一ですか?どこか極端に薄くなっている部分はありませんか?底の部分はどうなっていますか?
「ああ、やっぱり右手の力が強すぎたんだな。だから右側だけ薄くなって、そこから崩れたんだ」「中心がズレてたから、全体が波打って、遠心力に耐えられなかったんだな」「水をつけすぎて、土がヘタってるな」…などなど。失敗の原因を分析するんです。
そうやって「なぜ」を考える癖をつけると、次の挑戦で何を気をつけるべきかが明確になります。これは、ただ闇雲に回し続けるよりも、何倍も効果的な練習法です。あなたの目の前にある失敗作は、未来の成功作を生み出すための、最高の教科書なんですよ。そう考えると、なんだか失敗も悪くないなって、思えてきませんか?
電動ろくろとの向き合い方。失敗が怖くなくなる心の持ちよう

技術的な練習ももちろん大切ですが、それと同じくらい、いや、それ以上に大切なのが「心の持ちよう」です。電動ろくろが上手くなるためには、土と、そして自分自身と、どう向き合っていくか。ここでは、失敗が怖くなくなる、ちょっとした考え方のヒントをお伝えします。これを読めば、もっと肩の力を抜いて、陶芸を楽しめるようになるはずです。
完璧を求めすぎない。「味」という言葉の魔法
私たちは、お店で売っているような、左右対称で、どこにも歪みのない、つるんとした完璧な器を見慣れています。だから、いざ自分で作ろうとすると、無意識にその「完璧な形」を目指してしまう。そして、少しでも歪んだり、指の跡が残ったりすると、「ああ、失敗だ」と思ってしまう。
でも、ちょっと待ってください。そもそも、手作りの良さって何でしょう?
それは、「完璧じゃないこと」にあるんじゃないでしょうか。少し歪んでいる形。うっすらと残る指の跡。均一じゃない釉薬の色むら。それら全てが、機械で作られた量産品にはない、温かみであり、個性であり、世界に一つだけの「味」なんです。
「味」って、なんて便利な魔法の言葉でしょう!ちょっとくらい歪んでたって、「うん、味があるね!」でOK。少し形が気に入らなくても、「手作り感があって、逆にいいじゃない」でOK。完璧なシンメトリーを目指すのをやめて、「自分らしい味」を探す旅だと思ってみませんか?そう考えた途端、ろくろの上の土が、なんだかとても自由に見えてきます。失敗を恐れず、あなたの指が紡ぎ出す、あなただけの「味」を楽しんでみてください。
誰かと比べない。あなたのペースで土と遊ぶ時間
陶芸教室に行くと、どうしても周りの人が気になりますよね。「あの人はもうあんなに大きな壺を作っているのに、私はまだお茶碗もまともに作れない…」「同期で始めたはずなのに、どんどん差が開いていく…」そんな風に、誰かと自分を比べて、落ち込んでしまう。
気持ちはわかりますが、それは本当に、本当にもったいない!
陶芸は、スポーツのような競争ではありません。点数を競うものでも、速さを競うものでもありません。土と向き合い、自分と向き合う、とてもパーソナルな時間です。上達のスピードなんて、人それぞれで当たり前。不器用でも、時間がかかっても、いいじゃないですか。
大切なのは、誰かと比べることではなく、「昨日の自分より、ほんの少しでも成長できたか」どうかです。「前回より、中心出しがスムーズにできたな」「今日は、前より薄く壁を伸ばせたぞ」そんな小さな進歩を、自分で見つけて、自分で褒めてあげる。
陶芸は、あなたのための時間です。周りをキョロキョロ見るのをやめて、目の前の土と、自分の指先にだけ集中してみましょう。そこには、誰にも邪魔されない、穏やかで豊かな「あなただけの時間」が流れているはずです。あなたのペースで、土と遊ぶ。それでいいんです。
「今日は何を作ろう」ではなく「今日は土とどう触れ合おう」と考えてみる
私たちはついつい、「目的」に縛られがちです。「今日こそは、お茶碗を完成させるぞ!」「マグカップを3つ作るのが目標!」もちろん、目標を持つことは素晴らしいことです。でも、その「〜ねばならない」という気持ちが、時として自分を追い詰め、楽しむ心を奪ってしまうことがあります。
もし、ろくろの前に座るのが少し億劫に感じたり、失敗が怖くて手が動かなかったりするなら、一度その「目的」から離れてみませんか?
「今日は何を作ろう」と考えるのをやめて、「今日は土とどう触れ合おうかな」と考えてみるんです。
例えば、「今日はひたすら土の感触を楽しむ日にしよう」と決めて、ただ土殺しを繰り返してみる。土が手のひらで形を変えていく感覚、ひんやりとした温度、その重さ。五感をフルに使って、ただ土を感じる。あるいは、「今日はどこまで高く伸ばせるか、ゲーム感覚でやってみよう」と、完成させることが目的ではない挑戦をしてみる。途中で崩れたって構わない。だって、ゲームなんですから。
「作る」という目的から一旦自由になることで、土に触れること自体の喜びや楽しさを、もう一度思い出すことができます。そうやって、純粋に土との対話を楽しんだ後には、不思議と「よし、次は何か作ってみようかな」という意欲が自然と湧いてきたりするものです。焦らず、気負わず。まずは土と仲良くなることから、また始めてみませんか?
まとめ 電動ろくろの失敗は、あなたを成長させる最高のスパイス

さて、ここまで電動ろくろの失敗について、私の暑苦しいくらいの想いを語ってきました。もう一度、大切なことをお伝えしますね。電動ろくろの失敗は、あなたの才能がないからではありません。それは、上達するために誰もが通る、ごく自然なプロセスです。ぐにゃぐにゃになった土の塊は、あなたの挑戦の証であり、次へのステップに進むための貴重なデータなんです。
失敗には必ず原因があります。「土殺し」「中心出し」「力加減」「水の量」「姿勢と意識」、この5つのポイントを意識するだけで、あなたのろくろは劇的に安定するはずです。そして、地味な基礎練習を繰り返す勇気、小さなものから始める謙虚さ、そして何より、完璧を求めすぎず「味」を楽しむ心の余裕を持つこと。これらが、あなたを失敗の呪縛から解き放ってくれるでしょう。
陶芸は、自分自身と向き合う時間です。誰かと比べる必要なんてありません。あなたのペースで、あなたの作りたいものを、楽しんで作ればいいんです。失敗を恐れないでください。むしろ、たくさん失敗してください。失敗した分だけ、土の声が聞こえるようになり、指先が賢くなり、あなたの作品はどんどん味わい深くなっていきます。失敗は、あなたの陶芸ライフを豊かにしてくれる、最高のスパイスなんですから。
さあ、どうですか?なんだかまた、あのひんやりとした土に触りたくなってきませんか?次の教室では、きっと昨日より少しだけ、土と仲良くなれているはずですよ。