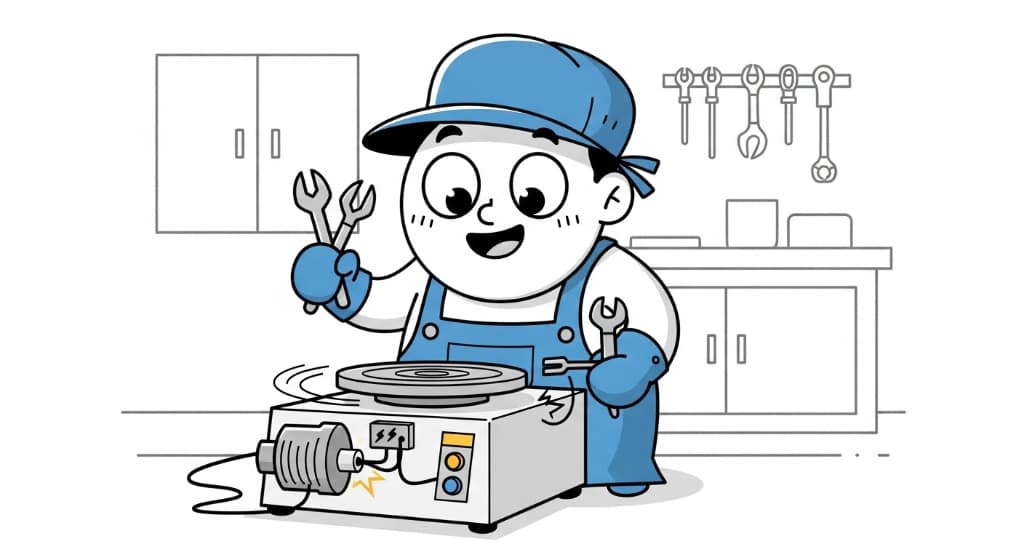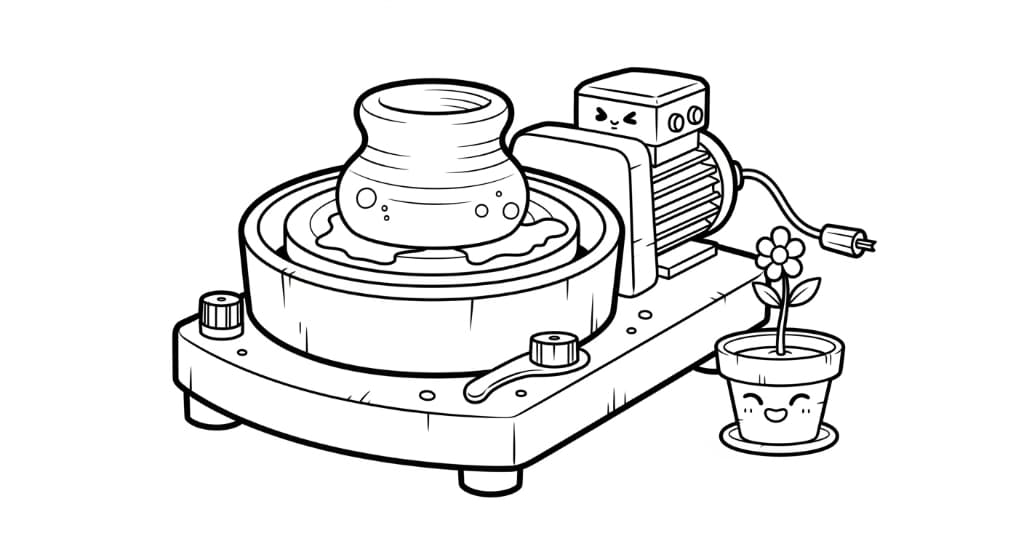電動ろくろでマグカップを作りたいあなたへ。成功への近道は?

「自分だけのオリジナルマグカップ、作ってみたいなぁ」
なんて、ふと思ったことはありませんか?
温かみのある土の感触、くるくると回るろくろの上で少しずつ形になっていく粘土。想像しただけで、なんだかワクワクしてきますよね。でも、同時に「電動ろくろなんて難しそう…」「不器用な私には無理かも」なんて不安もよぎる。わかります、すっごくわかります!何を隠そう、私も最初はそう思っていましたから。
電動ろくろでのマグカップ作りは、初心者でも絶対に楽しめます!そして、そこで手に入るのはただの器じゃありません。失敗も、苦労も、感動も、全部が詰まった「あなたの物語」そのもの。毎日のコーヒータイムが、何倍も、いや何十倍も愛おしくなる特別な体験が、あなたを待っています。
この記事では、陶芸ど素人だった私が、実際に電動ろくろでマグカップ作りに挑戦した一部始終を、包み隠さずお話しします。失敗談も、ちょっとしたコツも、感動した瞬間も、全部。読み終わる頃には、きっとあなたも「よし、やってみよう!」と、近所の陶芸教室を検索しているはず。さあ、一緒に土と格闘しながら、世界に一つだけの宝物、作ってみませんか?
電動ろくろのマグカップ作りは最高に楽しい

いきなり結論ですが、もうこれに尽きます。大変です。正直、思っていた10倍は難しい。でも、それ以上に100倍楽しいんです!なんでしょうね、この感覚。デジタルな世界に慣れきった指先が、原始的な「土」という物質と対話するような、不思議な充足感があるんですよ。お店で売っている、つるんとして完璧なマグカップも素敵です。でも、自分で作った、ちょっと歪んで、指の跡が残っているカップで飲むコーヒーの味は、本当に、本当に格別なんです。
私が陶芸にハマった、ある日の衝動
あれは確か、梅雨のジメジメした休日でした。やることがなくて、スマホでSNSをぼーっと眺めていたら、友人が投稿した一枚の写真に目が釘付けになったんです。それは、彼女が陶芸体験で作ったという、なんとも言えない味のある青いマグカップでした。完璧じゃない、むしろ少し歪んでいる。でも、それがたまらなく魅力的に見えた。「うわ、これいいな…!私も作りたい!」その瞬間、雷に打たれたみたいに衝動が走ったんです。
それからの行動は早かったですよ。すぐに「陶芸体験 初心者 東京」とかで検索して、一番雰囲気が良さそうな工房に予約を入れました。その時の私、たぶんちょっとどうかしてましたね(笑)。でも、あの時の衝動がなかったら、今こうして記事を書いていることも、毎朝お気に入りの自作カップでコーヒーを飲む幸せもなかったわけです。人生、何がきっかけになるかわからないものですよね。
難しそう?いやいや、そのハードルがたまらないんです
「電動ろくろって、映画とかで見るやつでしょ?なんか難しそう…」って思いますよね。はい、その通り、難しいです!断言します。特に最初の「土殺し(つちごろし)」と「センタリング」という工程。粘土の塊をろくろのど真ん中に固定して、芯を出す作業なんですけど、これがもう、言うことを聞かない。
先生は「力を抜いて、土の声を聞いて」なんて言うんですけど、こちとら土と会話した経験なんてないわけで。「え?声?何も聞こえませんが?」と心の中でツッコミまくりです。ぐにゃり、ぐにゃりと歪む粘土を前に、だんだんイライラしてきて、「もういい!今日のところは勘弁してやる!」って粘土に逆ギレしそうになるくらい(笑)。
でもね、不思議なんですよ。30分くらい格闘して、汗だくになって、先生に手伝ってもらって、ふっと粘土のブレが収まった瞬間があるんです。「あ、これか…!」っていう感覚。あの瞬間、脳内にドーパミンがドバドバ出るのがわかる。難しいからこそ、できた時の喜びが半端じゃない。この山あり谷ありの感じが、もう病みつきになるんです。
あなただけの「物語」がマグカップに宿る
お店に行けば、1000円も出せば素敵なマグカップが買える時代です。もっと安くて機能的なものもたくさんあります。でも、手作りのカップには、お金では買えない価値が宿るんですよ。
例えば、私が初めて作ったマグカップ。よく見ると、ちょっとだけ飲み口が歪んでいます。これは、最後に形を整える時に、うっかり指に力が入りすぎた跡。取っ手の付け根には、ちょっとだけヒビの補修跡があります。これは、乾燥させすぎた取っ手を慌てて付けようとして失敗した名残。
他人から見ればただの「失敗作」かもしれません。でも、私にとっては、その歪みもヒビも、全部が愛おしい「物語」なんです。「ああ、この時、先生に『力抜いて!』って3回言われたな」とか「このヒビ、もうダメかと思ったけど、先生が魔法みたいに直してくれたんだよな」とか。カップを見るたびに、あの日の奮闘が蘇ってくる。これって、最高の贅沢だと思いませんか?既製品には絶対にない、自分だけのストーリー。それこそが、手作りの一番の魅力なんだと、私は思います。
いざ挑戦!電動ろくろ体験でマグカップを作る流れ
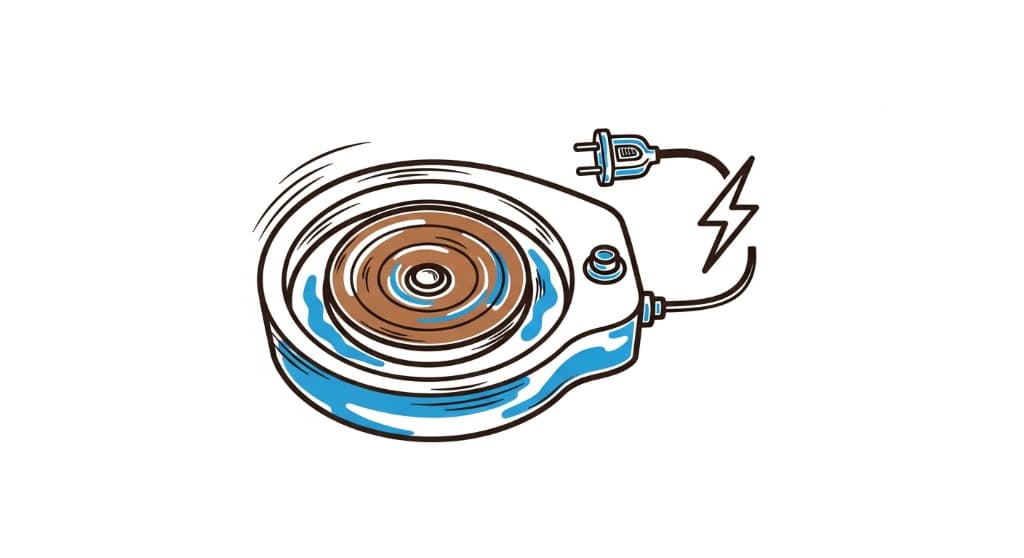
さて、ここからは実際の体験談を交えながら、マグカップ作りの流れを具体的にお話ししていきますね。陶芸体験って、だいたい2時間〜3時間くらいのコースが多いかな。その中で、粘土と格闘し、形を作り上げていくわけです。心の準備はいいですか?エプロンを締めて、いざ土の世界へ!
まずは心構えから。服装と持ち物、意外な落とし穴
まず服装。これはもう、絶対に「汚れてもいい服」一択です。工房でエプロンは貸してくれますが、甘く見てはいけません。泥水(粘土が溶けた水)が、思わぬところに跳ねます。特にズボン。気づいたら膝のあたりが泥だらけ、なんてことは日常茶飯事です。お気に入りの白いパンツなんて履いていったら、その日一日、ブルーな気持ちで過ごすことになりますよ。
そして、意外な落とし穴が「爪」。女性は特に注意してほしいのですが、ネイルアートをしている長い爪は、ろくろをやる上ではっきり言って邪魔です。粘土に爪の跡がガッツリ入ってしまって、綺麗な表面になりません。できれば、爪は短く切っていくのがベスト。私は何も考えずに行っちゃって、先生に「あー、爪、長いねぇ…」と苦笑いされました(笑)。
持ち物は、基本的には手ぶらでOKな工房が多いです。でも、汗をかくのでタオルはあった方がいいかも。あとは、完成した作品は後日郵送してくれる場合が多いので、その場で持ち帰る必要はありません。とにかく、身軽で、汚れてもヘコまない格好で行く。これが一番です。
土殺し(つちごろし)で土と対話する時間
さあ、いよいよ電動ろくろの前に座ります。目の前には、どーん、と粘土の塊。これをまず、ろくろの中心に据えて、菊練りされた粘土の粒子を整える「土殺し」という作業から始めます。名前が物騒ですよね(笑)。でもこれ、土と仲良くなるための、すごく大事な儀式なんです。
両手で粘土を包み込むようにして、ろくろを回しながら、ぐーっと力を入れて高くしたり、低くしたりを繰り返します。先生は「粘土の中心を意識して」「腰を入れて」なんて言うんですけど、もうね、粘土が暴れる暴れる。遠心力で外へ外へと逃げようとする粘土を、必死で抑え込む感じ。まるで、やんちゃなペットと格闘しているみたいです。
ここで焦っちゃダメなんです。私も最初は力任せにやろうとして、すぐに腕がパンパンになりました。「だーかーらー!言うこと聞いてよ!」って、粘土に話しかけてましたもん。でも、何度か繰り返すうちに、なんとなく粘土の動きが分かってくる。「あ、今、外に行きたがってるな」とか「このくらいの力で押さえると、素直になるな」とか。これが先生の言う「土との対話」の入り口なのかもしれません。この地味な作業が、後々の作りやすさを大きく左右するんですよ。
中心を出す「センタリング」が最大の山場!
土殺しで粘土と少しだけ心が通じ合えたら、次はいよいよ最大の難関、「センタリング」です。これは、粘土の塊をろくろの「ど真ん中」に、ブレないように固定する作業。これができていないと、この後どんなに頑張っても、ぐにゃぐにゃの歪んだ器しかできません。はっきり言って、マグカップ作りの成否の8割は、ここで決まります。
左手を添えて、右手でぐっと粘土を抑える。ろくろを回すと、ブルブルブル!と粘土が震える。これが「ブレ」です。このブレが完全になくなって、吸い付くようにピタッと真ん中で回り続ける状態を目指すんです。
これがねぇ、本当に難しい。ちょっと力を入れる場所がズレただけで、さっきまでマシだったブレが復活したりする。「うわああああ、戻った!」「なんでだよ!」って、何度心を折られそうになったことか。隣でスイスイやっているベテランっぽい人が神様に見えました。もうね、ここで半泣きです。でも、先生がそっと手を添えてくれて、「そうそう、こっちに力を入れてみて」と補助してくれる。すると、スッ…とブレが収まる瞬間が来るんです。
「できた…!」
この時の感動、わかります?世界が輝いて見える感じ。さっきまで憎たらしかった粘土が、急に愛おしい相棒に思えてくる。このセンタリングを乗り越えられたら、もうあなたは陶芸家の卵です!たぶん!
穴をあけて、壁を伸ばす。マグカップの形が見えてくる瞬間
センタリングという大きな山を越えたら、ここからは創造の時間。いよいよマグカップの形を作っていきます。まずは、ブレがなくなった粘土の塊の真ん中に、親指をそっと沈めていく。ずぶずぶ…と指が入っていく感触が、なんとも言えません。底に5mm〜1cmくらいの厚みを残して、穴をあけます。
次に、その穴に両手の指を入れて、内側と外側から壁を挟むようにして、ゆっくりと上に引き伸ばしていきます。これが、一番「陶芸やってる!」って感じがする作業かもしれません。下から上へ、下から上へ。焦らず、同じ力で、同じスピードで。これを意識するだけで、全然違います。
最初はただの粘土の塊だったものが、自分の指の力で、少しずつ筒状になっていく。だんだんと、マグカップらしい形が見えてくる。この瞬間は、本当に感動しますよ。「うわ、なんか、それっぽくなってきた!」って、ニヤニヤが止まらなくなります。ここで厚みが均一になるように意識するのがポイント。指先で壁の厚みを感じながら、薄いところはそっと、厚いところは少し力を入れて伸ばしていく。この繊細な作業が、また楽しいんです。
形を整えて、底を仕上げる。ここで油断すると…
筒状の壁がある程度の高さになったら、最後の仕上げに入ります。「シッピ」という糸でろくろから切り離す前に、形を整えていきます。飲み口の部分は、「なめし革」という濡らした革でそっと撫でてあげると、口当たりが滑らかになります。こういう一手間が、愛着に繋がるんですよね。
そして、器の外側の形を「コテ」や「カンナ」といった道具を使って整えていきます。腰の部分をちょっと膨らませてみたり、逆にシュッとシャープにしてみたり。デザインの自由度が高くて、一番個性が出るところかもしれません。
…で、ですよ。ここで油断すると、悲劇が起きます。私、やりました。いい感じに形が整って、「よし、完璧!」と思った瞬間、調子に乗ってコテを強く当てすぎたんです。ぐにゃり。さっきまで綺麗だった側面が、無残にも歪んでしまいました。「あーーーーーっ!!!」って、声にならない叫びが出ましたね。先生が「あー…うん、これも味だよ、味!」ってフォローしてくれたけど、内心は絶望です(笑)。そう、陶芸は最後まで油断大敵。完成だと思った瞬間が、一番危ないんです。この教訓、ぜひ覚えておいてください。
マグカップ作りで一番大事な「取っ手」をどうするか問題

マグカップに欠かせないもの、それはもちろん「取っ手」です。この取っ手をどうやって付けるか。実はこれ、結構大きな問題で、作り方もいくつかあるんです。初心者はどうするのがベストなのか、私の失敗談も交えてお話ししますね。これを読めば、取っ手で悲しい思いをすることはなくなるはず!
ろくろの上で一体成形?いや、初心者には無理ゲーです
たまに、ものすごく上手い人が、ろくろで挽いた筒から、にゅいーんと粘土を引っ張り出して、そのまま取っ手まで作ってしまうのを見ることがあります。いわゆる「一体成形」ですね。これ、めちゃくちゃカッコイイです。憧れます。
でも、はっきり言います。初心者がこれをやろうとするのは、無謀です。無理ゲーです。本体の形を整えるだけでもヒーヒー言ってるのに、そこからさらに繊細な力加減で取っ手を引き出すなんて、神業の領域。もし挑戦したら、99%の確率で本体を歪ませるか、取っ手がちぎれて終わります。私も「ちょっとやってみていいですか?」なんて無謀なことを言って、案の定、本体の飲み口あたりをぐにゃっとさせてしまい、先生に泣きつきました。まずは、基本に忠実に。カッコつけるのは、10年早いです(笑)。
あとから付ける「後付け」が現実的で楽しい選択肢
というわけで、初心者にとって最も現実的で、かつ一般的なのが「後付け」する方法です。ろくろで本体を作った後、別の粘土で取っ手パーツを作り、それを本体に接着するんですね。
この方法のいいところは、なんといってもデザインの自由度が高いこと。粘土を板状に伸ばして、好きな形の取っ手を切り出してもいいし、ひも状にした粘土を曲げて作ってもいい。丸っこい可愛い取っ手、四角いモダンな取っ手、ちょっと変わった形のアーティスティックな取っ手…あなたのセンスの見せ所です!
本体を作った時の緊張感から解放されて、粘土細工みたいに取っ手を作る時間は、すごくリラックスできて楽しいですよ。「どんな形にしようかな〜」なんて考えながら、コーヒーを飲む自分の姿を想像する。この時間こそ、マグカップ作りの醍醐味の一つかもしれません。本体作りで心が折れそうになっても、この取っ手作りで復活できるはずです。
私の失敗談。取っ手がポロリ…なんて悲劇を避けるには
さて、楽しい取っ手作りですが、ここにも落とし穴があります。それは「接着」です。本体と取っ手は、粘土が少し乾いた「半乾き」の状態でくっつけるのがベスト。そして、ただくっつけるだけじゃダメなんです。
接着する部分、つまり本体側と取っ手側の両方に、クシみたいな道具でギザギザの傷をつけます。そして、「ドベ」と呼ばれる、粘土を水で溶いたドロドロの接着剤を塗ってから、ぎゅっと圧着する。この「傷つけ」と「ドベ」をサボると、どうなるか。…ええ、想像通りです。焼いた後、取っ手がポロリ、なんていう悲劇が起こります。
私、やりましたよ、これ。初めて作った時、ちょっと傷つけが甘かったんでしょうね。焼き上がって、ウキウキでカップを持ち上げようとしたら、取っ手だけが指に残って、本体がガシャン!…と、いう悪夢を見ました(実際には窯出しの時点で取れてたらしいです)。先生に「あー、ここの接着が弱かったねぇ」と指摘され、もう泣くに泣けませんでした。皆さんは、絶対に、絶対に、接着面の傷つけとドベは念入りにやってくださいね!これは、先輩からの切実なお願いです。
形だけじゃない!色と質感で個性を爆発させる釉薬(ゆうやく)選び

形ができあがったら、陶芸の旅は終わり…ではありません!むしろ、ここからが第二のクライマックス。素焼きされた作品に「釉薬(ゆうやく)」というガラス質の薬品をかけて、本焼きをします。この釉薬選びが、また奥深くて、めちゃくちゃ楽しいんですよ。自分の作品に、命を吹き込む最終工程。どんな色にしようか、どんな手触りにしようか。あなたのセンスが光ります!
焼く前の色と全然違う!釉薬選びは化学実験のよう
陶芸工房に行くと、たくさんの釉薬の見本が並んでいます。透明なもの、白いもの、青いもの、緑のもの…。見ているだけでワクワクします。でも、ここで一つ、驚きの事実があります。釉薬って、かける前の液体の色と、焼いた後の色が、全然違うんです!
例えば、私が選んだ「織部(おりべ)」という緑色の釉薬。かける前の液体は、なんか、こう、くすんだネズミ色みたいな色なんです。「え、これがあの綺麗な緑になるの…?」って、半信半疑になりますよね。まるで化学実験みたいで、ドキドキします。他にも、ピンク色っぽい液体が焼くと深い青になったり、ただの白い液体が複雑な結晶模様になったり。
この「どうなるかわからない」感じが、たまらない魅力なんです。もちろん、見本があるので、ある程度の仕上がりは想像できます。でも、釉薬のかかり具合や窯の中の場所によって、一つとして同じ焼き上がりにはならない。この偶然性こそが、陶芸の面白さ。自分の作品がどんな表情を見せてくれるのか、窯出しの日までのお楽しみです。
ツルツル?マット?それともザラザラ?質感で印象は激変する
釉薬選びは、色だけではありません。「質感」も、ものすごく重要なポイントです。マグカップは直接口に触れるものだから、ここのこだわりは大事にしたいですよね。
大きく分けると、光沢のあるツルツルした質感の「透明釉」や「光沢釉」。そして、光沢がなく、しっとりとした手触りの「マット釉」。他にも、少しザラっとした土の風合いが残るような釉薬もあります。
例えば、同じ白い釉薬でも、ツルツルの白なら清潔感のあるモダンな印象に。マットな白なら、温かみのある、しっとりとした優しい印象になります。コーヒーの色を楽しみたいなら内側は透明釉や白系の釉薬がいいでしょうし、手触りを楽しみたいなら外側はマット釉にしてみる、なんていう組み合わせも素敵です。私は、口当たりを考えて飲み口のあたりはツルツルに、でも外側は土の温かみを感じたいからマットな質感に…なんて、延々と悩んでしまいました。この悩む時間も、また幸せなんですけどね。
「お任せ」もアリ。でも私は自分で選びたい派
陶芸体験によっては、「釉薬の色は工房にお任せします」というプランもあります。特に初心者で、何を選んでいいかわからない…という場合は、プロにお任せしてしまうのも一つの手です。工房の人が、その器の形に一番合うような素敵な色に仕上げてくれるはずです。それはそれで、福袋を開けるような楽しみがありますよね。
でも、私は断然「自分で選びたい派」です!だって、せっかくここまで苦労して形を作ったんですよ?最後の色の仕上げまで、自分で責任を持ちたいじゃないですか。たとえ、想像とちょっと違う色に焼き上がったとしても、それもまた「自分の選択の結果」。成功も失敗も、全部ひっくるめて自分の作品なんです。
「この色とこの質感を組み合わせたら、どうなるだろう?」って想像を膨らませて、見本とにらめっこする時間。これも、作品への愛情を深める大切なプロセスだと私は思います。もし釉薬選びで迷ったら、恥ずかしがらずに工房の先生に相談してみてください。「こういう雰囲気にしたいんですけど…」って伝えれば、きっと素敵な提案をしてくれますよ。
ついに完成!私のマグカップと過ごす日々

釉薬をかけてから、だいたい1ヶ月くらいでしょうか。窯で本焼きされ、冷まされる時間を経て、ついに完成の連絡が来ます。この間、もうソワソワしっぱなし。「うまく焼けてるかな…」「変な色になってないかな…」「取っ手、取れてないかな…」なんて、心配と期待で胸がいっぱいです。そして、いよいよ我が子との対面の時がやってきます。
窯出しの日のドキドキ感は、何物にも代えがたい
工房から「焼き上がりましたよ」の連絡が来た時の高揚感!私はもう、仕事を早退したいくらいの勢いでした(笑)。工房で、丁寧に梱包された箱を受け取る。ずっしりとした重みが、やけにリアルに感じられます。
家に帰って、テーブルの上で、そーっと箱を開ける瞬間。これはもう、試験の合格発表を見る時よりもドキドキします。新聞紙を一枚一枚めくっていくと…そこに、見覚えのある、でも全く新しい表情をした、私のマグカップがありました。
「うわぁ…!」
思わず声が出ました。あのネズミ色の液体だった織部釉は、深くて美しい、吸い込まれるような緑色になっていました。ツルツルとマット、悩んで塗り分けた質感も、想像以上にいい感じ。あの時、絶望した側面の歪みも、なんだか愛嬌のあるチャームポイントに見えるから不思議です。自分の手から生まれたものが、火の力を借りて、全く別の美しい存在に生まれ変わる。この感動は、本当に、何物にも代えがたい体験です。
ちょっと歪んでる?それこそが「味」なんだよね
完成したマグカップを、改めてじっくりと眺めてみます。うん、やっぱり、プロが作ったみたいにシンメトリーじゃない。飲み口も、完璧な円ではありません。光に透かすと、釉薬の濃淡がムラになっているのもわかります。
でも、それでいいんです。それがいいんです。このちょっとした歪みが、ろくろの上で粘土と格闘した証。この釉薬のムラが、私が慣れない手つきで釉薬をかけた証。全部、私の指が作った跡なんです。
完璧じゃないからこそ、世界にたった一つしかない。このカップが辿ってきた、土の塊からの道のりを、全部知っているのは私だけ。そう思うと、もう、愛おしくてたまらなくなります。お店で買った綺麗なカップも素敵だけど、この「不完全な完璧さ」は、自分で作ったものにしか宿らない特別な価値。これを「味」と呼ぶんですよね。やっと、その意味がわかった気がしました。
毎朝のコーヒーが、特別な儀式に変わった話
そして、初めてそのマグカップでコーヒーを飲む朝がやってきました。いつもと同じ豆、いつもと同じ淹れ方。でも、カップに注がれるコーヒーの音が、なんだかいつもより優しく聞こえます。
そっとカップを手に取ると、マットな質感がひんやりと心地いい。飲み口に口をつけると、なめし革で何度も撫でたおかげか、驚くほど滑らか。そして、コーヒーを一口。…なんだろう、いつもの3倍くらい美味しく感じるんです!もちろん、気のせいかもしれません(笑)。でも、このカップが生まれた物語を思い出しながら飲む一杯は、間違いなく、今までで一番豊かな味がしました。
それからというもの、毎朝のコーヒータイムは、ただの習慣から「特別な儀式」に変わりました。このカップを使うために、少しだけ早起きするようになったりして。たかがマグカップ一つ。でも、その一つが、私の日常を確実に、豊かに彩ってくれているんです。
まとめ 電動ろくろで作るマグカップは人生を豊かにする最高の趣味

さて、ここまで私の失敗だらけのマグカップ作り体験記にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。電動ろくろでのマグカップ作り、いかがでしたか?「やっぱり難しそう」と思いましたか?それとも「なんだか面白そう!」とワクワクしてくれましたか?
私がこの記事を通して一番伝えたかったこと。それは、電動ろくろでの器作りは、単なる「モノづくり」ではないということです。それは、土と、自分と、そして時間と向き合う、最高の「体験」なんです。
最初は言うことを聞かない土にイライラし、自分の不器用さに絶望するかもしれません。でも、その先には、自分の指先から形が生まれる感動が待っています。難しいからこそ、乗り越えた時の喜びは計り知れません。そして、最後に手にするのは、お店では絶対に買えない、あなたの時間と感情がギュッと詰まった、世界でたった一つの宝物です。
ちょっと歪んでたっていいじゃないですか。完璧じゃなくたっていいじゃないですか。その不完全さこそが、あなたの頑張りの証であり、何よりの「味」になるんですから。
もし、ほんの少しでも「やってみたいかも」という気持ちが芽生えたなら、ぜひ一歩、踏み出してみてください。スマホで「陶芸体験 〇〇(あなたの街の名前)」と検索する、その小さな勇気が、あなたの日常を今よりもっと豊かで、愛おしいものに変えてくれるはずです。あなたの物語が、ろくろの上から始まるのを、心から応援しています。