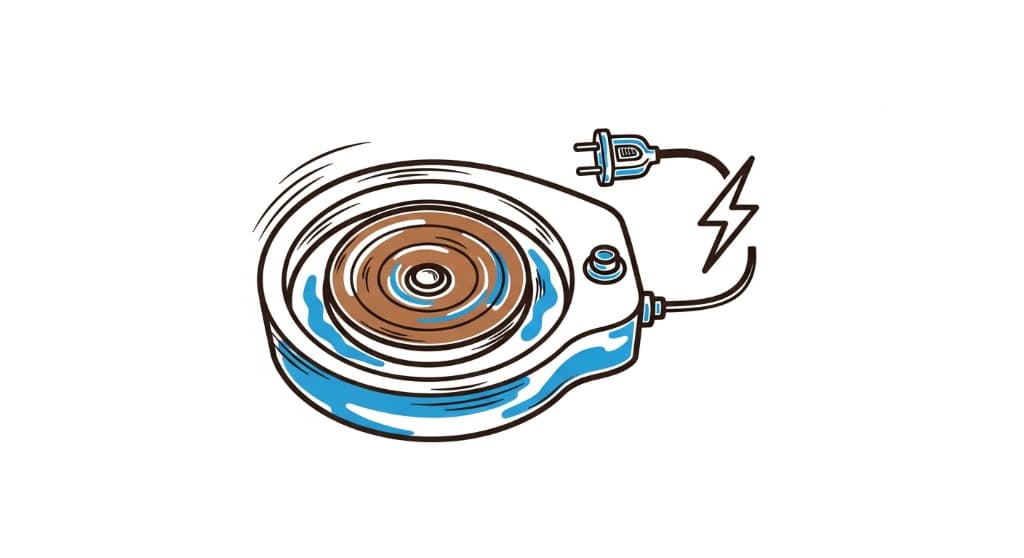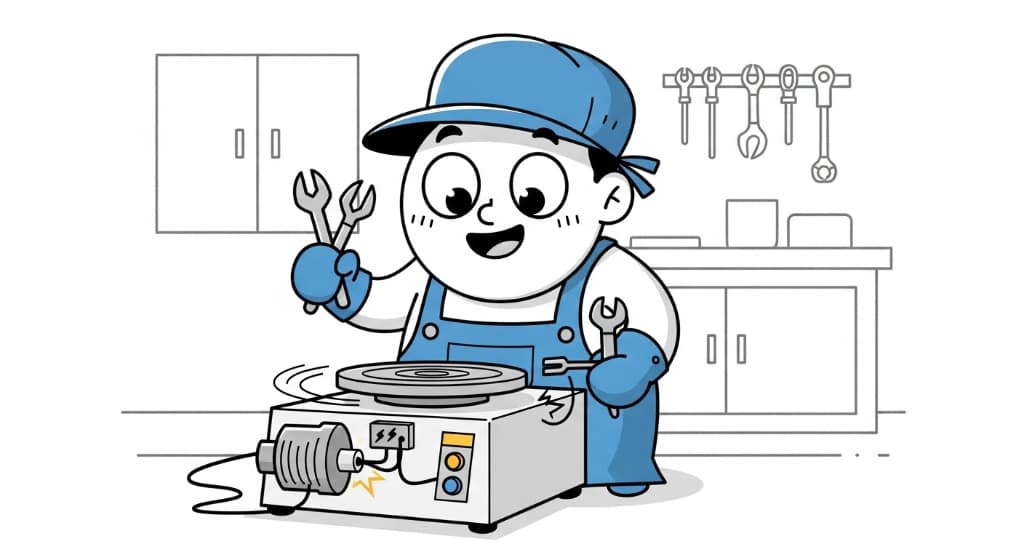電動ろくろの重さ、舐めてませんか?自宅陶芸の夢と現実、重さで失敗しないために
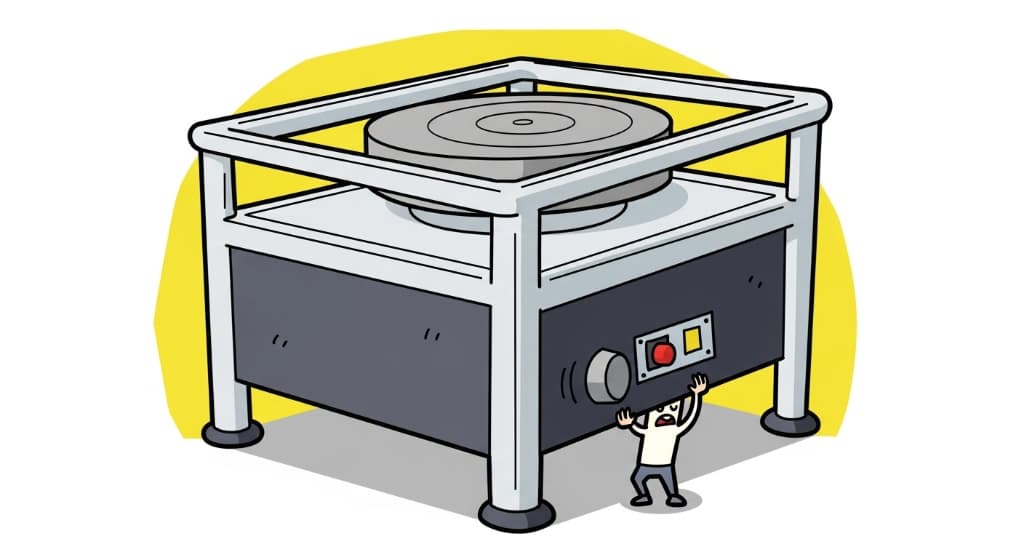
自宅で、好きな時に、好きなだけ土に触れる。あの粘土が指先でスルスルと形を変えていく、魔法のような時間…。考えただけでワクワクしますよね!私もその魅力にどっぷりハマった一人です。そして、多くの人が夢見るのが「電動ろくろの購入」ではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください!その夢、一歩間違えると悪夢に変わるかもしれないって知ってました?その運命の分かれ道が、何を隠そう「電動ろくろの重さ」なんです。実は電動ろくろって、軽いものは10kg台から、本格的なものだと40kgを超えるものまで、まさにピンからキリまで。この「重さ」を安易に考えて選んでしまうと、「重すぎて設置場所から動かせない…」「軽すぎて大きな作品が作れない!」なんていう悲劇が待っているんです。ええ、これは脅しじゃありません。私が実際に経験した、血と涙の教訓なんです…。
この記事では、そんな私の失敗談も包み隠さずお話ししながら、あなたの陶芸ライフを最高のものにするための「電動ろくろの重さ」の真実を、徹底的に、そして熱量マシマシで語り尽くします!この記事を読み終える頃には、あなたにピッタリの重さの相棒がどんなモデルなのか、ハッキリと見えているはず。後悔のない、最高の自宅陶芸デビューを飾りましょう!
電動ろくろの重さは「どう使いたいか」で選ぶのが絶対の正解です

いきなり核心からいきますが、電動ろくろの重さ選びで一番大切なのは、「あなたがどんな風に陶芸を楽しみたいか」を具体的にイメージすること。これに尽きます。ただ「軽い方が楽そう」とか「重い方が本格的っぽい」みたいなフワッとした理由で選ぶと、十中八九、後悔します。重さは、単なるスペックの数字じゃない。あなたの作陶スタイルそのものを決定づける、超重要な要素なんです。ここでは、卓上タイプと据え置きタイプ、それぞれの重さがもたらすメリットとデメリットを、私の体験も踏まえて生々しくお伝えしますね。
卓上タイプの「軽さ」は最高の魅力、でも注意点もてんこ盛り
まず、多くの方が最初に惹かれるのが、10kg〜20kg程度の「卓上タイプ」の電動ろくろじゃないでしょうか。わかります、その気持ち!「軽いし、コンパクトだし、使わない時はサッと片付けられそう♪」って思いますよね。実際、その手軽さは絶大なメリットです。アパートやマンション住まいで、常設のスペースが確保できない人にとっては、まさに救世主のような存在。テーブルの上に置いてすぐに始められるし、押し入れにだって収納できるかもしれません。
でもね、ここに大きな落とし穴があるんです。それは「作れる作品の大きさに限界がある」ということ。軽いということは、モーターのパワーもそれなりで、本体の安定感も低い場合が多いんです。お茶碗や湯呑み、小さな小鉢くらいなら、まあ問題なく作れるでしょう。でも、「よし、次はちょっと大きめのカレー皿に挑戦だ!」なんて意気込んで、粘土の塊をドスンと乗せた瞬間…どうなると思います?
モーターが「ウィィィィン…」と苦しそうな悲鳴をあげ、ろくろ本体がガタガタと揺れ始めるんです!もうね、土殺し(粘土の中心を出す作業)どころか、こっちが殺されそうになる(笑)。必死に力を込めても、ろくろ自体の軽さが災いして、粘土のパワーに負けちゃうんですよ。これ、本当にストレスが溜まります。「もっと大きなものを作りたいのに作れない!」このフラストレーションは、想像以上に創作意欲を削いでいきます。手軽さに惹かれて卓上タイプを選んだのに、結局「やりたいこと」ができなくて、陶芸から遠ざかってしまう…なんてことになったら、本末転倒だよね?
据え置きタイプの「重さ」は絶大な安定感の証
じゃあ、重い方はどうなの?って話ですよね。30kg〜40kg以上にもなる「据え置きタイプ」。もうね、ハッキリ言って、こいつは「動かすこと」を全く考えていません(笑)。一度設置したら、テコでも動かない。引越しの時なんて、業者さんが悲鳴をあげるレベルです。私も今のろくろを2階の作業部屋に運ぶ時、本気で腰が砕けるかと思いましたもん。
でも、その「重さ」こそが、最高の武器なんです。この圧倒的な重量がもたらす安定感たるや、もう異次元。5kg、いや10kgの粘土を乗せたってビクともしない。モーターは静かに、しかし力強く回り続け、あなたの力をダイレクトに粘土へと伝えてくれます。卓上タイプで感じていた、あの忌々しいブレや振動は一切なし。自分の技術だけに集中できるこの環境…最高ですよ、本当に。
大皿や大きな壺など、ダイナミックな作品に挑戦したいなら、もう据え置きタイプ一択です。重さは、そのまま作れる作品の可能性の広さに直結します。確かに、設置場所は取るし、値段も高い。気軽に「ちょっと始めてみようかな」で手を出せるものではないかもしれません。でも、本気で、長く陶芸と付き合っていきたいと考えるなら、この「重さ」は、何物にも代えがたい「投資」になるんです。
私が最初に重さで大失敗した、恥ずかしい話
ええ、何を隠そう、私も最初は見事に失敗しました。陶芸教室に通って、大きな作品を作る楽しさに目覚めたはずなのに、いざ自宅用に買う段になって、「まあ、最初は手軽な方がいいよね…」なんて日和ってしまったんです。選んだのは、ネットでそこそこ評判の良かった15kgくらいの卓上タイプ。届いた時は「おお!コンパクト!これなら邪魔にならない!」なんて喜んでました。
最初のうちは、教室の復習でお茶碗とかを作って、それなりに満足してたんです。でも、欲が出てくるじゃないですか、人間だもの。「よし、あの時作ったみたいな、パスタが映えそうな大きなお皿を作るぞ!」と意気込んで、粘土をこねて、いざ、ろくろへ!…結果は、先ほどお話しした通りです。ブレる、唸る、止まりそうになる。中心もまともに出せず、粘土は無残な姿に。もうね、悔しいやら情けないやらで…。
結局、その卓上ろくろは数ヶ月でお蔵入り。フリマアプリで寂しく売られていきました。そして、清水の舞台から飛び降りる覚悟で、今の40kg級の相棒(据え置きタイプ)を迎え入れたんです。あの絶望的な重さの搬入作業を乗り越えた先に待っていたのは、ストレスフリーな作陶天国でした。最初からこっちにしておけば、無駄な出費も、あの悔しい思いもしなくて済んだのに…!だからこそ、声を大にして言いたいんです。重さ選びは、本当に、本当に慎重に!って。
具体的に電動ろくろの重さってどれくらい?主要メーカーで比べてみよう

「重さが大事なのはわかったけど、じゃあ具体的にどのメーカーのどのモデルがどれくらいの重さなの?」と思いますよね。そりゃそうだ。ここからは、国内で人気の主要な電動ろくろメーカーをピックアップして、それぞれの特徴と重さのラインナップを、私の独断と偏見も交えながらご紹介していきます。カタログスペックだけじゃわからない、リアルな使用感なんかもお伝えできればなと。あくまで一個人の意見として、参考にしてみてくださいね。
シンポ(NIDEC-SHIMPO)はまさに王道!重さもモデルも超幅広い
陶芸やってる人で、この「シンポ」を知らない人はいないんじゃないかな?ってくらい、超メジャーなメーカーです。日本電産シンポ株式会社、今は「ニデック」って名前の方が通りがいいのかな。多くの陶芸教室で採用されているのも、このシンポのろくろです。プロからの信頼も厚い、まさに「王道中の王道」。
シンポのすごいところは、そのラインナップの広さ。軽い卓上タイプから、プロ仕様の超重量級まで、本当に幅広いニーズに応えてくれます。例えば、初心者にも人気の卓上タイプ「RK-5T」は、重さ約12kg。手軽さはピカイチですが、先述の通り、パワーはそれなり。趣味の範囲で小物を楽しむなら、という感じでしょうか。
一方で、私が喉から手が出るほど欲しかった(そして買った)のが、据え置きタイプの「RK-3D」や「RK-2XA」といったモデル。これらは重さが40kg前後あります。重い!だけど、その分モーターのパワーも静音性も段違い。粘土をしっかり受け止めてくれる懐の深さがあります。価格はそれなりにしますが、「本気でやるならシンポの据え置き」というのは、多くの陶芸家にとっての共通認識かもしれません。迷ったらシンポ、というくらい安定感のある選択肢ですね。
グット電機(GUT)はコンパクトで軽いモデルに強い味方
次に紹介したいのが、「グット電機」。シンポに比べると少しマニアックかもしれませんが、こちらも根強いファンを持つ国内メーカーです。特に、グット電機はコンパクトで軽量なモデルに定評があります。
代表的なモデル「らくらく2型」は、重さ約23kg。卓上タイプと据え置きタイプの中間くらいのイメージでしょうか。脚が取り外せるモデルもあって、収納性にも配慮されているのが嬉しいポイント。23kgというと、男性ならなんとか一人で運べるかな?くらいの重さですよね。この「絶妙な重さ」が魅力なんです。卓上タイプほどの非力さはないけれど、本格的な据え置きタイプほど重くて動かせないわけでもない。
「大きな作品もそこそこ作りたいけど、常設はちょっと厳しい…」という、わがままな(失礼!)願いを叶えてくれる可能性を秘めたメーカーです。デザインもちょっとレトロで可愛らしいものが多くて、個人的には結構好き。パワーと携帯性のバランスを重視するなら、グット電機はかなり有力な候補になるんじゃないでしょうか。
その他のメーカーと中古品という選択肢も忘れずに
もちろん、国内には他にも素晴らしいろくろを作るメーカーがあります。例えば「東海工業」なんかも、プロ向けの堅牢なろくろを作っていることで知られています。ただ、ちょっと情報が少なかったり、手に入れにくかったりすることもあるので、初心者の方が最初に選ぶには少しハードルが高いかもしれません。
そして、もう一つの選択肢が「中古品」。これがね、結構狙い目だったりするんです。ヤフオクやメルカリ、専門の中古陶芸機材店などを覗いてみると、憧れのシンポの据え置きタイプが、驚くような価格で出品されていることがあります。私も今のろくろを買う時、かなり中古市場をリサーチしました。
ただし、注意点も。電動ろくろは精密機械です。モーターの状態やベルトの消耗具合、ターンテーブルのブレなど、素人目には判断が難しい部分がたくさんあります。特に個人間の取引は「ノークレーム・ノーリターン」が基本。安さに釣られて飛びついたら、すぐに壊れて修理代の方が高くついた…なんてことになったら目も当てられません。もし中古を狙うなら、信頼できる出品者からか、整備済みのものを販売している専門店から購入することを強く、強く、お勧めします!
重さだけじゃない!電動ろくろ選びで本当に見なきゃいけないポイント
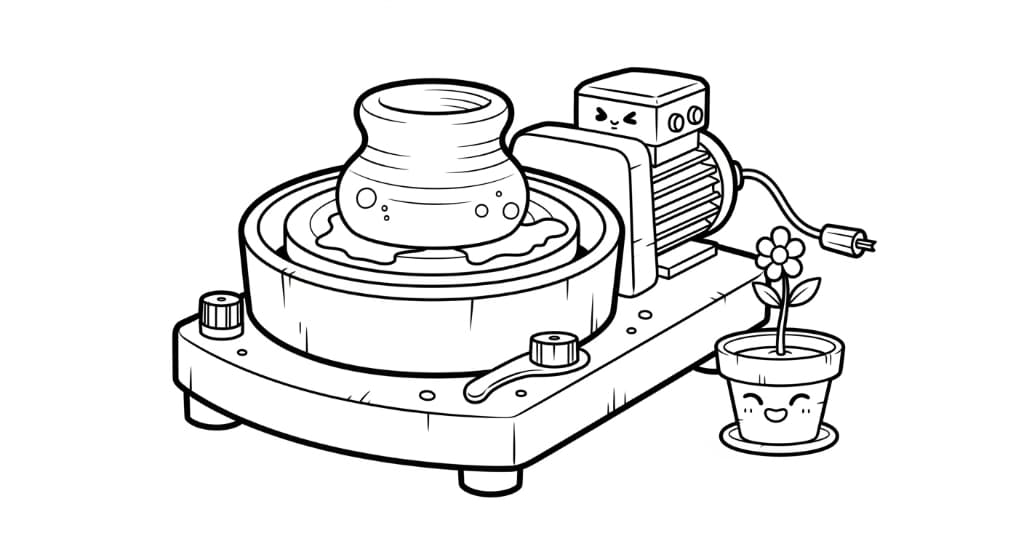
ここまで散々「重さ!重さが大事!」と叫んできましたが、もちろん、見るべきポイントは重さだけじゃありません。むしろ、重さとセットで考えなきゃいけない、もっと重要な要素がいくつかあるんです。ここを見逃すと、せっかく重さをクリアしたのに「なんか使いにくい…」という、また別の後悔が生まれてしまいます。ここでは、私が実際に使ってみて「これは絶対にチェックすべき!」と痛感したポイントを、熱を込めてお伝えします。
モーターのパワー(トルク)は粘土の量に直結する超重要項目
はい、出ました。最重要項目です。モーターの「パワー」、専門用語で言うと「トルク」ですね。これが弱いと、はっきり言って話になりません。重さとパワーは比例する傾向にありますが、必ずしもそうとは限らないので、スペックをしっかり確認する必要があります。
パワーが弱いとどうなるか。それはもう、私の失敗談で語った通りです。ある程度の量の粘土を乗せて、グッと力を加えた瞬間に、回転が遅くなったり、最悪の場合止まってしまったりします。これ、本当にイライラするんですよ!「うおお、今だ!中心を出すぞ!」って一番集中したい時に、ろくろが「無理です…」ってギブアップしちゃうんですから。
カタログにはよく「搭載粘土量〇kg」みたいに書かれていますが、正直、あれは最大値なのであまりアテになりません。書かれている量の半分くらいの粘土を、ストレスなく扱えるかどうか、が一つの目安かなと私は思っています。大きな作品を作りたいなら、モーターの出力(W数)が大きいモデルを選ぶのが絶対条件。重さと合わせて、このパワーだけは絶対に妥協しないでください!
ドベ受け(泥受け)の形状は掃除のしやすさに直結する!マジで!
地味!地味なポイントだって思いました?いやいや、とんでもない。この「ドベ受け」の使い勝手が、日々の陶芸ライフの快適さを左右すると言っても過言ではありません。ドベ受けとは、ろくろを回した時に飛び散る粘土や水(これを「ドベ」と言います)を受け止めてくれるお皿のこと。
作陶が終われば、当然、このドベ受けを掃除することになります。これがね、モデルによって掃除のしやすさが天と地ほど違うんです。一体型で取り外しにくいものもあれば、パカっと二つに分割できて、シンクでサッと洗い流せるものもあります。私の使っているシンポのろくろは、この分割タイプなんですが、もうこれが最高に楽ちん。作陶後のあの面倒な片付けが、劇的にスムーズになりました。
考えてみてください。毎回、粘土でドロドロになった重たいパーツを、狭いシンクで四苦八苦しながら洗う光景を…。想像しただけでウンザリしませんか?この「掃除のしやすさ」は、創作活動を継続する上でのモチベーションに、地味〜に、でも確実に影響してきます。「あー、またあの掃除か…」と思うと、ろくろに向かう足も重くなっちゃいますからね。本当に、ここは購入前にしっかりチェックしてほしい!
音の静かさも見逃せない!ご近所トラブルは絶対に避けたいよね
特にマンションやアパートにお住まいの方にとっては、死活問題になりかねないのが「音」です。電動ろくろは、モーターでターンテーブルを回す機械。当然、作動音が出ます。この音が、思った以上に響くことがあるんです。
古いモデルや安価なモデルだと、「ウィーン」「ゴーーー」といった、結構な騒音を出すものもあります。昼間ならまだしも、仕事から帰ってきて夜に作陶したい、なんて場合には、ご近所迷惑になってしまう可能性大。壁の薄いアパートだったら、もう完全にアウトでしょう。
最近のモデル、特にシンポなどが採用している「ブラシレスモーター」や「ダイレクトドライブ方式」のものは、驚くほど静かです。本当に「え、回ってるの?」って思うくらい。私が据え置きタイプに買い替えて感動したことの一つが、この静音性でした。夜中でも、気兼ねなく作陶に没頭できる。この安心感は、何物にも代えがたいですよ。集合住宅で陶芸を楽しみたいなら、「静音性」は必須条件としてリストアップしておくべきです。
意外と忘れがち?回転方向と速度調整の機能もチェック
最後に、ちょっとマニアックだけど意外と大事なポイントを二つ。一つは「ターンテーブルの回転方向」。右利きの場合、ろくろは反時計回りに回すのが一般的です。でも、中には左利きの方や、特定の技法で逆回転させたい、という人もいます。ほとんどのろくろはスイッチで回転方向を切り替えられますが、ごく稀に一方向にしか回らないモデルも存在します。まあ、ほとんどの人は大丈夫だと思いますが、念のため確認しておくと安心です。
もう一つは「速度調整」。足で踏むペダルで回転速度をコントロールするのが基本ですが、このペダルの反応の良さや、最低速度と最高速度の幅も、使い勝手に影響します。特に、繊細な作業をする時は、ごくごく低速で安定して回ってほしいもの。逆に、土殺しの時にはパワフルに高速回転してほしい。このあたりの操作感は、実際に触ってみないとわからない部分も大きいですが、レビューなどを参考に「速度調整がスムーズか」という点も見ておくと、より良い選択ができるはずです。
電動ろくろの重さと格闘!リアルな設置と片付けを想像してみよう

さあ、理想のろくろのイメージが固まってきた頃でしょうか。でも、まだ終わりじゃありません。最後に、購入後の「現実」について、しっかりシミュレーションしておく必要があります。そう、あの「重さ」とのリアルな格闘です。どんなに素晴らしい性能のろくろでも、設置できなきゃただの重いオブジェ。片付けが面倒で使わなくなっても意味がない。ここでは、見落としがちな設置と片付けのリアルについて、私の血と汗の経験からお話しします。
どこに置く?床の耐荷重と神聖なる作業スペースの確保
まず、どこに置きますか?その電動ろくろ。卓上タイプならまだしも、30kg、40kgを超える据え置きタイプを置くとなると、話は簡単じゃありません。特に、木造アパートの2階とかだと、床が重さに耐えられるのか?という問題が出てきます。40kgのろくろに、10kgの粘土、そして60kgの自分…合計110kgが一点に集中するわけです。床、抜けたりしませんかね?大丈夫?心配な方は、大家さんや管理会社に確認した方がいいかもしれません。
そして、スペースの問題。電動ろくろを置くだけじゃなく、自分が座る椅子、粘土を置く場所、水を入れたバケツ、道具を並べる台…と、作陶には意外と広いスペースが必要になります。さらに、粘土は驚くほど飛び散ります!壁や床に養生シートを貼ることも考えると、最低でも2畳くらいの「汚れてもいい専用スペース」を確保したいところ。この「聖域」を自宅に確保できるかどうかが、快適な陶芸ライフの第一歩です。
運搬はマジで地獄?一人で運べる重さの限界を知っておこう
購入したろくろは、誰が玄関から設置場所まで運びますか?…そう、あなたです。宅配便のお兄さんは、玄関までしか運んでくれません。私の40kgの相棒が届いた日、私は一人で途方に暮れました。「これ、2階までどうやって運ぶんだ…?」と。結局、毛布で包んで引きずり、一段一段、休み休み、半泣きになりながら運び上げました。腰が爆発するかと思った。本当に。
一般的に、成人男性が一人で安全に運べるのは20kg〜25kgくらいが限界じゃないでしょうか。女性ならもっと軽い重さが目安になるでしょう。それ以上の重さのろくろを選ぶなら、必ず手伝ってくれる人を確保してください。マジで。この運搬問題をクリアできるかどうかも、モデル選びの重要な判断基準になります。「重さ」は、購入時の一回だけじゃなく、引越しや模様替えのたびに、あなたの前に立ちはだかる壁になることを忘れちゃいけません。
毎回の片付けを考えると…やっぱり軽さは正義かもしれない
「本気なら据え置き!」とさんざん言ってきましたが、ここで少しだけ卓上タイプの肩を持ちたいと思います。それは「毎回の片付け」を考えた時です。据え置きタイプは、一度置いたら動かせません。掃除は、その場でやるしかない。でも、卓上タイプならどうでしょう。作陶が終わったら、本体ごとシンクの近くやベランダに持っていって、豪快に水洗い!なんてことも可能です(もちろん、モーター部分は濡らさないように!)。
この「片付けの手軽さ」は、特にズボラな私のような人間にとっては、かなりの魅力です。毎日使うとなると、この一手間二手間の差が、だんだん大きなストレスになってくる可能性も否定できません。「大きな作品は作れないけど、手軽に楽しんで、片付けも楽ちんな方がいいな」というライフスタイルも、もちろんアリ!なんです。最終的に、どちらのメリットを取るか。あなたの陶芸に求めるものが、ここで問われるわけですね。うーん、悩ましい!
まとめ 電動ろくろの重さは、あなたの陶芸愛の重さかもしれない

さて、ここまで電動ろくろの「重さ」について、これでもかというくらい熱く語ってきました。もうお腹いっぱいですかね?(笑)
結論として、電動ろくろの重さは、軽い卓上タイプで10kg台から、本格的な据え置きタイプで40kg超までと幅広く、その選択は「あなたがどんな陶芸をしたいか」に直結します。手軽に小物を楽しみたい、収納場所を確保したいなら「軽さ」は正義です。一方で、大きな作品に挑戦し、ストレスフリーな作陶環境を求めるなら、動かせないほどの「重さ」がもたらす安定感こそが、最高のパートナーになるでしょう。
重さ以外にも、モーターのパワー、掃除のしやすいドベ受け、静音性など、チェックすべきポイントはたくさんあります。そして何より、購入後の設置や運搬、日々の片付けといったリアルな現実を想像することが、後悔しないろくろ選びの鍵を握っています。私の失敗談が、あなたの賢い選択の助けになれば、こんなに嬉しいことはありません。
電動ろくろは、決して安い買い物ではありません。重いし、場所も取る。正直、面倒なことも多いです。でも、その重い機械と格闘し、泥だらけになりながら、自分の手から新しい形が生まれる瞬間の喜びは、何物にも代えがたいものです。もしかしたら、電動ろくろの「重さ」とは、あなたの陶芸に対する「愛の重さ」なのかもしれませんね。この記事を読んで、あなたの心に火が灯ったなら、ぜひその熱い想いを信じて、最高の相棒探しの旅に出てください。泥んこまみれの、素晴らしい日々があなたを待っていますよ!