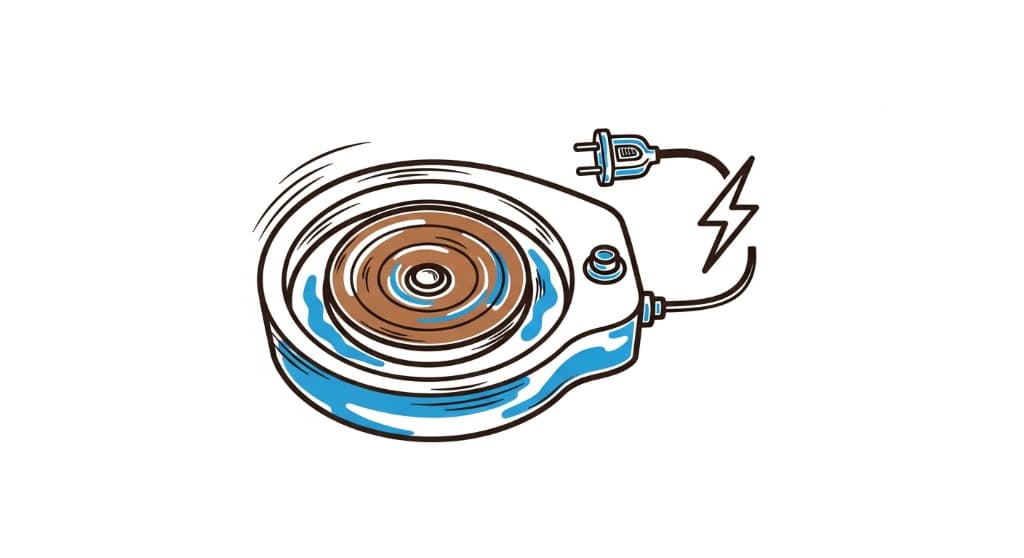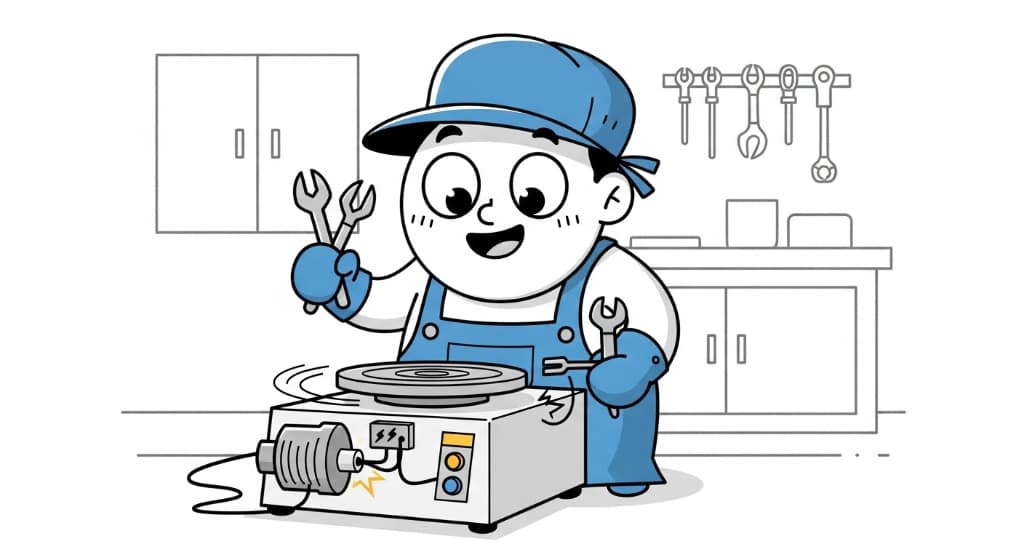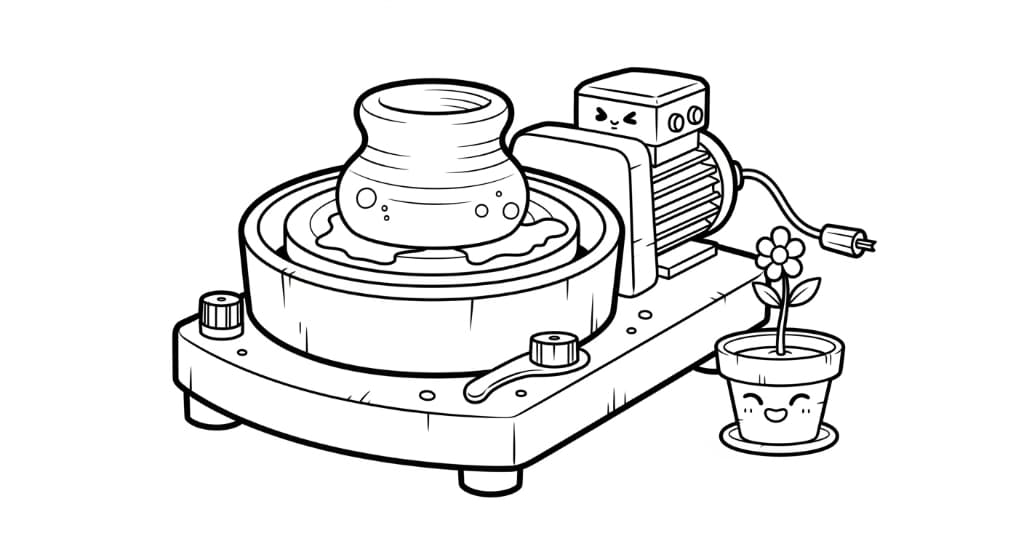もう失敗しない!電動ろくろの基本を完全マスターして、自分だけの器を作る方法
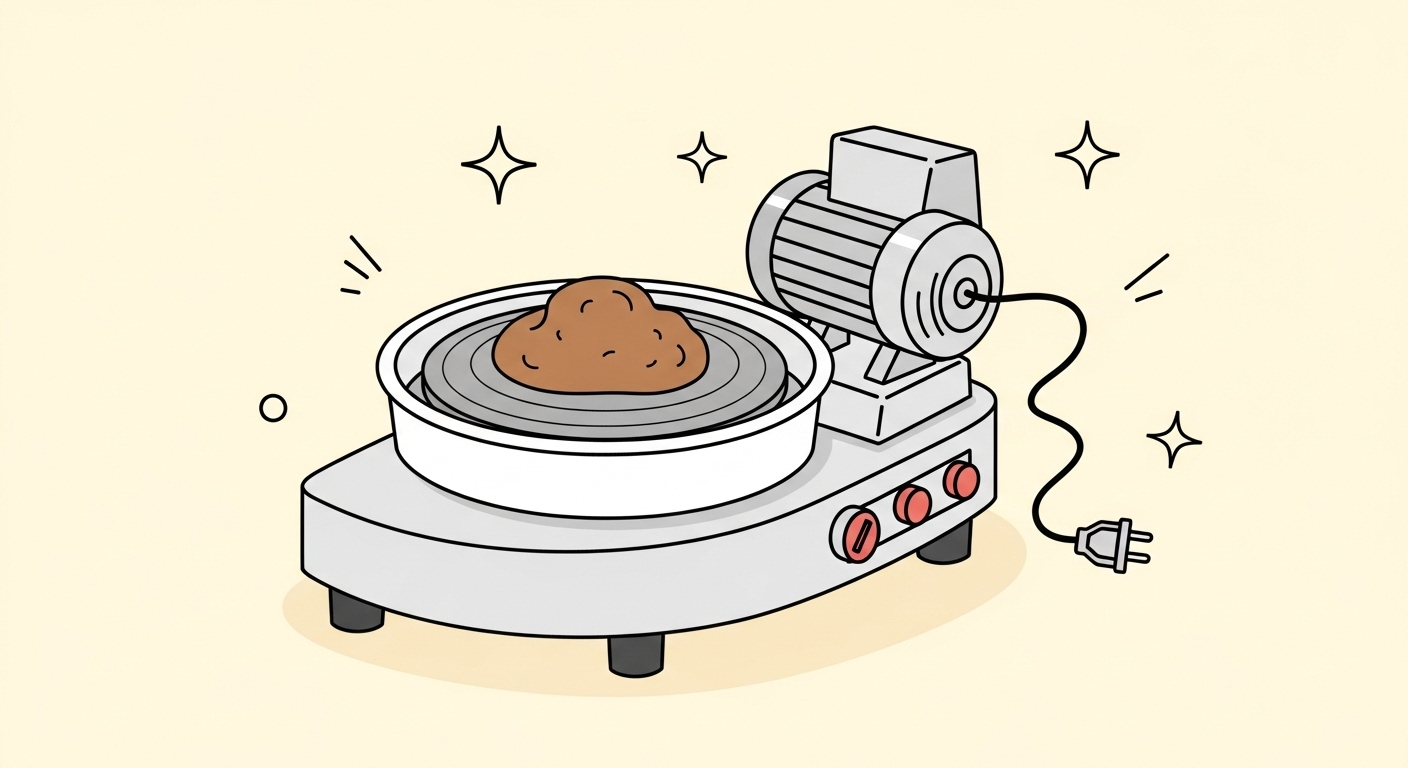
「いつか自分の手で、オリジナルの器を作ってみたい…」
そう思いながら、陶芸教室のホームページを眺めては閉じ、眺めては閉じ…なんてことを繰り返していませんか?わかります、すっごくわかります。特に「電動ろくろ」って、なんだかプロっぽくて、難しそうに感じますよね。くるくる回る土のかたまりを前に、自分だけ無様にぐちゃぐちゃにしてしまったらどうしよう、なんて不安になったり。
でも、安心してください。断言します。電動ろくろは、いくつかの「基本」さえしっかり押さえれば、驚くほど素直にあなたの言うことを聞いてくれる、最高の相棒になるんです。かくいう私も、最初は粘土をろくろの中心に置くことすらできず、遠心力で粘土をアトリエの壁に飛ばした経験者です(笑)。でも、そんな私でも、今では自分で作ったいびつな湯呑みで毎朝お茶を飲むのが、何よりの幸せになりました。
この記事では、小難しい理屈は一旦横に置いておいて、私がたくさんの失敗から学んだ「これだけは!」という電動ろくろの基本を、余すところなくお伝えします。この記事を読み終える頃には、あなたの「難しそう」という不安は「早く土に触りたい!」というワクワクに変わっているはず。そして、あなただけの愛しい器を生み出す、魔法のような時間への第一歩を踏み出せることをお約束しますよ。さあ、一緒に土と遊ぶ準備を始めましょう!
電動ろくろの成功は「土殺し」と「中心出し」が9割を占める

いきなり核心から言いますね。電動ろくろって、たくさんの工程があるように見えて、実は成功するかどうかの9割は、最初の「土殺し」と「中心出し」で決まってしまうんです。本当に、これだけ。これさえ乗り越えれば、あとはもうウィニングランみたいなもの、と私は本気で思っています。
家の建築で例えるなら、土殺しと中心出しは「基礎工事」。この基礎がグラグラだったら、いくら素敵な壁や屋根を乗せようとしても、すぐに傾いて崩れてしまいますよね。それと全く同じなんです。この最初の2つのステップを丁寧に行うことが、美しい器への唯一の近道であり、最大のコツなんですよ。
なぜ「土殺し」と「中心出し」がそんなに重要なのか
「土殺し」って、なんだか物騒な名前ですよね。私も最初は「え?殺しちゃうの?」ってびっくりしました。これは、粘土の中に含まれる空気の粒や、硬さのムラを均一にする作業のこと。粘土の粒子を整えて、ろくろで回した時に素直に伸びてくれるように「粘土のご機嫌をとる」作業、みたいなイメージです。これをサボると、後で器を薄くしていく段階で、空気の穴が「ブツッ」と表面に出てきたり、硬い部分だけが言うことを聞かずに形が歪んだりする原因になります。もう、最悪です。
そして「中心出し」。これは、ろくろの回転の中心と、粘土の中心をぴったり合わせる作業です。これができていないと、ろくろを回した瞬間に粘土がぐわんぐわんと暴れ出します。まるで、言うことを聞かないやんちゃなペットみたいに。この状態で無理やり形を作ろうとしても、遠心力に負けてぐにゃり。ああ、無情。中心がピタッと決まった時の、あの手に吸い付くような一体感、ぶれずに静かに回り続ける粘土の姿は、本当に美しいんですよ。この「静寂」を手に入れることこそが、電動ろくろの第一関門なんです。
私が最初にぶち当たった巨大な壁、ぐにゃぐにゃ粘土との格闘記
私が初めて陶芸体験で電動ろくろの前に座った日のこと、今でも鮮明に思い出せます。先生が「はい、じゃあ中心を出してみて」と、いとも簡単にやってみせるのを見て、「なんだ、簡単そうじゃん」なんて、完全にナメていました。ごめんなさい。
いざ自分の番。ろくろの上に粘土をドン!と置いて、スイッチオン。その瞬間、粘土は私の手を振り払うように暴れ始めました。「え?ちょ、待って!」と慌てて押さえつけようとするんですが、押さえれば押さえるほど、粘土は奇妙な形に歪んでいくんです。タコみたいになったり、富士山みたいになったり、最終的には遠心力に負けてべちゃっと潰れてしまいました。もう、プライドも何もあったもんじゃありません。周りの人がスイスイ形を作っているように見えて、焦りと悔しさで泣きそうになったのを覚えています。「私、才能ないのかも…」って本気で落ち込みました。
でも、先生が教えてくれたのは「力じゃない、土の声を聞くんだよ」という言葉。力を抜いて、手のひら全体で土を包み込むように、ろくろの回転に身を任せる。すると、さっきまで暴れていた粘土が、ふっと静かになる瞬間があるんです。あの感覚!「あ、これか!」と。まさに、土と対話できた瞬間でした。この体験があったからこそ、私は「中心出し」の重要性を、誰よりも熱く語れるのかもしれません。
始める前に知っておきたい!電動ろくろの基本の「き」

さあ、いよいよ実践!…と、その前に。戦場(アトリエ)に赴く前の準備はとっても大事です。何事も形から入るの、悪くないと思います。最低限必要な道具や、心構え、そして服装。これを最初に知っておくだけで、当日の余裕がまったく違ってきますからね。焦ってあたふたしないためにも、ここでしっかりインプットしておきましょう。
どんな道具が必要?最低限これだけは揃えたい7つ道具
陶芸の道具って、見ているだけでもワクワクしますよね。いろんな種類がありますが、最初から全部揃える必要は全くありません。まずは基本の道具たちと仲良くなることから始めましょう。私が「これさえあれば、とりあえず形になる!」と思う、最低限の7つ道具をご紹介しますね。
シッピ:細い針金に持ち手がついた道具です。完成した作品をろくろから切り離す時に使います。これが無いと、せっかく作った器がろくろから剥がせず、悲劇が起きます。地味だけど超重要。
なめし皮:器の口当たりを滑らかにするための皮です。薄くスライスされた鹿の皮が一般的。これで口元を「きゅっ」と撫でるだけで、作品が一気にプロっぽくなります。魔法のアイテム。
針(ハリ):その名の通り、粘土用の針です。器の縁の高さを揃えるために印をつけたり、不要な粘土を切り取ったり。細かい作業の相棒です。
弓(ゆみ):U字型の金属にワイヤーが張られた道具。器の側面や底の余分な粘土を削ぎ落とすのに使います。シュッ、シュッと粘土が削れていく感覚は、なかなか爽快ですよ。
コテ:木や金属でできた、いろんな形のヘラです。器の表面を滑らかにしたり、カーブを整えたりするのに使います。自分の手の延長のような感覚で使えるようになると、表現の幅がぐっと広がります。
スポンジ:作品に水を与えたり、逆に余分な水分を吸い取ったり、表面を滑らかにしたりと、大活躍の万能選手。普通の食器洗い用スポンジとは違う、きめ細かい陶芸用のものが使いやすいです。
桶:水を入れておくためのバケツです。ろくろ作業中は常に手を濡らしておく必要があるので、すぐ手の届くところに置いておきましょう。泥水でどんどん濁っていきますが、それもまた味です。
服装と心構え。汚れてもいい服と「失敗は当たり前」のマインドセット
まず服装ですが、これはもう声を大にして言いたい。絶対に汚れてもいい服で来てください! できれば爪も短く切っておきましょう。
お洒落なカフェに行くような気分で、お気に入りの白いブラウスなんか着ていったら、100%後悔します。泥はねは、あなたが思っている以上に広範囲に、そして絶妙な場所に飛びますから。「え、なんでこんなところに?」って場所に泥がついてるのが、陶芸あるあるです。ジャージや着古したTシャツ、エプロン持参が最強です。あと、ズボンも汚れるので、下半身も油断しないように。靴も、泥がついても笑って許せるものを選びましょう。
そして、服装と同じくらい大事なのが「心構え」です。それは「最初からうまくいくわけがない。失敗は当たり前!」というマインドセットを持つこと。
電動ろくろは、本当に繊細です。その日の自分の体調や、心のありようが、そのまま土に伝わります。焦っていたり、イライラしていたりすると、不思議なくらい土は言うことを聞いてくれません。
だから、ぐにゃっとなっても、穴が開いても、「あーあ、やっちゃった!次いこ、次!」くらいの軽い気持ちでいることが、上達への一番の近道なんです。完璧な器を1個作ることより、ぐちゃぐちゃの粘土を10個作る方が、よっぽど学びがあります。失敗作は、また粘土に戻せばいいだけ。失うものは何もありません。だから、どうか失敗を恐れずに、大胆に土と戯れてみてください。
いよいよ実践!電動ろくろの基本ステップを徹底解説

さて、準備は整いましたか?ここからは、いよいよ電動ろくろを使った作陶の基本的な流れを、ステップバイステップで見ていきましょう。言葉で説明すると少し長く感じるかもしれませんが、一つ一つの作業は繋がっています。焦らず、私の失敗談も思い出しながら(笑)、イメージトレーニングしてみてください。大丈夫、あなたならできます!
ステップ1「土殺し(土練り)」粘土のキホンは均一にすること
まず、ろくろの中心に粘土を置きます。量は、初心者のうちは湯呑みやお茶碗サイズが作りやすいので、500g〜800gくらいがおすすめです。
スイッチを入れて、ろくろを回転させます。最初はゆっくりで大丈夫。両手に水をたっぷりつけて、粘土を濡らします。ここでの目的は、先ほども説明した通り、粘土の硬さを均一にすること。円錐形に高く伸ばしていったり、またそれを上からぐーっと押さえつけて平たくしたり、この上下運動を数回繰り返します。これを「菊練り」ならぬ「ろくろ練り」なんて言ったりもしますね。
ポイントは、常に両手で、左右対称に力を加えること。そして、力を込めるだけでなく、粘土がどう動きたがっているかを感じることです。最初はただの力仕事に感じるかもしれませんが、慣れてくると、だんだん粘土が滑らかになって、手に馴染んでくるのがわかるようになります。「ああ、君も準備ができてきたんだね」と、粘土と会話するような気持ちで、じっくり時間をかけてあげてください。
ステップ2「中心出し(芯出し)」ろくろとの一体感を得る最重要ポイント
土殺しが終わったら、いよいよ最重要関門「中心出し」です。粘土を半球状に整えたら、左手を粘土の左側面に「壁」のように添え、右手で上から斜め下にぐっと押さえつけていきます。この時、肘を太ももや体に固定すると、腕がぶれにくくなります。
ろくろは時計回りに回っていると仮定すると、粘土はあなたの左手にぐいぐいとぶつかってこようとします。その力に負けないように、でも力みすぎずに、壁となった左手でそっと受け止めてあげる。右手は、粘土を「中心へ、中心へ」と導いてあげるイメージです。
最初は間違いなく、ぐわんぐわんとブレます。100%ブレます。でも、そこで諦めないでください。一度ろくろを止めて、形を整え直して、また挑戦。これを繰り返していると、ある瞬間、ふっとブレが収まり、粘土が手のひらの中心で「すんっ」と静かに回り始める時が来ます。これです!この感覚!この「ろくろと粘土と自分が一体になった」ような感覚を掴むことができれば、もうあなたは電動ろくろマスターへの道を半分以上進んだと言っても過言ではありません。この静寂の瞬間の感動を、ぜひ味わってほしいです。
ステップ3「穴あけ」器の深さを決める運命の一瞬
中心が出たら、いよいよ器の内部を作っていきます。まず、両手の親指を揃えて、粘土の中心にゆっくりと、垂直に突き刺していきます。まるで、柔らかいバターに指を入れるような感覚です。焦って突き刺すと、中心がズレてまた粘土が暴れ出すので、あくまでゆっくりと。
ここで重要なのが、器の底になる部分の厚みを残しておくこと。指を底まで貫通させてしまったら、ただの穴あき粘土になってしまいますからね(私はやりました)。指をある程度の深さまで入れたら、一度止めて、針を刺して底の厚さを確認します。だいたい1cmくらいの厚みが残っていれば安心です。
この「穴あけ」は、器の深さを決める、まさに運命の一瞬。ここで開けた穴が、あなたの作る器のすべての始まりになります。深くすれば背の高い湯呑みに、浅ければ平たいお皿に繋がっていきます。どんな器にしたいか、少しだけ想像しながら指を進めてみてください。
ステップ4「筒状に引き上げる」焦らずゆっくり、土の声を聞きながら
穴が開いたら、その穴を少しずつ広げていき、そこから器の壁を上に引き上げていきます。器の内側に左手の指を、外側に右手の指を添えて、粘土をサンドイッチするように挟みます。そして、その挟んだままの状態で、ゆっくりと、本当にゆっくりと、下から上へ指を移動させていきます。
ここでのコツは、内側の指と外側の指の高さを常に同じに保つこと、そして引き上げるスピードを一定にすることです。どちらかの指が先行したり、途中でスピードが変わったりすると、壁の厚さがまだらになったり、形が歪んだりする原因になります。
最初は、ただの分厚い壁が少しだけ高くなる、という程度の変化しかありません。でも、これを2回、3回と繰り返していくうちに、粘土はあなたの指に従って、すーっと上へ上へと伸びていきます。この、自分の手で土を伸ばしていく感覚、これが電動ろくろの醍醐味の一つです!「伸びろー、伸びろー」と心の中で念じながら、焦らず、土の伸びたがっている声に耳を澄ませてみてください。
ステップ5「形を整える」自分だけのカーブを描こう
筒状に粘土が立ち上がったら、最後の仕上げ、形作りです。ここが一番クリエイティブで楽しい時間かもしれませんね!
外側に添える指の力加減や、コテの使い方一つで、器は様々な表情を見せてくれます。例えば、下の方をぐっと指で押してあげれば、ふっくらと丸みを帯びた形になりますし、逆に口元を少し外に広げてあげれば、シャープでモダンな印象になります。
なめし皮を使って口元を滑らかにしたり、弓を使って腰のあたりの余分な粘土を削ぎ落としたり。自分の「好き」を、思う存分この粘土にぶつけてみてください。少しくらい歪んでいても大丈夫。それが手作りの「味」というものです。完璧なシンメトリーを目指すよりも、あなたの手の跡が残っているような、少し不格好なくらいの方が、絶対に愛着が湧きますから。最後の最後まで、土との対話を楽しんで、あなただけの形を見つけてください。
初心者が陥りがちな失敗と、その乗り越え方

さて、ここまで理想的な流れを説明してきましたが、現実はそう甘くはありません。というか、ほぼ100%の確率で、何かしらの失敗を経験します。でも、それはあなたが下手だからじゃない。みんなが通る道なんです。ここでは、私が実際に経験し、多くの初心者が「あぁっ!」と叫ぶ代表的な失敗例と、そのリカバリー方法(あるいは心の持ちよう)についてお話しします。
「ぐにゃっ…」中心がずれる!そんな時のリカバリー方法
これはもう、王道の失敗ですね。いい感じに筒状に伸びてきたのに、ちょっと指に力が入りすぎた瞬間、「ぐにゃっ」と器が歪んでしまう。あの絶望感、たまりませんよね。
もし歪みが小さければ、慌てずにろくろの回転を少し遅くして、内側と外側から優しく手を添え、ゆっくりと形を修正してみましょう。焦って力を加えると、さらに歪みが大きくなるので、深呼吸して、とにかく優しく。
でも、もし歪みが大きくて、もうどうしようもない!という状態になったら…思い切って上からぐしゃっと潰して、もう一度「中心出し」からやり直すのが一番の近道です。ええー、もったいない!と思うかもしれませんが、歪んだまま無理やり進めても、ロクなことになりません。その歪んだ粘土は、あなたに「中心が大事だよ」と教えてくれた、最高の先生だと思ってください。潔くやり直す勇気、これが上達の秘訣です。
「薄くしすぎた!」穴が開いちゃった時の絶望と対処法
これも、本当によくあります。特に、薄くて繊細な器を作ろうと意気込んでいる時ほど、やってしまいがち。「あともう少しだけ薄く…」という欲望が、悲劇を呼びます。指先に「ブスッ」という嫌な感触。見ると、器の側面に無情にも小さな穴が…。
本当に小さな穴であれば、リカバリーできる可能性はあります。その穴より少し大きい粘土の破片(「友土」と言います)を持ってきて、穴の部分にペタッと貼り付け、指で優しく馴染ませてみてください。うまく一体化すれば、何事もなかったかのように修正できます。
でも、これも穴が大きい場合や、修正しようとして逆にぐちゃぐちゃになってしまった場合は、諦めが肝心です。その器は、残念ながらそこで命運が尽きました。でも、落ち込まないで。あなたは「これ以上薄くすると穴が開く」という、貴重な指先の感覚を学んだのです。これは、大成功の失敗なんですよ。次の挑戦では、きっとその指先の感覚があなたを助けてくれるはずです。
どうしても上手くいかない…そんな時は一旦離れてみる勇気も大事
何度やっても中心が出ない。作っては潰し、作っては潰し、もう粘土が泥水みたいになってきた…。そんな時、ありますよね。イライラしてきて、楽しくて始めたはずの陶芸が、ただの苦行に感じてしまう。
そんな時は、一度、電動ろくろから離れてみましょう。
手を洗って、お茶でも一杯飲んで、他の人の作品を眺めたり、アトリエの外の空気を吸ったり。少し時間を置くだけで、凝り固まっていた肩の力が抜け、新しい視点が見えてくることがあります。陶芸は、根性論だけではどうにもならない、不思議な世界です。自分の心と体がリラックスしていないと、土も応えてくれません。
「今日はもうダメだ!」と思ったら、その日は潔く終えるのも立派な選択です。その日の失敗は、決して無駄にはなりません。あなたの体と指先が、その失敗の感覚をちゃんと覚えています。そして次回、ろくろの前に座った時、不思議と前回よりもうまくいく、なんてことが本当にあるんですよ。土との付き合いは、人間関係と一緒。時には距離を置くことも大切なんです。
まとめ 電動ろくろは、あなただけの物語を紡ぐ道具

さて、ここまで電動ろくろの基本について、私の暑苦しいくらいの熱量でお話ししてきました。いかがでしたでしょうか。道具の準備から、具体的なステップ、そして誰もが通る失敗の道まで、一通りお伝えしてきました。
結局のところ、電動ろくろで一番大切なのは、家の土台作りと同じ「土殺し」と「中心出し」という最初のステップでしたね。ここさえ丁寧に行えば、あとの工程は驚くほどスムーズに進みます。そして、忘れてはならないのが「失敗は当たり前」という心構え。ぐにゃぐにゃになった粘土も、穴が開いてしまった器も、すべてがあなたを成長させてくれる貴重な経験なんです。
電動ろくろは、単に粘土で形を作るための機械ではありません。私は、自分自身と向き合い、自分だけの物語を紡ぐための、最高の道具だと思っています。くるくると回る土に触れていると、日々の悩みや焦りがすーっと消えていき、無心になれる。そして、自分の手の中から、世界に一つだけの形が生まれてくる。たとえそれが少し歪んでいたって、不格好だって、構いません。その歪みこそが、あなたがその時、その場所で、土と対話した証。誰にも真似できない、あなただけの「味」になるのですから。
この記事を読んで、「ちょっとやってみようかな」と、あなたの心が少しでも動いてくれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。さあ、汚れてもいい服に着替えて、土のひんやりとした感触を、その手で確かめに行きませんか?あなただけの、愛しい器が生まれるのを、土もきっと待っていますよ。