陶芸をやるメリット!陶芸で人生がちょっと豊かになった話
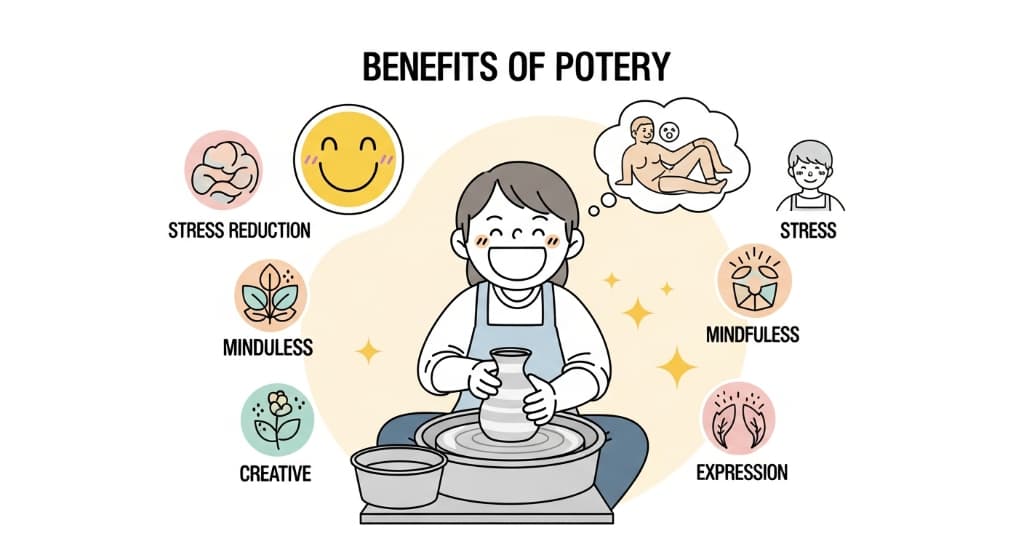
「何か新しい趣味、始めたいな…」
そう思ってスマホを眺めているあなた。ええ、わかります。私もそうでした。毎日仕事と家の往復で、なんだか心がすり減っていくような感覚。かといって、何を始めたらいいのかわからない。
そんなあなたに、私が心の底からおすすめしたいのが「陶芸」です。
え、陶芸?地味じゃない?難しそうだし、不器用な私には無理かも…。
うん、その気持ちもよーくわかります。でも、ちょっとだけ聞いてください。陶芸は、ただの趣味や習い事なんかじゃありません。これは、すり減った心を潤し、日常に彩りを与え、自分自身と向き合うための、いわば「最高の自己投資」なんです。
毎日使うマグカップが、もし自分で作った世界に一つだけのものだったら?
イライラやモヤモヤでいっぱいになった頭を、空っぽにできる時間があったとしたら?
何かに無心で没頭する、あの子供の頃のような感覚を、もう一度味わえるとしたら?
最高じゃないですか?
この記事では、かつてはあなたと同じように「不器用だし…」と尻込みしていた私が、なぜこんなにも陶芸にどハマりしてしまったのか、そのメリットを余すところなく、私の体験談と熱量マシマシでお伝えします。読み終わる頃には、きっとあなたも土をこねたくてウズウズしているはず。保証しますよ!
陶芸は究極の「自分時間」 デジタルデトックスと創造の喜びが同時に手に入る

まず、声を大にして言いたいこと。それは、陶芸がもたらしてくれる「自分だけの時間」の価値です。現代社会って、常に何かに接続されていませんか?スマホ、PC、SNS…。情報が滝のように流れ込んできて、気づけば頭の中は他人の情報でパンパン。そんな毎日に、陶芸は強制的に「待った」をかけてくれるんです。
スマホを置いて土と向き合う贅沢な時間
陶芸をやっている間、スマホなんて触っていられません。だって、両手は泥だらけなんですから。これが、実はとんでもなく贅沢なことなんです。
初めて陶芸教室の門を叩いた日、私は正直、不安でいっぱいでした。周りはなんだかベテランっぽい人ばかりに見えるし、「私なんかが場違いかも…」なんて思ったりして。でも、先生に渡されたひとかたまりの土を目の前にして、こね始めた瞬間、そんな不安はどこかへ消えていきました。
ひんやりとして、しっとりとした土の感触。指先に伝わるその重み。力を込めれば形を変え、優しく撫でれば滑らかになる。そこには、土と私しかいません。通知音も、誰かからのメッセージも、締め切りも、一切ない世界。ただただ、目の前の土と対話する。
最初は「うまく作らなきゃ」という気持ちが強かったんです。でも、何分か経つうちに、そんなことどうでもよくなりました。ただ、この感触が心地いい。形が変わっていくのが面白い。それだけ。気づけば1時間なんてあっという間。教室を出る頃には、あんなに重かった頭が、信じられないくらいスッキリしていました。これって、最高のデジタルデトックスだと思いませんか?私たちは、意識的に「何もしない」「情報から離れる」時間を作らないと、どんどん疲弊してしまうのかもしれませんね。
「無心」になれるって実はすごいこと
「無心になる」って、言葉で言うのは簡単ですけど、実際にやってみるのってすごく難しいですよね。瞑想しようとしても雑念が浮かぶし、ぼーっとしようとしても仕事のことが頭をよぎる。わかります、私もそうでしたから。
でも、陶芸、特に「ろくろ」は、半ば強制的に私たちを「無心」の状態へといざなってくれるんです。
高速で回転する土の塊に、そっと指を添える。少しでも気を抜いたり、余計なことを考えたりすると、遠心力に負けて形はあっという間にぐにゃり。そう、歪んでしまうんです。だから、成功させるためには、全神経を指先に集中させ、土の中心を感じ、呼吸を整えなければなりません。
「うわっ!」「あーっ!」なんて情けない声を上げながら、何度も失敗しました。隣のおばあちゃんが涼しい顔で美しい壺を立ち上げている横で、私は得体の知れない物体を量産していましたよ。ええ、笑ってください。でも、その失敗の繰り返しの中で、ふっと雑念が消える瞬間が訪れるんです。回転する土と自分の指先だけが世界のすべてになる、あの不思議な一体感。
時間が溶けていくような感覚。これこそが「無心」なんだと、体で理解した瞬間でした。日々の悩みやストレスなんて、高速回転するろくろの前ではちっぽけなもの。終わった後の、あの心地よい疲労感と達成感は、他の何にも代えがたいものがあります。悩みを忘れたいなら、旅行に行くより、お酒を飲むより、ろくろを回した方が早いかもしれません。…いや、ちょっと言い過ぎかな?でも、私にとってはそれくらいの効果があったんです。
世界に一つだけの「マイうつわ」が作れる 愛着が湧きすぎて市販品には戻れないかも

陶芸の醍醐味といえば、やっぱりこれでしょう!自分の手で、世界に一つしかないオリジナルのうつわが作れること。お店で売っているような完璧なものじゃなくてもいい。いや、むしろ完璧じゃないからこそ、愛おしくなるんです。
歪んでたってそれが「味」 完璧じゃないから愛おしい
私が初めて完成させた作品は、お茶碗でした。…いや、お茶碗のつもりで作った何か、と言った方が正しいかもしれません。形は少しいびつで、ろくろ目もガタガタ。釉薬(ゆうやく)のかかり方もムラがあって、高台(こうだい)なんてちょっと斜め。お店に並んでいたら、間違いなく誰も手に取らないでしょうね。
でもね、焼き上がったその“お茶碗”を手に取った時の感動は、今でも忘れられません。「え、これ私が作ったの?マジで?」って。あの無機質な土の塊が、こんなにも温かみのあるものに変わるなんて。信じられない気持ちでした。
その歪んだお茶碗で、初めて白いご飯をよそって食べた時のこと。もう、格別でした。正直、市販のつるんとしたお茶碗の方が持ちやすいし、食べやすい。でも、このガタガタのお茶碗で食べると、なぜかお米が3倍くらい美味しく感じられたんです。不思議ですよね。自分の指の跡が残っていたり、ちょっと厚ぼったくなってしまった部分があったり。そのすべてが「私が作った証」で、たまらなく愛おしく感じられる。
完璧なものを求めるのが当たり前の社会で、「完璧じゃないもの」を慈しむ時間。不格好な部分を「味」として受け入れる感覚。これって、すごく人間らしいし、優しい気持ちになれると思いませんか?以来、私の食器棚には、そんな「味」のある子たちが少しずつ増え続けています。
毎日の食事がちょっと特別なイベントに変わる魔法
自分で作ったうつわを使い始めると、いつもの何気ない食事が、なんだか特別なイベントのように感じられるようになります。これは本当です。
例えば、朝食。いつもは慌ただしくトーストをかじるだけだったのが、自分で作ったちょっと大きめのプレートに盛り付けるだけで、なんだかカフェのモーニングみたいに見えてくるから不思議。スーパーで買ってきたお惣菜だって、手作りの小鉢にちょこんと乗せるだけで、料亭の一品みたいに(…は、言い過ぎか)見えたりするんです。
「このお皿には、どんな料理が合うかな?」
「このカップでコーヒーを飲んだら、美味しいだろうな」
そんなことを考える時間が増えました。料理をするのも、前よりずっと楽しくなった気がします。うつわが主役で、料理がそれを引き立てる、みたいな。逆転の発想ですよね。
友人が遊びに来た時に、「このお皿、素敵だね」なんて言われた日には、もう大変。「えへへ、これ、私が作ったんだ」って、得意げに言っちゃいます。相手が「えー!すごい!」なんて言ってくれたら、自己肯定感は天井を突き破りますよ。たかがうつわ、されどうつわ。自分で作ったうつわ一つで、日常はこんなにも豊かになる。これは、陶芸を始めなければ絶対に分からなかった感覚です。
驚くほどストレス解消になる 土の感触が脳を癒やすってホントだった

「土をいじると癒やされる」って、よく聞く話だと思いませんか?正直、私は始めるまで半信半疑でした。「泥遊びの延長でしょ?」くらいにしか思っていなかった。でも、ごめんなさい。私が間違っていました。土の力、なめてました。あれは、科学的にも理にかなった、最高のセラピーなんです。
ひんやりなめらか…五感をフル活用する心地よさ
陶芸って、五感をめちゃくちゃ使うアクティビティなんです。まず、土に触れる「触覚」。ひんやりとして、しっとりとした粘土の感触は、それだけでなんだか落ち着きます。こねたり、叩いたり、伸ばしたりする中で、その感触はどんどん変化していく。このプロセスが、単純に気持ちいい。
そして、土の匂いをかぐ「嗅覚」。雨上がりの地面のような、懐かしい匂いがします。目をつぶって深呼吸すると、なんだか自然の中にいるような気分に。さらに、ろくろが回る音や、土を叩く音を聞く「聴覚」。集中していると、そのリズミカルな音がBGMのように心地よく響きます。
もちろん、形作られていくうつわを見る「視覚」も。自分の手の中から、少しずつ形が生まれてくる様子は、見ていて飽きることがありません。そして最後は、完成したうつわで食事を味わう「味覚」。ほら、五感全部使ってるでしょ?
普段の生活、特にデスクワークなんて、視覚と聴覚くらいしか使っていないことが多い。でも陶芸は、眠っていた感覚を全部呼び覚ましてくれるような感じ。この五感への刺激が、脳をリフレッシュさせ、ストレスを和らげてくれるんだそうです。難しい理屈はよくわからないけど、とにかく「気持ちいい」ってことは、私の体が証明しています。
イライラも悩みもろくろと一緒に回して吹き飛ばす!
仕事で理不尽なことがあった日。人間関係でモヤモヤした日。そんな日は、もう陶芸教室に駆け込むに限ります。
特に効果的なのが「菊練り」という、土の空気を抜く工程。体重をかけて、ぐっ、ぐっ、とリズミカルに土を練り込んでいく作業です。これがもう、めちゃくちゃストレス発散になる!「あの野郎ー!」なんて心の中で叫びながら練っていると、不思議と怒りが土に吸収されていくような気がするんです。物理的に力を加えるっていうのが、いいのかもしれませんね。サンドバッグを殴るような感覚に近いかも(殴ったことないけど)。
そして、先ほども話した「ろくろ」。高速で回転する土を見つめていると、自分の悩みなんて、遠心力でどこかへ吹き飛ばされてしまったような気分になります。ぐにゃりと形が崩れたっていいんです。「あーあ」って笑い飛ばせば、さっきまで悩んでいたことが馬鹿らしくなってくる。
陶芸は、自分の内側にあるネガティブな感情を、創造的なエネルギーに変換する装置のようなものかもしれません。イライラやモヤモヤを土にぶつけて、こねて、形にして、最後には美しい(?)うつわに変えてしまう。なんて生産的なストレス解消法なんでしょう。お酒を飲んで愚痴るのもいいけど、次の日には何も残らない。でも陶芸なら、あなたの手元に「作品」という形で、乗り越えた証が残るんですよ。これって、すごくないですか?
新しい「仲間」との出会いがある 世代を超えたゆるやかな繋がりが心地いい

一人で黙々と作業するイメージが強い陶芸ですが、実は、人との新しい出会いが生まれる場所でもあるんです。しかも、会社や地元の付き合いとはちょっと違う、ゆるやかで心地よい繋がりがそこにはありました。
陶芸教室はまるで大人の新しい社交場
私が通っている陶芸教室には、本当に色々な人がいます。20代の若いカップルから、私のような30代の会社員、子育てが一段落した主婦の方、そして、人生の大ベテランである70代、80代のおじいちゃん、おばあちゃんまで。職業も年齢もバラバラ。普段の生活では、絶対に交わることのなかったであろう人たちが、同じ「土が好き」という共通点だけで集まっている。
そこには、会社の飲み会のような面倒な気遣いや、ママ友同士の探り合いみたいなものはありません。「その釉薬の色、いいですね」「あら、その形、面白いわね」なんて、作品を通して自然と会話が生まれます。
そういえば、この前なんて、隣で作業していたおじいちゃんが「お嬢ちゃん、その土殺し(※土の中心を出す作業のこと)、腰が入っとらんな」なんて、渋い声でアドバイスをくれたりして。最初は「え、土殺し…?」って言葉の物騒さにビビりましたけど(笑)、そういう世代を超えた交流がすごく新鮮で楽しいんです。みんな、先生であり、生徒でもある。そんなフラットな関係性が、とても心地いいんですよね。
作品を褒め合う文化が自己肯定感を爆上げしてくれる
陶芸教室の素敵なところは、「褒め合う文化」が根付いていること。自分の作品が焼き上がって棚に並べられると、誰かしらが「わー、素敵!」「この色合い、どうやって出したの?」と声をかけてくれます。
正直、自分の作品なんて、まだまだ未熟で、人様に見せるのも恥ずかしいレベル。でも、みんな自分の作品作りの大変さを知っているからこそ、他人の作品の良いところを見つけて、心から褒めてくれるんです。これ、めちゃくちゃ嬉しいですよ。
会社では、成果を出して当たり前。褒められることなんて、そうそうありません。でも、ここでは、自分が楽しんで作ったものが、誰かの心を動かし、褒めてもらえる。この経験が、乾ききっていた私の自己肯定感を、じわじわと満たしてくれました。
「私にも、こんなものが作れるんだ」
「私のセンスも、まんざらじゃないかも」
そう思えるだけで、日々の生活にハリが出る。ちょっと大げさかもしれないけど、陶芸教室は、私にとって心の安全地帯であり、エネルギーをチャージできるパワースポットのような場所になっています。
意外と奥が深い!探求心がくすぐられ一生モノの趣味になる可能性大

最初は「ちょっとやってみようかな」くらいの軽い気持ちで始めた陶芸。でも、やればやるほど、その奥深さに気づかされます。これは、ちょっとかじっただけでは終わらない、一生付き合っていける趣味になるかもしれない。そんな予感がしています。
土選び釉薬焼成…知れば知るほど沼にハマる
陶芸って、ただ粘土をこねて形を作るだけじゃないんです。その先には、広大で深淵な「沼」が広がっていました。
まず、「土」。粘土にも色々な種類があるんです。ざらっとした質感の「信楽(しがらき)」、きめ細やかで白い「磁器土」、鉄分を多く含んで黒っぽくなる土…。土の種類を変えるだけで、作品の表情はガラリと変わります。
次に、「釉薬(ゆうやく)」。うつわの表面にかけるガラス質の薬品のことですが、これがまた、とんでもなく奥深い。透明なもの、マットなもの、貫入(かんにゅう)という細かいヒビが入るもの。同じ釉薬でも、厚くかければ濃い色に、薄くかければ淡い色に。2種類の釉薬を重ねがけしたらどうなる…?なんて考え始めると、もう止まりません。実験みたいで、ワクワクするんですよ。
そして、最終工程の「焼成」。窯の中でどうやって焼くか(酸化焼成か還元焼成か)によって、同じ土と釉薬でも、まったく違う色合いに焼き上がることがあるんです。もう、化学の世界ですよね。窯を開けるまでは、どんな作品に仕上がっているかわからない。このドキドキ感がたまりません。まあ、たまに「えええ!こんな色になるなんて!」っていう悲劇も起こりますけど、それもまた一興。
知れば知るほど、試したいことが増えていく。この探求心が尽きない感じ、まさに「沼」です。でも、こんなに楽しくてクリエイティブな沼なら、喜んでハマり続けたいと思いませんか?
失敗は成功のもと 割れたってそれもまた学び
陶芸は、失敗がつきものです。乾燥中にヒビが入ったり、素焼きで割れたり、釉薬がうまくかからなかったり、本焼きで歪んでしまったり…。時間と手間をかけた作品がダメになってしまった時のショックは、正直、かなり大きいです。「あんなに頑張ったのに…」って、本気でへこみます。
私が初めて作った大皿は、乾燥のさせ方が悪かったみたいで、見事に真っ二つに割れてしまいました。もう、悲しくて悲しくて。でも、教室の先生が「あー、やっちゃったね。でも、なんで割れたかわかる?これがわかれば、次はもっといいのが作れるよ」と笑いながら教えてくれました。
そうなんですよね。失敗には、必ず原因がある。乾燥が急すぎたのか、厚みが均一じゃなかったのか、土の締め方が甘かったのか。その原因を考えて、次に活かす。このトライ&エラーの繰り返しこそが、上達への一番の近道なんです。
これって、なんだか人生みたいじゃないですか?失敗を恐れて何もしないより、どんどん挑戦して、失敗して、そこから学んで次に進む。陶芸は、そんな大切なことを、身をもって教えてくれているような気がします。割れてしまったお皿は悲しいけど、そのおかげで得られた知識や経験は、確実に私の力になっている。そう思えるようになってから、失敗を恐れずに、もっと色々なことに挑戦できるようになりました。
まとめ 陶芸はあなたの日常を豊かにする最高のスパイスです

ここまで、私が陶芸にどハマりしている理由、そして陶芸がもたらしてくれる数々のメリットについて、熱量たっぷりに語ってきました。いかがでしたでしょうか?
陶芸は、スマホや情報から離れて「無心」になれる究極のデジタルデトックスであり、自分自身と向き合うための貴重な時間を与えてくれます。そして何より、世界に一つだけの「マイうつわ」を生み出す創造の喜びは、何物にも代えがたいもの。歪んでいたっていい、不格好だっていい。その「味」こそが愛おしく、いつもの食卓を特別なものに変えてくれる魔法のアイテムになるんです。
ひんやりとした土の感触は驚くほどストレスを癒やしてくれますし、教室に行けば、年齢や職業を超えた新しい仲間との出会いも待っています。知れば知るほど奥深いその世界は、あなたの探求心をくすぐり、一生モノの趣味になる可能性を秘めています。
「でも、やっぱり不器用だし…」「センスがないから…」
まだ、そう思っていますか?大丈夫。そんな心配は、土を触り始めた瞬間にどこかへ吹き飛んでしまいますから。大切なのは、うまく作ることじゃありません。「やってみたい」という、その好奇心だけ。あとは、土が全部受け止めてくれます。
まずは、お近くの陶芸教室の「体験コース」にでも、足を運んでみませんか?たった数時間で、あなたの日常に新しい風が吹き込み、世界がほんの少しだけ違って見えるようになるはずです。土をこねて、形作って、火に入れて、新しいものを生み出す。そんな原始的でクリエイティブな営みの中に、私たちが忘れかけていた大切な何かが、きっと詰まっています。











