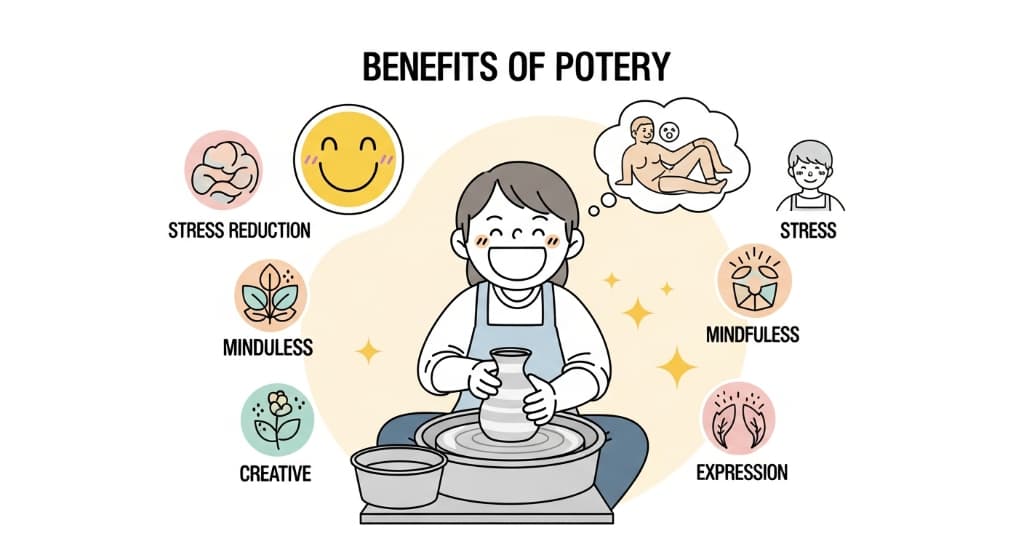不格好が愛おしい!陶芸体験で「私だけの花瓶」を作ったら

なんか毎日同じことの繰り返しだな…。そんな風に感じているあなた、週末に陶芸体験で花瓶作りなんていかがでしょう?
「え、陶芸?難しそう…」「不器用だから無理!」って思いました?わかります。私も最初はそうでした。でもね、結論から言っちゃうと、陶芸体験は不器用な人ほど、そして完璧主義じゃない人ほど、心の底から楽しめる最高のアクティビティなんです。
特に「花瓶作り」。これがまた、いいんですよ。自分が作った、ちょっと歪で、どこか頼りない世界に一つだけの花瓶。それに道端の小さな草花を一本生けるだけで、いつもの部屋が、見違えるほど愛おしい空間に変わるんです。この記事では、私が実際に陶芸で花瓶作りに挑戦した体験談を、余すところなく、超・生々しくお伝えします!
この記事を読み終わる頃には、あなたもきっと土の匂いが恋しくなって、近所の陶芸工房のサイトを検索しちゃってるはず。土と戯れる、ちょっと特別な世界の扉を開けてみませんか?
陶芸体験で花瓶を作るのが最高の休日の過ごし方です

私がなぜこんなにも「陶芸で花瓶作り」を熱烈におすすめするのか。それは、単なる「モノ作り体験」では終わらない、とんでもない魅力が詰まっているからに他なりません。完成した作品が生活に溶け込む喜び、そして何より、自分の「不完全さ」を丸ごと愛せるようになる、魔法のような時間なんです。
既製品にはない「物語」が生まれるから
スーパーや雑貨屋さんに行けば、そりゃあもう、形が整った綺麗な花瓶がいくらでも売っています。安くて、オシャレで、完璧な花瓶が。でも、自分で作った花瓶には、そういう既製品には絶対にない「物語」が宿るんですよ。
「あ、この歪みは、ろくろの回転にビビって変な力が入った時のか…」「この指の跡、先生に『もっと大胆に!』って言われて、思い切って付けたやつだ!」みたいに、花瓶を見るたびに、その日の奮闘や感動が鮮やかによみがえってくるんです。それはもう、ただの花瓶じゃなくて、私の思い出そのもの。うちの子、みたいな感覚。
花を生けていなくても、ただそこに置いてあるだけで、なんだか空間がほっこりする。そんな存在になるんです。こればっかりは、どんなに高級なブランドの花瓶にも真似できない、プライスレスな価値だと、私は本気で思っています。
「まあ、いっか」が心地よくなる不思議な体験
普段の生活や仕事って、どうしても「ちゃんとやらなきゃ」「完璧にしなきゃ」ってプレッシャー、ありませんか?私はあります。めちゃくちゃあります。でも、陶芸、特に電動ろくろは、そんな完璧主義を一瞬で粉砕してくれます。
ちょっと力を入れすぎればぐにゃり、集中が切れればぐにゃり。イメージ通りになんて、まずいきません。最初は「あー!もう!」ってイライラするんですけど、不思議なことに、だんだんそれが面白くなってくるんです。先生が「はい、これも味だから大丈夫!」って笑い飛ばしてくれると、「そっか、味か…」って力が抜けていく。
最終的に出来上がったのは、想像とは似ても似つかない、ずんぐりむっくりな花瓶。でも、これがなんだか最高に愛おしい。「まあ、いっか。これも私らしいや」って、心から思える。この「まあ、いっか」の感覚こそ、陶芸体験がくれる最高のプレゼントかもしれません。日々の小さな失敗にも、ちょっとだけ優しくなれる気がするんです。え?気のせい?いやいや、そんなことないはず!
いざ陶芸体験へ!その前に知っておきたいアレコレ
「よーし、私も陶芸やってみるぞ!」と気持ちが盛り上がってきたあなた。素晴らしい!でも、ちょっと待って。その勢いのまま突撃する前に、知っておくと当日100倍楽しめる、いくつかのポイントがあるんです。私の失敗談も交えながら、リアルな準備についてお話しさせてください。これ、学校じゃ教えてくれないやつですよ。
服装と持ち物?汚れてもいい服なんて持ってない問題
よく「汚れてもいい服装で」って書いてありますよね。でも、正直な話、「心底どうでもいい服」なんて、そんなに持ってなくないですか?私はお気に入りの白いスウェットで行って、見事に泥はねのシミをつけました。ええ、芸術的な模様だと自分に言い聞かせています…。
結論、エプロンは貸してもらえますが、あれは気休めだと思った方がいいです。特に電動ろくろは、回転の遠心力で泥水が結構飛びます。なので、ボトムスも油断禁物。黒っぽい色の、ジャージとか、洗いやすい素材のものが絶対におすすめ。あと、意外と見落としがちなのが靴。足元にも泥が落ちるので、おニューのスニーカーは避けた方が賢明です。
持ち物は、基本的には手ぶらでOK。でも、もしあると便利なのが「爪切り」。爪が長いと、土を触る時に作品にひっかき傷を作っちゃうんです。まさに私がやりました。繊細な作業の邪魔になるので、爪は短く切っていくのがマナーであり、自分のためでもあります。あとは、汗を拭くタオルと、何より「楽しむぞ!」っていう童心。これが一番大事な持ち物ですね!
工房選びと予約のコツというか私の好み
さて、どこで体験するか。これがまた悩ましい問題ですよね。「陶芸体験」で検索すると、まあ出るわ出るわ。大手予約サイトで口コミを見ながら選ぶのも一つの手。それはそれで安心感があります。
でも、私個人としては、ちょっとマニアックな探し方が好きだったりします。個人の陶芸家さんがやっている、ちょっと古びた(失礼!)工房のホームページとかをディグるのが楽しいんです。そういうところって、先生の作品へのこだわりが垣間見えたり、独特の雰囲気があって。
プランを選ぶ時は、ぜひ「電動ろくろ」に挑戦してみてほしい!手びねりも味があって素敵なんですが、やっぱり「陶芸やってる感」が一番高まるのは、ウィーンと回るろくろと格闘する、あの時間だと思うんです。難易度は高いけど、その分、形ができた時の感動はひとしおですよ。
予約する時は、「花瓶を作りたいんですけど、どのくらいの大きさまで作れますか?」って事前に聞いておくのもいいかもしれません。夢ばっかり膨らんで、作れる粘土の量が決まってて「え、湯呑みサイズしか…」なんてことになったら悲しいですからね。
いざ本番!土と戯れる感動と絶望の体験記

予約も済ませ、服装もバッチリ。ついにやってきた陶芸体験当日。工房のドアを開けた瞬間にふわっと香る、ひんやりとした土の匂い。この匂いを嗅ぐと、いまだにあの日の興奮がよみがえってきます。さあ、ここからは私が実際に体験した、笑いあり涙あり(?)の陶芸奮闘記を、時系列でお届けします!
土とのご対面、そして「土殺し」という名の儀式
先生に案内されて席に着くと、目の前にはずっしりとした粘土の塊が。「これが…これから私の花瓶になるのか…」と、なんだか神妙な気持ちになります。ひんやりとしていて、しっとり滑らか。生き物みたいで、ちょっとドキドキします。
そして始まる最初の工程、その名も「土殺し」。なんだか物騒な名前ですけど、粘土の中の空気を抜いて、粘土の菊の花びらのような模様を作る「菊練り」という作業のことです。先生がやると、いとも簡単に、リズミカルに粘土が形を変えていく。かっこいい…。
「はい、じゃあやってみましょう!」と渡されて、いざ挑戦。…え?なにこれ、全然言うこと聞かない。ただの重たい塊をこねくり回しているだけの人、それが私。腕はパンパンになるし、手のひらは泥だらけ。もうこの時点で「私、向いてないかも…」と心が折れかけました。でも、先生が「最初はみんなそんなもんですよ!大丈夫!」って優しく手伝ってくれて、なんとか形に。この最初のつまずきが、後の感動を大きくしてくれるんですよね、たぶん。
電動ろくろとの格闘!言うことを聞かないじゃじゃ馬
いよいよ本日のメインイベント、電動ろくろです!ペダルを踏むと、ウィーンと軽快な音を立ててろくろが回り始める。おお、テレビで見たやつだ!とテンション爆上がり。
先生のお手本通り、まずは粘土をろくろの真ん中に固定する「土殺し」ならぬ「中心出し」。これが、まあ、できない。ちょっと力を入れると、粘土が遠心力でぐわんぐわんと暴れだす。まるで生きているみたいに。「力を抜いて、粘土の中心を感じて…」って言われるんですけど、その「中心」がどこにあるのか全くわからない!
「あ、あ、あ!」って声にならない悲鳴を上げていると、粘土は無慈悲にも「ぐにゃあ〜」と無残な姿に。絶望。でも、その瞬間、すっと先生の手が伸びてきて、魔法のようにくいっと形を戻してくれるんです。「おお…神…!」ってなります、マジで。この「絶望からの救済」のコンボが、体験中に何度も繰り返される。もはや一種のアトラクションですよ、これは。
奇跡の瞬間!器が立ち上がる感動のクライマックス
何度もぐにゃぐにゃになりながら、先生に助けてもらいながら、それでも諦めずに土に触れ続けていると、ある瞬間、ふっと指先の感覚が変わるんです。あれ、なんか、言うこと聞いてくれてる…?
水で濡らした指をそっと添えて、ゆっくりと上に引き上げていく。すると、さっきまでただの塊だった粘土が、意思を持ったかのようにすーっと立ち上がってくるんです!うわあああ!立った!立ったよ!って心の中で叫びました。
この瞬間の感動は、ちょっと言葉にできません。自分が、この手で、無から有を生み出している。大げさじゃなく、そんな感覚に包まれます。多少歪んでいても、ちょっと厚ぼったくても、そんなことはどうでもいい。自分の手から生まれた形が、目の前にある。その事実だけで、胸がいっぱいになりました。これだから陶芸はやめられないんです!
私だけの花瓶を作る!こだわりと諦めのせめぎ合い

さて、なんとか器の形が立ち上がったところで、ここからが「花瓶」にしていく工程です。ただの筒じゃなくて、ちゃんとくびれがあったり、口が広がっていたりする、あの花瓶らしいフォルムを目指します。でもね、ここでもまた、理想と現実の厳しいギャップに打ちのめされることになるんですよ…。
理想は高く、現実は寸胴。でもそれがいい
私の頭の中では、そりゃあもう、北欧デザインのような、シュッと洗練されたスマートな花瓶が完成するはずでした。首がキュッとしまっていて、口がラッパみたいにふわっと開いている、あの感じ。
で、ですよ。先生に「この辺を少しへこませてみましょうか」って言われて、おそるおそる指で押さえてみるわけです。…すると、どうでしょう。へこむんじゃなくて、全体が内側に傾いて、ただの「背の高い湯呑み」みたいになっていくじゃないですか!え?なんで?
焦って修正しようとすると、今度は別の場所が歪む。まさに泥沼。もうパニックです。最終的に、先生の助けもあってなんとか形にはなったんですけど、出来上がったのは、当初のイメージとはかけ離れた、どっしり安定感のある寸胴フォルムの花瓶。「うん、まあ、これはこれで…素朴でいいんじゃないかな…」と自分を納得させました。でも、この「思い通りにならない感」こそが、手作りの醍醐味。今ではこの寸胴ちゃんが、愛おしくてたまりません。
装飾という名の悪あがきと、愛着の芽生え
形が決まったら、最後の仕上げ、装飾です。カンナという道具で表面を削って滑らかにしたり、竹串で模様を描いたり、ハンコを押したり。ここが個性の見せ所!
私は調子に乗って、側面をぐるっと一周、波線模様を入れようとしました。が、ろくろの回転と手の動きがシンクロせず、見事なまでにガタガタの線に。「あちゃー…」と思ったけど、先生は「手描きの味が出てて良いじゃないですか!」と褒めてくれる。そうか、これも味か。魔法の言葉ですね。
最後に、底の部分に自分のイニシャルをこっそり彫りました。この小さなサインを入れた瞬間、この粘土の塊が、完全に「私のもの」になった気がしました。不格好で、計画通りにはいかなかったけど、間違いなく世界に一つだけの、私の花瓶。この時点でもう、愛着はMAXレベルに達していました。
体験後のお楽しみ!完成までの長い道のりと感動の再会

陶芸体験は、作品を作って「はい、おしまい」じゃないんです。むしろ、本当の楽しみはここから始まるのかもしれません。自分が魂を込めて作ったあの子が、どんな姿になって帰ってくるのか。その待ち遠しい時間も、体験の重要な一部なんですよ。
釉薬(ゆうやく)選びは運命の分かれ道
形作りが終わったら、作品は一度乾燥させ、素焼きされます。そして、その後に色を決める「釉薬(ゆうやく)」をかける工程があります。この釉薬選びが、また楽しくて、そして恐ろしい。
工房には、たくさんの釉薬の見本が置いてあります。「焼くとこんな色になりますよ」っていう小さなタイルみたいなやつです。透明感のある青、マットな白、渋い緑、温かみのある茶色…。もう、どれも素敵で目移りしちゃいます。
私は、深い森のような、しっとりとした緑色に一目惚れ。「これだ!」と決めて、お願いしました。でも、先生が言うんです。「釉薬はね、焼き方や土との相性で、見本通りになるとは限らないんですよ。それが面白いんだけどね」って。え、そうなの!?一種のギャンブルじゃないですか、それ。自分の子の運命を、窯の神様に委ねるしかない。このドキドキ感、たまりません。
忘れた頃にやってくる!箱を開けた瞬間の絶叫
体験から待つこと、約1ヶ月半。正直、日常の忙しさにかまけて、花瓶のことは少し忘れかけていました。そんなある日、ピンポーンと宅配便が。届いたのは、陶芸工房からの小さな段ボール箱。
「キターーーー!」
もう、心臓バクバクです。カッターで慎重にテープを切って、緩衝材をかき分けると…そこに、いました。私の、花瓶が。
まず思ったのは、「ちっさ!」。焼くと一回り縮むとは聞いていたけど、想像以上にコンパクトになっていて、なんだか可愛らしい。そして、肝心の色は…私が選んだ深い緑、ではなく、なんだか青みがかった、少し古びた銅のような、不思議な色合いになっていました。でも、それが、めちゃくちゃ良い!狙って出せる色じゃない、偶然が生んだ絶妙な風合い。ガタガタだと思っていた波線も、なんだかアーティスティックに見えるから不思議です。
「うわー!すごい!私がこれ作ったんだ…!」
思わず声に出して、一人で絶叫してしまいました。手の中にずっしりと感じる重みと、ひんやりと滑らかな手触り。この感動は、何にも代えがたい宝物です。
まとめ 陶芸体験は不器用なあなたのための最高の処方箋です

ここまで陶芸体験記にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。私がこの記事を通して、喉が枯れるほど伝えたかったこと。それは、陶芸体験、特に花瓶作りは、単なる暇つぶしや物作りなんかじゃない、ということです。
それは、自分の手で「物語」を生み出す体験。思い通りにいかない現実と向き合い、「まあ、いっか」と自分を許せるようになる時間。そして、完成した不格好な作品が、日々の暮らしにささやかな彩りと愛おしさを与えてくれる、魔法のような体験なんです。
電動ろくろの上でぐにゃりと崩れる粘土は、まるでコントロールできない自分の心のようでした。でも、先生に助けてもらいながら、必死に形にしていくうちに、なんだか自分自身と対話しているような、不思議な感覚になりました。完成した花瓶は、完璧じゃないけど、紛れもなく私の分身です。その子に道端の草花を生けるたび、私はちょっとだけ、自分を好きになれる気がします。
もし、あなたが日々の生活に少しでも疲れを感じていたり、何か新しいことを始めたいけど一歩が踏み出せずにいるのなら、騙されたと思って、近所の陶芸工房のドアを叩いてみてください。土の匂いを嗅ぎ、ひんやりとした粘土に触れた瞬間、きっと新しい世界の扉が開くはずです。さあ、次はあなたの番。あなただけの不格好で愛おしい花瓶の物語を、ぜひ紡いでみてください。