【暴露】陶芸家の年収、ぶっちゃけいくら?初心者が知っておくべきお金の話と生き残り戦略

「陶芸家って、なんだか素敵…」「自分の作った器で暮らすって、憧れるなぁ」
めちゃくちゃわかりますよ、その気持ち。土の香りに包まれて、ろくろを回し、世界に一つだけの作品を生み出す。そんな暮らしに、一度は夢を馳せますよね。
でも、ふとよぎる現実的な疑問。「…で、陶芸家って食べていけるの?年収って、実際どれくらいなの?」
今日は、そんなあなたの素朴で、でもめちゃくちゃ大事な疑問に、真正面からお答えしようと思います。
結論から言いますね。夢を壊すようで本当に申し訳ないんですが、陶芸だけで生活していくのは、正直言ってかなり厳しい道です。平均年収なんて言葉が霞んで見えるくらい、稼げる人とそうでない人の差が激しい世界。でも、絶望するのはまだ早い。この記事では、厳しい現実をお伝えするだけじゃなく、「じゃあ、どうすればいいの?」という具体的な話、そして年収という数字だけでは測れない陶芸の“本当の価値”について、私の経験も交えながら、余すところなくお話しします。
この記事を読み終える頃には、あなたはただ憧れるだけでなく、自分なりのリアルな陶芸との向き合い方を見つけられるはず。さあ、ちょっと生々しいけど、大切な「お金」と「夢」の話、始めましょうか。
ぶっちゃけ陶芸家の年収は厳しい!これが現実

さて、いきなり核心に迫りますよ。心の準備はいいですか?陶芸を仕事にしたいなら、まずこの現実を知っておくことが、何よりも大切なんです。憧れやキラキラしたイメージだけで突っ走ると、間違いなく途中で心が折れてしまいますからね。私も最初は「好きなことだから頑張れる!」なんて思っていましたが、いやはや、現実はそんなに甘くなかった…。
平均年収は200〜300万円?いや、もっと低い人もゴロゴロいる世界
よくネットで検索すると「陶芸家の平均年収は200万円~300万円」なんて情報が出てきたりします。でもね、これ、正直言ってあまりアテにならない数字だと私は思っています。え?なんでかって?
この数字には、人間国宝級の超有名作家さんも、美術大学を出て工房でアシスタントをしている若手も、私みたいに細々とやっている作家も、全部ごちゃ混ぜに含まれている可能性が高いからです。それに、そもそも「陶芸家」という肩書きだけで生計を立てている人がどれだけいるのか、正確な統計なんてないのが実情なんですよ。
私の周りを見渡してみても、現実はもっとシビアです。年収100万円に届かない作家さんなんて、本当にゴロゴロいます。というか、ほとんどの人がそうじゃないかな…。多くの作家は、陶芸教室の先生をしたり、全く別のアルバイトをしたりして、なんとか生計を立てています。「陶芸からの収入だけで暮らしてます」なんて言える人は、ほんの一握りの、選ばれし者たち。それが偽らざる現実なんです。悔しいけど、本当の話。だから、「陶芸家になる=いきなりバラ色の生活」という幻想は、今すぐゴミ箱にポイしちゃってください。それが、あなたの夢を守るための第一歩になります。
なぜ陶芸では稼ぎにくいのか?構造的な問題点
じゃあ、なんでそんなに稼ぎにくいのか?って話ですよね。「頑張りが足りないから?」いえいえ、それだけじゃないんです。これには、陶芸というジャンルが抱える、構造的な問題があるんですよ。
まず、とんでもなくコストと時間がかかること。粘土代、釉薬(ゆうやく)代、そして何より電気窯やガス窯を動かすための光熱費がバカになりません。特にガス代や電気代が高騰している昨今、窯焚き(かまたき)のボタンを押す手が震える…なんてことも日常茶飯事です。「うわ、今月も請求が…」って、毎月思いますもん。
しかも、一つの作品が完成するまでには、土練り、成形、削り、乾燥、素焼き、釉薬がけ、本焼き…と、めちゃくちゃ長い工程が必要です。一個のマグカップを作るのに、一体何時間かかっていると思ってるの!って叫びたくなります。でも、だからといって、マグカップ1個に1万円の値札をつけられますか?って話。なかなか、難しいですよね。ニトリや100円ショップに行けば、安くて機能的な器が手に入る時代ですから。私たちの作品は、そういう大量生産品と同じ土俵で価格競争をさせられてしまう宿命にあるんです。
稼ぐことへの罪悪感?作家特有のメンタリティ
もう一つ、これは作家側のメンタリティの問題かもしれないんですが、「自分の作品にお金の話を絡めることへの抵抗感」みたいなものも、結構ある気がします。私もそうでした。
「お金のために作っているんじゃない」「作品の価値を自分で値付けするなんておこがましい」…そんな風に考えてしまって、どうしても価格を安く設定しがちなんです。お客さんから「え、こんなに素敵なのに、こんなに安くていいんですか?」なんて言われると、「いやいや、とんでもないです!」なんて言っちゃう。本当は「でしょ!?もっと高くてもいいくらいでしょ!?」って心の中で叫んでるのにね(笑)。
この「清貧の思想」みたいなものが、アートや工芸の世界には根強く残っている気がします。でも、生活していくためには、自分の仕事に正当な対価を求めることは、絶対に必要。このマインドブロックを外すのが、実は技術を磨くのと同じくらい、あるいはそれ以上に難しいのかもしれません。
それでも稼いでいる陶芸家は何が違うの?

さっきまで、散々「稼げない!」って脅してしまって、ごめんなさい。でも、もちろん、ちゃんと陶芸で生計を立てて、キラキラ輝いている作家さんだっているんです。じゃあ、そういう人たちと、そうでない人の差は一体どこにあるんでしょう?「作品がズバ抜けて素晴らしいから?」うーん、それも一理ありますが、実はそれだけじゃない。今の時代、生き残る作家さんには、作品作り以外のある共通点があるんです。
「作品が良い」だけじゃダメ?プラスアルファのスキルが必須
昔は「良いものを作っていれば、いつか誰かが見つけてくれる」という神話がありました。でも、ごめんなさい、そんな時代はとっくに終わりました。今は、情報が溢れかえっていて、ただ黙って良いものを作っているだけでは、誰の目にも留まらずに埋もれていってしまいます。
じゃあ何が必要か。それは「届ける力」です。具体的には、セルフブランディングやマーケティングのスキル。例えば、自分の作品のコンセプトを明確な言葉で語れるか。作品の世界観が伝わるような、美しい写真を撮れるか。InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを効果的に使って、自分の活動や人柄を発信できるか。こういうスキルが、作品の良し悪しと同じくらい、いや、それ以上に重要になってきています。
「あの作家さん、なんであんなに人気なんだろう?」と思ってSNSを覗いてみたら、作品はもちろん素敵なんだけど、それ以上に投稿される文章が面白かったり、日々の暮らしの切り取り方がおしゃれだったりする。作品そのものだけじゃなくて、その作家さんが紡ぎ出す「世界観」まるごとを、ファンは愛しているんですよね。これ、めちゃくちゃ大事なポイントです。
作品を「売る場所」をどう確保するか
作った作品を、どこで、どうやってお客さんに届けるか。この「販路」の開拓も、作家の重要な仕事です。主な販路としては、以下のようなものがあります。
個展・グループ展: ギャラリーを借りて、自分の作品だけで空間を構成する。世界観を存分に表現できるけど、集客や費用面でのハードルは高め。
クラフトフェア・陶器市: 全国各地で開かれるイベントに出店する。たくさんのお客さんと直接話せるのが最大の魅力!でも、出店料もかかるし、何より体力勝負。一日中立ちっぱなしで接客するのは、想像以上にキツいですよ…。
委託販売: 雑貨屋さんやセレクトショップに作品を置いてもらう。自分でお客さんを探さなくてもいいのは楽だけど、売上の何割かを手数料としてお店に支払う必要があります。
オンラインショップ: BASEやSTORES、minne、Creemaなどを利用して、ネット上で販売する。全国の人に届けられるのが強み。でも、ただお店を開いただけでは誰も来てくれません。SNSでの告知や魅力的な写真が不可欠です。
どれか一つに絞るのではなく、これらを組み合わせながら、自分の作風やライフスタイルに合った売り方を見つけていく必要があります。「私のこの器は、どんな場所で、どんな人に見てほしいかな?」と想像することが、戦略の第一歩になりますね。
ファンを作るということの本質
最終的に、作家として長く活動していくために一番大切なのは、あなたの「ファン」を作ることです。ここで言うファンとは、ただの「お客さん」ではありません。「あなただから買う」「あなたの次の作品を楽しみにしている」と言ってくれる、熱烈な応援団のこと。
ファンは、作品の機能性や価格だけで判断しません。作品に込められたストーリー、作っているあなたの情熱や人柄、その全てを含めて「応援したい」と思ってくれる人たちです。
私が駆け出しの頃、クラフトフェアで一日中誰にも見向きもされず、心が折れかけていた夕方。「このお皿の、このちょっと歪んだところが、なんだか人間みたいで良いですね」って、一枚のお皿をそれはそれは愛おしそうに買ってくれたお客さんがいました。その言葉と笑顔に、どれだけ救われたことか…。今でも、あの時の光景は忘れられません。
そういう一人ひとりのファンとの出会いが、作家を続けさせてくれる何よりの原動力になるんです。だから、ただ売るだけじゃなく、SNSや対面販売の場で、自分の想いを伝え、お客さんの声に耳を傾ける。その地道なコミュニケーションこそが、何にも代えがたい財産になっていくんですよ。
「陶芸で生きたい」初心者が今からできること
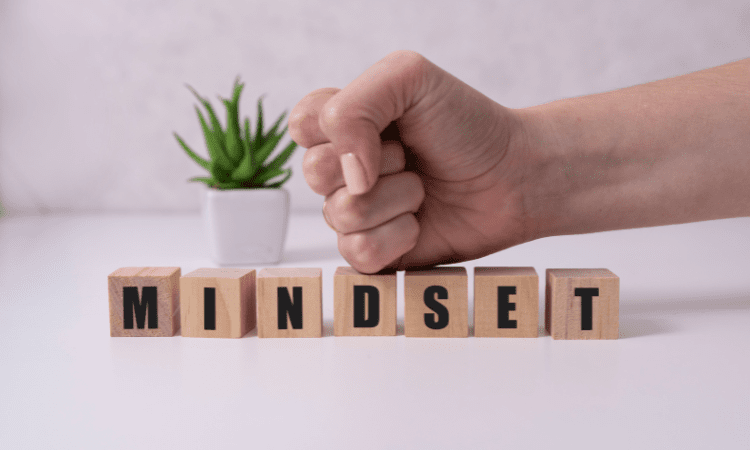
ここまで読んで、「うわー、やっぱり陶芸で生きていくのって大変そう…」と、ちょっと尻込みしちゃいましたか?大丈夫、大丈夫。いきなりプロを目指さなくたって、陶芸と関わる道はたくさんあります。むしろ、焦りは禁物。ここでは、これから陶芸を始めたいあなたに、「今すぐできること」をいくつか提案させてください。
まずは「趣味」として全力で楽しむのが最強のスタート
もしあなたが今、陶芸未経験なら、まずやるべきことは一つだけ。近所の陶芸教室を探して、体験コースに申し込むことです!「プロになるには、早くから修行しないと!」なんて考える必要は全くありません。
なぜなら、お金のことや将来のことを一切考えずに、ただただ無心で土に触れる時間こそが、あなたの「好き」という気持ちを一番育ててくれるからです。その「好き」という初期衝動こそが、この先どんな壁にぶつかっても乗り越えられる、最強のエンジンになります。
私も最初は、会社の福利厚生で使える陶芸教室に、友達と遊び半分で通い始めたのがきっかけでした。「うわ、土ってこんなに気持ちいいんだ!」「ろくろ、全然言うこと聞かない!でも面白い!」って、童心に返ったようにはしゃいでいました。あの時の純粋な楽しさがなかったら、今こうして文章を書いていることもなかったでしょうね。だから、まずは難しく考えず、趣味として全力で楽しむ。それが、遠回りに見えて、実は一番の近道なんです。
副業から始める「週末陶芸家」という選択肢
陶芸教室に通って、だんだん自分の作りたいものが作れるようになってきたら、次に考えるのが「週末陶芸家」という道です。平日は会社員として安定した収入を得て、土日や仕事終わりの時間を使って創作活動をする。このスタイル、今の時代にはすごく合っていると思います。
何が良いって、経済的な安心感がもたらす精神的な余裕です。正直に言いますけど、お腹が空いていたら、良い器なんて作れませんって!「この作品が売れなかったら、来月の家賃が払えない…」なんていうプレッシャーの中で作る作品は、どこか悲壮感が漂ってしまうもの。
でも、本業の収入があれば、「売れたらラッキー!」くらいの軽い気持ちで、本当に自分の作りたいものを、妥協なく追求できます。その自由な創作活動から生まれた作品の方が、結果的に人の心を打つ魅力的なものになったりするから不思議です。今はminneやCreemaのようなハンドメイドマーケットも充実しているので、週末陶芸家でも作品を発表する場はたくさんあります。まずは副業としてスモールスタートを切ってみる。これ、めちゃくちゃ賢い選択だと思いますよ。
技術だけじゃない「自分の世界観」を育てよう
陶芸教室に通っていると、ついつい「先生みたいに綺麗な形を作りたい」「もっとろくろが上手くなりたい」と、技術の向上ばかりに目が行きがちです。もちろん、技術は大切。でも、それと同じくらい、いや、それ以上に大切なのが「あなただけの世界観」を育てることです。
上手なだけの人なんて、世の中にいくらでもいます。でも、「あなたにしか作れないもの」は、あなたにしか作れない。じゃあ、その世界観ってどうやって育てるの?って思いますよね。それは、陶芸以外のいろんなものに触れることです。
美術館に行く、素敵なカフェで過ごす、旅行に出かける、映画を観る、本を読む、音楽を聴く…。一見、陶芸とは何の関係もなさそうな体験が、ある日突然、あなたの作品のインスピレーションになるんです。私なんて、この前見たSF映画の宇宙船のデザインから、次の花瓶のフォルムを思いつきましたからね(笑)。そういう、自分の中に蓄積された「好き」の引き出しを増やすことが、誰にも真似できない、あなただけのオリジナリティに繋がっていくんです。
年収だけが全てじゃない 陶芸が与えてくれる豊かさ
ここまで、年収だの、稼ぎ方だの、なんだかお金の話ばかりしてしまいましたね。でも、忘れないでほしいんです。私たちが陶芸に惹かれるのって、お金を稼ぎたいからだけじゃないですよね?陶芸には、年収というモノサシでは絶対に測れない、もっと深くて、温かい豊かさがあるんです。
土に触れる喜びと「無心」になれる時間
毎日スマホを見て、PCのキーボードを叩いて、頭の中は常に情報でパンパン…。そんなデジタルな日常に、ちょっと疲れていませんか?
陶芸は、そんな私たちを強制的にアナログな世界に引き戻してくれます。ひんやりと湿った土の感触。自分の手の力加減で、にゅーっと形を変えていく粘土。静かな部屋に響く、ろくろのモーター音。その時間だけは、仕事の悩みも、人間関係のストレスも、全部忘れて「無心」になれるんです。これって、最高のデジタルデトックスであり、マインドフルネスだと思いませんか?
私にとって、作陶は仕事であると同時に、一番のセラピーです。頭でごちゃごちゃ考えるのをやめて、ただ手の感覚に集中する。その時間が、すり減った心を優しく回復させてくれる。この感覚は、一度味わったら病みつきになりますよ。
自分の手で「暮らし」を創り出す感動
そして、陶芸の最大の魅力は、なんといっても自分の手で「暮らしの道具」を創り出せることでしょう。
初めて自分で作った、ちょっと歪んだお茶碗にご飯をよそって食べた時の感動。不格好なマグカップでコーヒーを飲んだ時の、なんとも言えない愛おしさ。道端の草花を、自作の一輪挿しに生けた時の、小さな誇らしさ。
それは、お店で買ってきたどんなに高価な器でも味わえない、特別な体験です。自分の手で作ったものが、自分の日常に溶け込んで、暮らしを彩っていく。それは、消費するだけでは得られない「創り出す喜び」そのものです。いつものコンビニのサラダが、自分で作ったお皿に盛り付けただけで、なんだかデパ地下のデリに見えたりするんですよ(笑)。そういう小さな魔法が、日々の暮らしを豊かにしてくれるんです。
まとめ

さて、陶芸家の年収という、ちょっと生々しいテーマから始まった今日の話、いかがでしたか?
結論として、陶芸家の年収は、平均値で見れば決して高くはありません。むしろ、アルバイトなどと兼業しなければ生活が成り立たない人が大半、というのが厳しい現実です。良い作品を作る技術だけでは不十分で、SNSでの発信力やブランディングといった「届ける力」、そして何よりあなたを応援してくれる「ファン」の存在が不可欠になります。
だからといって、「陶芸家になるのはやめた方がいい」と、私は言いたいわけでは全くありません。むしろ逆です。この現実を知った上で、それでも「やりたい」と思うのなら、あなたにはきっと、その道を歩んでいくだけの情熱があるはず。
いきなりプロを目指すのではなく、まずは趣味として全力で楽しむ。あるいは、本業を持ちながら「週末陶芸家」として活動する。そんな風に、自分に合った距離感で陶芸と付き合っていく道だってあります。大切なのは、年収という数字に振り回されるのではなく、「自分はなぜ、土に触れたいのか」「自分の手で、何を生み出したいのか」という原点を、決して見失わないことです。
陶芸は、お金には換えられない「心の豊かさ」や「暮らしの彩り」を、私たちに与えてくれます。この記事が、あなたの「好き」を、憧れのままで終わらせず、現実的な一歩へと繋げるきっかけになったなら、これ以上に嬉しいことはありません。
さあ、あなたも一緒に、泥んこになってみませんか?その先に、思いもよらない素敵な世界が待っているかもしれませんよ。










